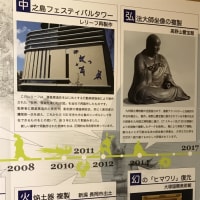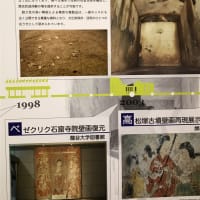台風14号で河川の氾濫が相次いだ。
ニュースで自治体の河川局の人などが「支流も含めて氾濫しないよう対策をとりたい」と言っている。
ただ、本当に可能なのだろうか?
そもそも河川の堤防はある一定の水位まで耐えられるようには設計されているが、それを超えた水位の場合は決壊のリスクがあるし、そもそも堤防自体は決壊しなかったとしても水位が堤防の高さを越えてしまえばやはり氾濫する。
上流から下流まですべて堤防が作られたとしたら、流域に降った雨はすべて河川に流れ込む。そして、満潮時には河口の水位が上がるうえに、低気圧や風の影響があれば、河口での浸水のリスクは逆に高まるのではないか。
それを回避するためには、雨水を一時溜めておく調整地が作られるが、降雨が連続して調整地がいっぱいになると、そこからの放水が逆に下流の氾濫の要因になる(これはダムも同じ)
とすると、対応策としては以下のものが考えられる。
① 堤防の計画高水位のレベルを今以上に上げる
② 河川の拡幅や調整地の増設をする
③ 流域住民に河川の計画高水位や降水量による水位変化の情報を与え、タイムリーに避難勧告をする
①②は事前予防だが
①は既存の橋を架け替えたり、堤防の補強(高くすれば幅広くする必要がある)のために周辺の道路や住宅を変更する必要がある
②はもっと広範囲に収用手続きが必要になる
さらに予算や工期の制約も大きい
と一気に進めるにはハードルが高い。
③は最近各自治体がハザードマップを出すようになり、かなり改善されているが、前提が地域の降水量をベースにしており、河川の氾濫においては流域全体の降水量や潮の干満や気圧等による水位の変動も含めての危険度を示せればよりよいと思う。
ただ、そうすると、「危険」とされた地域は地価が下落する、という観点からの反対も考えられる。
更に将来、危険とされた地域の地価がかなり下がった場合は、特に都市部において「リスクを承知で安いところに住む」ことを選択する人々(必ずしも貧困層とは限らず、都心居住のメリットを優先する人など)も出てくるであろう。
そうすると、想定をはるかに上回る自然災害が到来したとき、日本でも今回のニューオーリンズと同じことが起きないとも限らない。
結局、
(1) どこまでのリスクを社会として許容するか、
(2) 個人の判断のためにいかに適切かつ十分なリスク情報を与えるか、
(3) リスクを負うという判断をした人々に対してどのレベルのセーフティーネットを用意し、また被害回避のために強制的な措置をとるか
をどのレベルでバランスさせるかの問題になるのだろう。
そこについて、地域住民のコンセンサスと行政の説明責任の履行(一言で言えば「民主的プロセス」)が確保されれば、万が一被害があった場合にも、容認していたリスクが顕在化したということで、無益な非難合戦にならずにすむように思う。
少なくとも今回のKatrinaをめぐる議論見る限り、アメリカにはそれがなかったのだろう。
では、日本はどうだろうか。
ニュースで自治体の河川局の人などが「支流も含めて氾濫しないよう対策をとりたい」と言っている。
ただ、本当に可能なのだろうか?
そもそも河川の堤防はある一定の水位まで耐えられるようには設計されているが、それを超えた水位の場合は決壊のリスクがあるし、そもそも堤防自体は決壊しなかったとしても水位が堤防の高さを越えてしまえばやはり氾濫する。
上流から下流まですべて堤防が作られたとしたら、流域に降った雨はすべて河川に流れ込む。そして、満潮時には河口の水位が上がるうえに、低気圧や風の影響があれば、河口での浸水のリスクは逆に高まるのではないか。
それを回避するためには、雨水を一時溜めておく調整地が作られるが、降雨が連続して調整地がいっぱいになると、そこからの放水が逆に下流の氾濫の要因になる(これはダムも同じ)
とすると、対応策としては以下のものが考えられる。
① 堤防の計画高水位のレベルを今以上に上げる
② 河川の拡幅や調整地の増設をする
③ 流域住民に河川の計画高水位や降水量による水位変化の情報を与え、タイムリーに避難勧告をする
①②は事前予防だが
①は既存の橋を架け替えたり、堤防の補強(高くすれば幅広くする必要がある)のために周辺の道路や住宅を変更する必要がある
②はもっと広範囲に収用手続きが必要になる
さらに予算や工期の制約も大きい
と一気に進めるにはハードルが高い。
③は最近各自治体がハザードマップを出すようになり、かなり改善されているが、前提が地域の降水量をベースにしており、河川の氾濫においては流域全体の降水量や潮の干満や気圧等による水位の変動も含めての危険度を示せればよりよいと思う。
ただ、そうすると、「危険」とされた地域は地価が下落する、という観点からの反対も考えられる。
更に将来、危険とされた地域の地価がかなり下がった場合は、特に都市部において「リスクを承知で安いところに住む」ことを選択する人々(必ずしも貧困層とは限らず、都心居住のメリットを優先する人など)も出てくるであろう。
そうすると、想定をはるかに上回る自然災害が到来したとき、日本でも今回のニューオーリンズと同じことが起きないとも限らない。
結局、
(1) どこまでのリスクを社会として許容するか、
(2) 個人の判断のためにいかに適切かつ十分なリスク情報を与えるか、
(3) リスクを負うという判断をした人々に対してどのレベルのセーフティーネットを用意し、また被害回避のために強制的な措置をとるか
をどのレベルでバランスさせるかの問題になるのだろう。
そこについて、地域住民のコンセンサスと行政の説明責任の履行(一言で言えば「民主的プロセス」)が確保されれば、万が一被害があった場合にも、容認していたリスクが顕在化したということで、無益な非難合戦にならずにすむように思う。
少なくとも今回のKatrinaをめぐる議論見る限り、アメリカにはそれがなかったのだろう。
では、日本はどうだろうか。