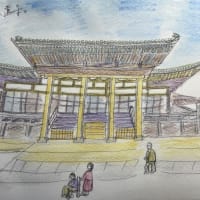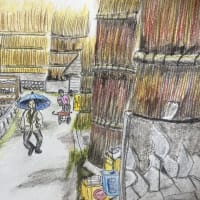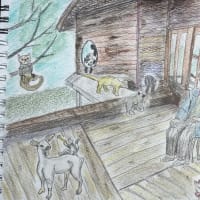御所平へ続く林道は今、リニア新幹線のトンネル工事の為、毎日大きなトラックが往来しています。

傍らの石仏が寂し気に工事を見守っているように見えるのは私だけでしょうか?


この大鹿村という場所。
今、交通手段が車や電車になり、交通の便では不便な山の中という印象を拭い切れないけれど、
宗良親王を匿い守る為には絶好の場所だったーと、ぐるりと四方を見渡してみると納得するのです。
特に大河原は東西を聳え立つ南アルプス赤石連邦と伊那山地に囲まれている、地球規模での要塞となっているわけで、
日本中探してもこんな地形の所はないのではないかと思うのです。
確かに下伊那地方に落ち武者が隠れ住んだのも頷ける・・。そして、
人が歩いて生活していた時代の事を考えると、
この大河原からは赤石山脈を越える事も不可能ではなく、南下して地蔵峠を越え遠山へ、そして青崩峠を越えれば静岡に至る秋葉街道。
そのまま南下すれば浜松方面、愛知県へ至る。
下の写真の崖崩れ跡が傷跡の様に残る伊那山地の北端大西山を登り、唐松峠を越えて飯田へ、そして木曽の御坂峠を越え岐阜に至る東山道へ。

北に向かえば分杭峠を越えて今の伊那市長谷から高遠へ入り、入笠山を越えて富士見、山梨から関東へ、高遠から杖突峠を越えて諏訪方面へと四方に道は広がっている。
それも、恐らくはそんなに長い時間を費やさなくて峠越えはできただろうと実際に歩いてみて思うのです。
主要地域のほぼ中心にあり、山を越えればどこへも最短距離で行けるというこの場所にリニアが通るのも、
皮肉でもありながら納得がいく気もするのです。
宗良親王を敵の攻撃から守る為、山奥の釜沢の奥に御所を建て、宗良親王に仕えたのが大河原城主であった香坂宗高。
南北朝時代、30余年にわたり皇子を守り通し、1407年、大河原城で没したとされています。
大正4年、香坂崇高は宗良親王に忠誠を尽くしたその功績に対して従四位を送られ、
香坂神社に祭られていると書かれていました。

香坂宗高の居城であった大河原城跡は
小渋川を望む絶壁の上にあり、険しい地形を生かした城であったことが想像されます。、
今は城跡碑と説明版が木々に囲まれて静かに立てられていました。

その他、この赤石岳を望む上蔵地域には

長野県最古(鎌倉時代 1160年建立)の木造建築として国の重要文化財に指定されている福徳寺や

木造二階建ての廻り舞台のある野々宮神社などもあり、歴史の古さを感じさせてくれます。

小渋川に架る小渋橋は国の登録有形文化財に指定されています。

「山深き 世のひとこともきこえぬに 何を空蝉 なきくらすらん」
「世のうめき 見えぬ山路の蔦の風 いかにふけはか 先うらむらん」
釜沢集落の奥、宗良親王が隠れ住んだ安住の地、御所平まで歩いてみると、
700年も前の句も身に染みて理解できる・・・そんな静かな南アルプスの麓。
( 参考 おおしか村ってこんな村)
リニアのトンネル工事のトラックが歴史ロマンの邪魔をする・・・