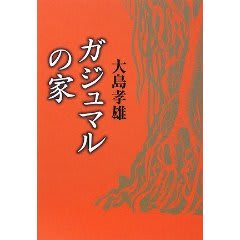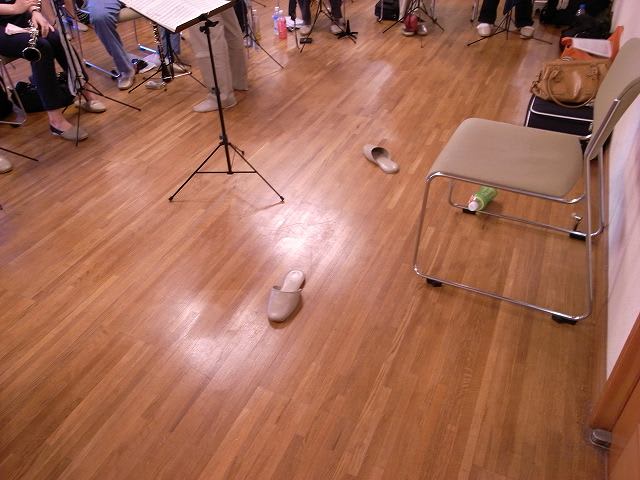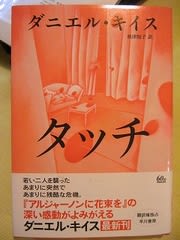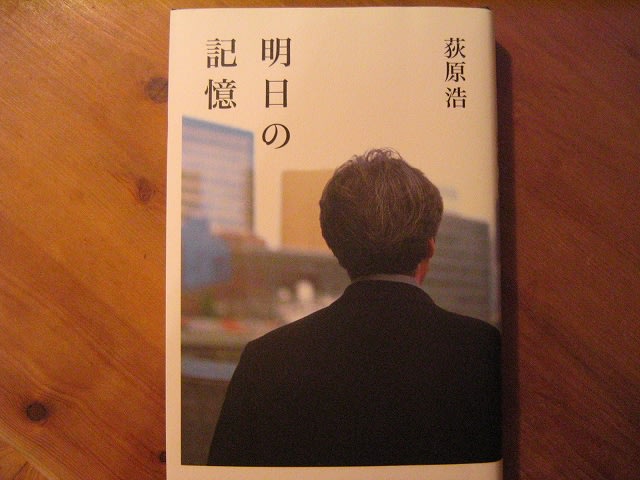この画家が、いかにタヒチという場所の光、色、土のにおいなんかに衝撃を受け、魅了されたか。タヒチには女がいて、子供がいて、月の女神がいて、鮮やかな花があって、夜になれば悪霊がさまよう。岡本太郎さんが1972年に書いた「沖縄文化論~忘れられた日本」で、沖縄発上陸の印象を“「何もないこと」の眩暈”などと書いているが、ゴーギャンにとってのタヒチもそれに通じるものがあったような気がする。
今まであまり知らなかったゴーギャンの人物像を新たに知ることができたのも収穫だった。
ゴーギャンは幼少期からの英才教育でも何でもなく、26歳になって人に勧められて初めて絵の学校に入る。もともと絵の鑑賞は好きだったらしく、株で大もうけしてセザンヌやマネの絵を買っていたらしい。よほど儲かったのだろうが、後に株の暴落で手放した。そして、その暴落の経験から「サラリーマンをやっていても、身分は不安定だ」と悟り、絵で食べていくことを決心。どう考えてもそっちの方が不安定だと思うが・・・。
案の定、ゴーギャンは一生、貧乏生活だった。
と、なかなかおもろい生き方をしたオッサンだったのですな。
まあ、他人事だからそういえるのであって、奥さんや子供にとってはいい迷惑だったろうが。
ゴーギャンは妻子を本国に残してタヒチに行っているのだが、タヒチで妙に現地妻が多い。
それも13歳くらいの女子を何人も孕ませてしまっている。ほとんど犯罪である。
一説には、バイセクシャルでどっちもかなりのものだったという(さすがにこれは国立美術館の展示には書いてありませんが)。ゴッホの耳切り事件で終焉するゴッホとの同居生活も、もしかしたら男色愛憎劇だったのでは?と憶測してしまう。
自分をキリストに見立てて「絵画の神」的に思っていたふしもあり、自尊心の強い結構嫌なヤツだったかもしれない。
ともあれ、ほのぼのとしたタヒチの自然に惹かれた孤高な哲学者、という勝手なイメージが、見事に崩れました(笑)
それにしても、国立近代美術館の旧態依然とした運営はどうにかならないですかねぇ。
開館時間が「平日午後5時まで」ですよ。
勤め人は絶対行けやしない。
ご丁寧に、ミュージアムショップまで5時に終わるのだそうだ。
しかも、4時20分に入ったら、音声ガイドの貸し出しはすでに終了していた。
来場者を増やすチャンスも、収益を上げるチャンスも、みすみす逸している。
私だけでなく、ほかの客からも「5時って、まだ昼じゃない
 」と不満の声が。
」と不満の声が。パリのルーブルは、通常は午後6時までだが、水・金は夜間開館で9時45分までだ。
日本の美術館もせめてこのくらいにしてほしい。
いっそのこと独立行政法人にでもしたら、もう少し来場者志向の運営になるのかも。
「ゴーギャン展」は、9月23日まで。
絵の素晴しさとともに、ぜひその“人間くささ”をご鑑賞ください。

 国立近代美術館近くの皇居・平川門。
国立近代美術館近くの皇居・平川門。
★1クリックの応援をお願いします

人気Blogランキング














 」のバンコクです。これは夕暮れのバッポン通り。
」のバンコクです。これは夕暮れのバッポン通り。 と思っただろう。今もまだ混乱は続いているようだ。
と思っただろう。今もまだ混乱は続いているようだ。