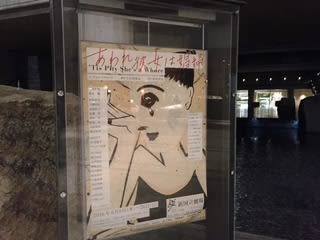1週間近く経ってしまいましたが、5月27日に新国立劇場のオペラLOHENGRINを見ました。
このオペラは2012年に上演したものの再演です。
実は2012年にも単身赴任先から帰ってこのオペラは見ていましたので、今回2回目の鑑賞となります。
何と言ってもLOHENGRIN役のクラウス・フロリアン・フォークトの歌にものすごい感銘力があります。新国立のHPには、「神々しい美声、そして端正な容姿」とありますが、本当に神の使いとしてエルザ・フォン・ブラバンドを救出するために現れた聖杯の騎士の神々しい声を聴いているような気がします。フォークトは、Staats Oper unter den Lindenでは「ニュルンベルクのマイスタージンガー」ではヴァルター役で出ているそうですが、このような世界で活躍する歌手が、来日公演ではなく、新国立劇場の通常の上演の演目に出演してもらえることは大変あり難いことです。フォークトの歌声を聴くだけでも、来た甲斐がありました。オルトルート役の歌手も、歌もうまければ憎々しい演技もうまく、邪悪な企みでフォークト=聖杯の騎士の行いを妨げようとする役を上手に演じていました。この2人と比べてしまうと他の歌手は、特別に来日した歌手も含め、いささか見劣りしてしまうことは否定することができず、エルザ(無表情なのは、演出ではなく、演技の余裕がなかったからのように見受けられました)とテルラムントはついていくのが大変だったのではないかと思われました。
演出は、シンプルといえばシンプルです。ローエングリンは白鳥にひかれるのではなく、白鳥をデザインしたゴンドラからスーパー歌舞伎のように天井から姿を現します。エルザは、天然系という演出なのでしょうか、第1幕では背中にフードのような不思議なものをつけています(これがブラバンド公国の公女であるエルザの負っている重みの象徴でしょうか。)。第2幕では、LEDライト付きの板の上にのって登場し、その上には“はかなさ”の象徴である傘のようなものがあります。そして、オルトルートから疑念を植え付けられた後に登場する時には、“フープドレス”というらしいのですが、頭上に渦巻きのように巻きついたものがついています。これは、オルトルートの埋め込んだ“疑念”の象徴でしょうか。
第3幕の第2場では、ローエングリンもエルザも黒を基調にした重苦しい衣装に着替えて登場です。
演出もシンプルながら楽しめましたし、なんといっても美術・衣装は、あの光の魔術師として有名なロザリエですので、光をうまく使用した舞台セットになっていました。
この上演を最初に見た2012年時点では知らなかったのですが、ロザリエといえば、2013年にライプツィヒに行った際に、造形美術館で、企画展”WELTENSCHÖPFER RICHARD WAGNER, MAX KLINGER, KARL MAY MIT RÄUMEN VON ROSALIE” 「世界の創造者―リヒャルト・ワーグナー,マックス・クリンガー,カール・マイ―ロザリエによる空間とともに―」を見ていますが、あのロザリエです。スクリーンに映し出すワッフルのような格子、LEDライトなど、さすが本業は光を用いた現代アーティストだけありました。
大変満足のいくオペラでありましたが、やはりオケのほんの一部、否、管楽器の一部というか、おそらくお一人、今回もまた若干問題があったように思います。フォークトのような歌手の出る演目で、しかも前奏曲の段階から??という演奏は避けてもらいたいような気がします(ちなみにパルジファルの上演の時も同じパターンだったような気がします。)。これでは、オケ全体が悪いといわれかねませんので。
スタッフ
【指揮】 飯守泰次郎
【演出】 マティアス・フォン・シュテークマン
【美術・光メディア造形・衣裳】 ロザリエ
【照明】 グイド・ペツォルト
【舞台監督】 大澤 裕
キャスト
【ハインリヒ国王】 アンドレアス・バウアー
【ローエングリン】 クラウス・フロリアン・フォークト
【エルザ・フォン・ブラバント】 マヌエラ・ウール
【フリードリヒ・フォン・テルラムント】 ユルゲン・リン
【オルトルート】 ペトラ・ラング
【王の伝令】 萩原 潤
【ブラバントの貴族Ⅰ】 望月哲也
【ブラバントの貴族Ⅱ】 秋谷直之
【ブラバントの貴族Ⅲ】 小森輝彦
【ブラバントの貴族Ⅳ】 妻屋秀和
【合唱指揮】 三澤洋史
【合唱】 新国立劇場合唱団
【管弦楽】 東京フィルハーモニー交響楽団
【協力】 日本ワーグナー協会
【芸術監督】 飯守泰次郎
あらすじ
【第1幕】東方からの侵略に備えた兵力要請のためドイツ国王ハインリヒがブラバント公国にやってくると、公国に不和が広がっていた。その訳を国王が尋ねると、ブラバント公の跡取りゴットフリート王子を姉のエルザが殺した、とテルラムント伯が告発する。エルザは無実を訴え、夢に見た騎士が現れて自分を救ってくれるはずだと語る。神明裁判でエルザの代わりに戦う騎士を募ると、白鳥の引く小舟にのった騎士がやってくる。エルザのために遣わされたという美しい騎士は、勝利したら彼女の夫となり国を治めるが、ひとつ約束を守ってほしい、と言う。それは、決して名前や素性を尋ねないこと。エルザは約束を守ると誓う。騎士とテルラムントが戦い、騎士が勝利する。
【第2幕】追放されたテルラムントと彼の妻である魔女オルトルートは、騎士は素性を問われると力を失うと見抜き、復讐に燃える。オルトルートはエルザに、素性を明かさない騎士は突然姿を消すのではないか、と吹き込む。夜が明け、婚礼のため大聖堂へ向かうエルザに、オルトルートは、裁判で騎士が勝ったのは魔法を使ったからだと叫ぶ。騎士はテルラムントに素性を問われるが、エルザ以外に答える必要はないとあしらう。エルザの心は激しく揺れている。
【第3幕】結婚式後、初めて2人だけの甘い時を迎えているが、エルザは愛する人を名前で呼べない辛さを訴え、とうとう騎士に名前を尋ねてしまう。騎士は国王の前で素性を語り出す。彼は、パルジファルの息子で聖杯の騎士、名はローエングリン。素性を知られたからには去らねばならないという。白鳥の引く小舟にローエングリンが乗り、白鳥の首の鎖をはずすと、ゴットフリート王子が現れる。王子は殺されたのではなく、オルトルートの魔法で白鳥にされていたのだ。ローエングリンが去った後、残されたエルザは悲しみのあまり、くずれおちる。