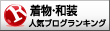第2次世界大戦中、リトアニア領事代理として日本政府に背いて多くのユダヤ難民にビザを発給し、
彼らの命を救った杉原千畝の半生を映画化。
監督は、日本で生まれ育ったアメリカ人であるチェリン・グラック。
今でこそ彼の出身地である岐阜県八百津町には、立派な杉原千畝記念館もできたそうですが
岐阜出身の私が子どもの頃は、その名前を聞いたこともありませんでした。
日本政府が公式に謝罪し、名誉回復が行われたのは2000年、
本人が亡くなって14年も後のことだというのだから、無理もありません。

戦後、日本の外務省をユダヤ人男性が訪ねるところから映画は始まります。
杉原の消息を尋ねる男に、外務省役人は、そんな人間はいなかったとつれなく答える。
国の意向に逆らった人間として、彼の名前は外務省の記録から抹殺されていたのです。
日本のシンドラーと呼ばれる彼のことをもっと知りたいと、楽しみにしていたのですが…
美化し過ぎず、淡々と描いた点には好感が持てるのですが
あまりに淡泊すぎて、物足りないという感じも否めない。
主役を演じた唐沢寿明が、これはエンターティメントとして観て欲しいと言っていたようですが
エンタメにしては長すぎ(2時間半弱)、そして盛り上がりに欠けている気がします。
例えば、杉原が汽車に乗ってまでもサインし続けたという有名な話は、
幸子夫人の著書にも書かれているのに、映画ではあっさりと汽車に乗り込んでしまっている。
やっとの思いでビザを手にした何千人ものユダヤ人が、ソ連を列車で横断するシーンにしても
妙に綺麗な恰好で、整然と座り込んでいる。
当時、あの広いソ連をぎゅう詰めの列車で数週間かけて横切ることが、どんなに大変であったか、
そしてソ連兵に金品を没収されながらようやく辿り着いたウラジオストク、
そこから敦賀港を経て、どのようにアメリカなどに行くことができたのか、その辺も観たかったのですが。
そんなこと言ったら、もっと長くなっちゃうか。
終盤のダンスシーンなど、削れるところもあったと思うんだけど…

英語、露語、独語、仏語など数ヵ国語を操るインテリジェンス・オフィサー(諜報外交員)と
としての顔も持つ杉原の様子が、映画では淡々と描かれていました。
「Persona Non Grata(ペルソナ・ノン・グラータ)」(好ましからざる人物)という
ソ連からの評価である言葉が、どうして映画の副題になっているのだろうと不思議でしたが
次の説明を読んで納得しました。
”監督は映画の英語タイトル「Persona Non Grata(ペルソナ・ノン・グラータ)」
(好ましからざる人物)に強いこだわりをみせる。
千畝はその諜報活動によって、ソ連側から「Persona Non Grata」の指定を受けて入国を
拒否され、在モスクワ日本大使館へ赴任できなくなる。
「軽蔑されて締め出された経験」を持たなければ、排外される人間の気持ちはわからないという思いと、
戦時下で千畝のような行動をした人は他にもいたという思いを込めているからだ。”

ポーランドでのオールロケで撮ったというこの作品も、その撮影時、
現地のエキストラの人々に感謝の言葉を言われたといいます。
多くの日本人に観て頂きたい作品です。
チェリン・グラック監督に聞く http://www.nippon.com/ja/people/e00091/?pnum=1
映画「杉原千畝」 http://www.sugihara-chiune.jp/