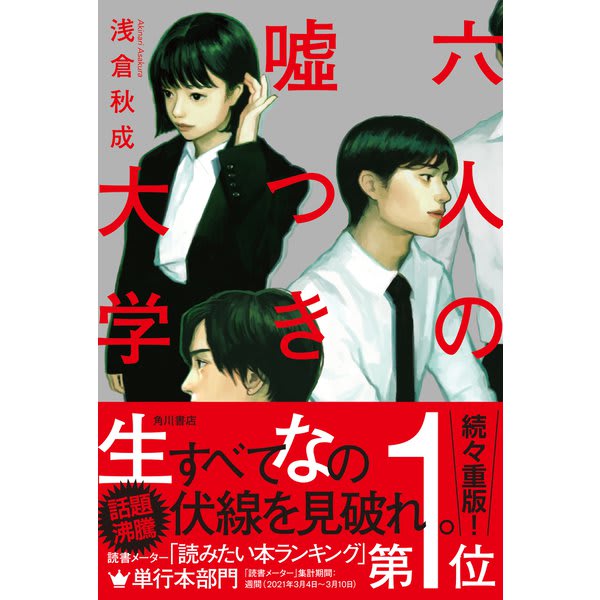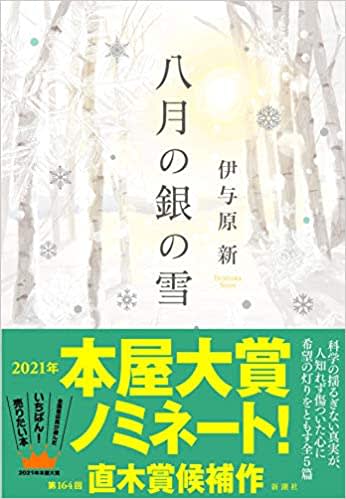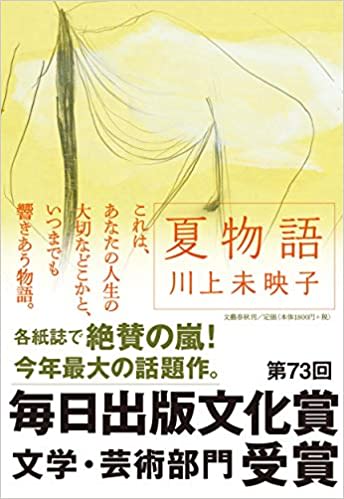「夜空に泳ぐチョコレートグラミー」
「52ヘルツのクジラたち」で2021年の本屋大賞を取った町田その子の作品。
5編の短編集、その中でも私は、デビュー作という「カメルーンの青い魚」が好きです。
閉塞感漂う地方の小さな町で、恵まれない環境や理不尽な社会に負けず、なんとか生きて行こうとしている男女の話。
シングルマザーである母親に捨てられ、祖母に育てられたサキコと、児童養護施設育ちのりゅうちゃん。
この書き出しがふるっています。
「大きなみたらし団子にかぶりついたら、差し歯がとれた」
こんなマヌケな書き出しで、こんなヒリヒリするほど切ない物語が展開するとは。
この短編集の登場人物たちは皆、どうしようもない生きづらさを抱えていますが、なんとかこの世界を泳いでいこうと、自分の小さなヒレを必死に動かしているのです。
5編の短編は何処かで繋がっていて、最後に一つの、希望に満ちた輪となります。
「52ヘルツのクジラたち」で2021年の本屋大賞を取った町田その子の作品。
5編の短編集、その中でも私は、デビュー作という「カメルーンの青い魚」が好きです。
閉塞感漂う地方の小さな町で、恵まれない環境や理不尽な社会に負けず、なんとか生きて行こうとしている男女の話。
シングルマザーである母親に捨てられ、祖母に育てられたサキコと、児童養護施設育ちのりゅうちゃん。
この書き出しがふるっています。
「大きなみたらし団子にかぶりついたら、差し歯がとれた」
こんなマヌケな書き出しで、こんなヒリヒリするほど切ない物語が展開するとは。
この短編集の登場人物たちは皆、どうしようもない生きづらさを抱えていますが、なんとかこの世界を泳いでいこうと、自分の小さなヒレを必死に動かしているのです。
5編の短編は何処かで繋がっていて、最後に一つの、希望に満ちた輪となります。

「むらさきのスカートの女」
2019年芥川賞受賞作。
近所に住むむらさき色のスカートをはく女の人が気になって仕方がない、黄色のカーディガンの「わたし」。
むらさきの女をつけ回し、同じ職場で働くように誘導し、アパートまで追いかけ、彼女の生活を逐一観察する。
最初は、近所でも浮いているというむらさきの女が余程の変わり者かと思って読み進めますが、職場でも普通に働き、そこの上司と不倫もし、公園で子供たちと遊び、普通の女性だということが分かって来る。
むらさきの女を見下していた「わたし」の方が、実はもっと孤独で問題ありの人間であることが明らかになって来る。
最後にむらさきの女は何処かに消え、気が付くとそこに「わたし」がすっぽりと収まっていた。
一人の人間の見方を裏返すと、まるで違う面が見えてくることの恐ろしさを書きたかったのでしょうか?
しかし、これが芥川賞とは…私にはその面白さは、そこまで分かりませんでした。