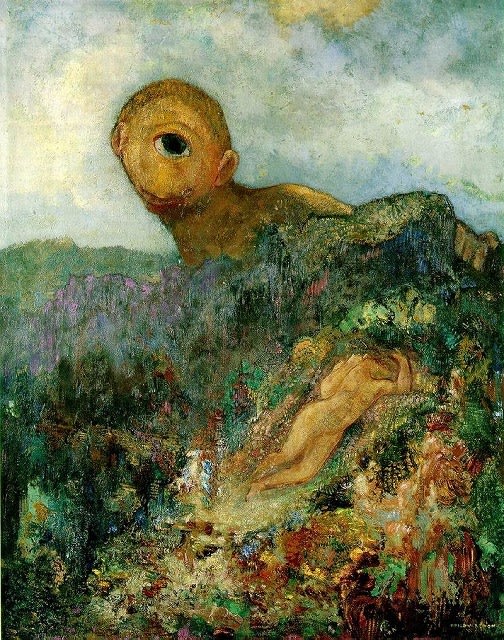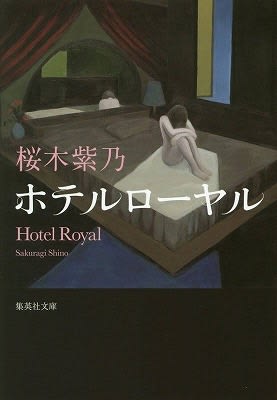伊東マンショの肖像画に触発されて、遠藤周作の「侍」を読んでみました。
ごく若い頃、学生時代に読んだ筈なのですが、詳細は綺麗に忘れて
臭くて暗くて絶望的だったというイメージしか憶えていない。
再読しても、やはり同じ印象を受けました。
”湿った藁の臭いは宣教師の坐っている牢獄にも充満していた。
その臭気には今までここに入れられていた信徒たちの体臭や尿の臭いも入り混じり、それが時折つよく鼻を刺した。”
などという描写がどうも心に残る。
やれやれ私の感受性、加齢しても同じということか。
1613年に伊達政宗によって送られた慶長遣欧使節団の実話を基にした歴史小説。
宣教師ルイス・ソテロと支倉常長がモデル。
藩主の命によりローマ法王への親書を携えて、「侍」は海を渡った。
あの時代に何か月もかけて太平洋を渡り、メキシコ、スペイン、バチカンに赴く。
大洋では何度も嵐に見舞われ、メキシコの砂漠や高山、或いはスペインの原野をひたすら歩き、
スペイン国王、ローマ教皇に謁見するために、不本意ながら洗礼まで受けるが
藩が望む貿易交渉は成立しなかった。
失意のうちに7年という月日をかけて帰国すると、日本は鎖国に方針転換、
キリシタンは御法度となっていた。
使節団の苦労はすべて「なかったこと」にされ、あろうことか受洗の罪を問われることになる。
野心と闘争心に燃える宣教師と、すべてを受け入れ、主君の為に困難な旅を続ける侍。
対照的であるが、何一つ叶わず、何一つ報われなかったという結果は同じ。
失意と喪失感のうちに、宣教師は火あぶりの刑に、侍は切腹の刑に処せられる。
最後にその侍の背中に、先に受洗した忠実な使用人が声をふりしぼる。
”「ここからは…あの方がお供なされます」
侍は立ち止まり、ふりかえって大きくうなずいた。
そして黒光りのするつめたい廊下を、彼の旅の終わりに向かって進んで行った”
「主は汝と共に、汝の霊と共に、あれよかし」
これがクリスチャンであった著者の最大のテーマか。
ちなみに、伊東マンショ達少年使節団については、宣教師の言葉として
”かつてペテロ会のヴァリニャーノ管区長が、乞食にも等しい少年たちを貴族の子供と偽り、
使節としてローマに送ったが、向うでは誰にも怪しまれることはなかった”
という描写があるだけでした。
「侍」 https://tinyurl.com/y9uvzkxr