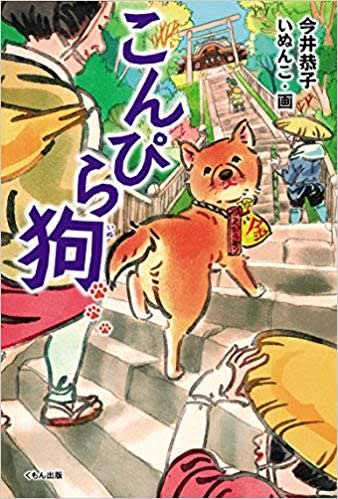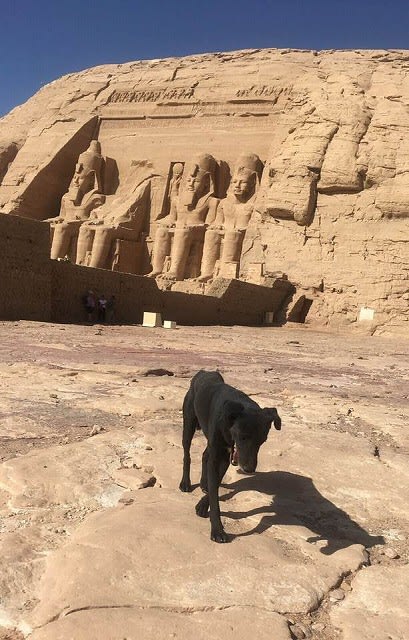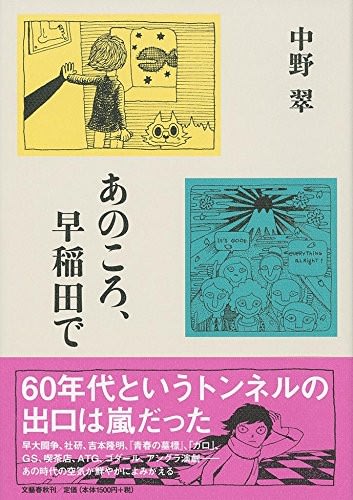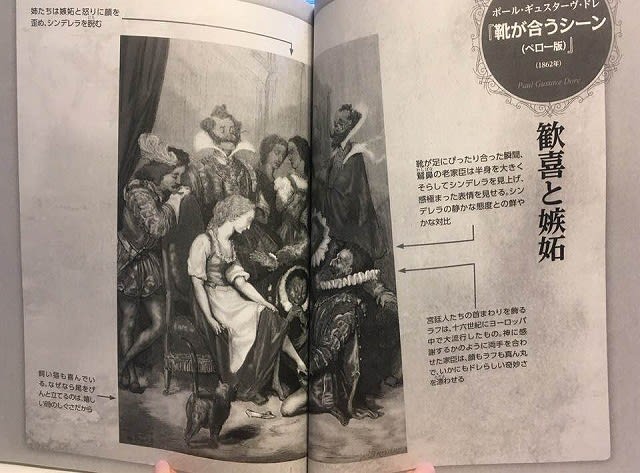”ゲルニカを消したのは誰だ?
衝撃の名画を巡る陰謀に、ピカソを愛する者たちが立ち向かう。
現代と過去が交錯する怒濤のアートサスペンス! ”(amazonより)
1937年第二次世界大戦中のパリ、そして21世紀初め9.11同時多発テロ直後のニューヨーク、
二つの物語が同時に進行します。
パリで愛人のドラ・マールと暮らしていたピカソに、パリ万国博スペイン館に
展示する壁画制作依頼が来る。
そこへバスク地方ゲルニカが、ナチスによって襲撃されたという知らせが入る。
もう一つの舞台は21世紀のニューヨーク、MoMA(ニューヨーク近代美術館)に
キュレーターとして勤める瑤子は、9.11テロで最愛の夫を亡くす。
悲しみに打ちひしがれながら瑤子は、MoMAの企画展に反戦の意を込めて
ゲルニカを展示したいと奔走する。
しかしスペイン側は頑なにそれを拒否し、そこにバスクのテロ組織が関わって
瑤子は誘拐されてしまう。
美術品を巡っての史実にフィクションを織り交ぜた、原田マハ得意のスタイルです。
過去の部分は、スペインの大富豪パルド・イグナシオとMoMA理事長の
ルース・ロックフェラー以外は全部実在の人物であるらしい。

衝撃の名画を巡る陰謀に、ピカソを愛する者たちが立ち向かう。
現代と過去が交錯する怒濤のアートサスペンス! ”(amazonより)
1937年第二次世界大戦中のパリ、そして21世紀初め9.11同時多発テロ直後のニューヨーク、
二つの物語が同時に進行します。
パリで愛人のドラ・マールと暮らしていたピカソに、パリ万国博スペイン館に
展示する壁画制作依頼が来る。
そこへバスク地方ゲルニカが、ナチスによって襲撃されたという知らせが入る。
もう一つの舞台は21世紀のニューヨーク、MoMA(ニューヨーク近代美術館)に
キュレーターとして勤める瑤子は、9.11テロで最愛の夫を亡くす。
悲しみに打ちひしがれながら瑤子は、MoMAの企画展に反戦の意を込めて
ゲルニカを展示したいと奔走する。
しかしスペイン側は頑なにそれを拒否し、そこにバスクのテロ組織が関わって
瑤子は誘拐されてしまう。
美術品を巡っての史実にフィクションを織り交ぜた、原田マハ得意のスタイルです。
過去の部分は、スペインの大富豪パルド・イグナシオとMoMA理事長の
ルース・ロックフェラー以外は全部実在の人物であるらしい。

数年前、マドリードのソフィア王妃芸術センターでこの絵を観ました。
縦3.5m、横は8m近い巨大な絵です。
それほど混んでいない美術館の中で、そこだけ黒山の人だかりができていました。
訳がわからないまま、反戦絵画としての迫力に私も圧倒されました。
この絵がゲルニカ爆撃を表しているということは知っていましたが
その制作前後にピカソのそんな葛藤があったこと、
パリ万博の展示以後、あちこちを流転していたことは知りませんでした。
この絵を特に好きでない私にとっては、本作全体が気負いすぎという印象が
否めませんが、著者が元MoMAのキュレーターであったという事実が
説得力を増している気がします。
テロ組織に殺されそうになってさえ、
「ゲルニカは誰のものでもない、私たちのもの。
平和を望む世界中のすべての人たちのもの」
と瑤子は叫ぶのです。
最初から最後まで緊迫した物語の中で一つの救いは、何度も登場する「トルティージャ」。
これはジャガイモがたっぷり入った、素朴なスペイン風オムレツです。
「暗幕のゲルニカ」 https://tinyurl.com/y3skf37t
縦3.5m、横は8m近い巨大な絵です。
それほど混んでいない美術館の中で、そこだけ黒山の人だかりができていました。
訳がわからないまま、反戦絵画としての迫力に私も圧倒されました。
この絵がゲルニカ爆撃を表しているということは知っていましたが
その制作前後にピカソのそんな葛藤があったこと、
パリ万博の展示以後、あちこちを流転していたことは知りませんでした。
この絵を特に好きでない私にとっては、本作全体が気負いすぎという印象が
否めませんが、著者が元MoMAのキュレーターであったという事実が
説得力を増している気がします。
テロ組織に殺されそうになってさえ、
「ゲルニカは誰のものでもない、私たちのもの。
平和を望む世界中のすべての人たちのもの」
と瑤子は叫ぶのです。
最初から最後まで緊迫した物語の中で一つの救いは、何度も登場する「トルティージャ」。
これはジャガイモがたっぷり入った、素朴なスペイン風オムレツです。
「暗幕のゲルニカ」 https://tinyurl.com/y3skf37t