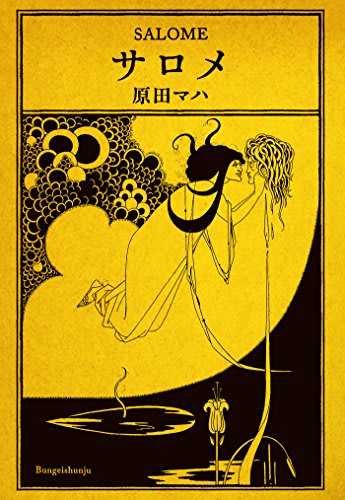サンフランシスコの心療内科のオフィスで、老精神医エド・ウィルソンは
壁に掛けられた海の絵を観ながら、半世紀以上前の沖縄での日々を思い出していた。
彼は若い頃、太平洋戦争終結直後の沖縄へ軍医として派遣された。
幼い頃から美術を愛し、自らも絵筆をとる心優しいエドは、精神を病んだ兵士を診る傍ら、
愛車を乗り回して憂さを晴らし、ある日不思議な場所に辿り着く。
「ニシムイ・アートヴィレッジ」と名付けられたそこは、みすぼらしい掘立小屋の集まりだが
誇り高い沖縄の若き画家たちが集まった美術の楽園であった。
その出会いが彼らの運命を変えて行く…
凄惨を極めた沖縄の地上戦。
終戦直後も食糧難、物資の欠乏、米兵による暴行と、厳しい受難は続く。
そうした中で良家の息子であるエドは、軍医としての任務に携わる傍ら、
本国の親から送られた真っ赤なオープンカーに乗って休日にドライブする。
彼の愛車ポンティアック1948シルバーストリークというのは、こんな感じらしい。
壁に掛けられた海の絵を観ながら、半世紀以上前の沖縄での日々を思い出していた。
彼は若い頃、太平洋戦争終結直後の沖縄へ軍医として派遣された。
幼い頃から美術を愛し、自らも絵筆をとる心優しいエドは、精神を病んだ兵士を診る傍ら、
愛車を乗り回して憂さを晴らし、ある日不思議な場所に辿り着く。
「ニシムイ・アートヴィレッジ」と名付けられたそこは、みすぼらしい掘立小屋の集まりだが
誇り高い沖縄の若き画家たちが集まった美術の楽園であった。
その出会いが彼らの運命を変えて行く…
凄惨を極めた沖縄の地上戦。
終戦直後も食糧難、物資の欠乏、米兵による暴行と、厳しい受難は続く。
そうした中で良家の息子であるエドは、軍医としての任務に携わる傍ら、
本国の親から送られた真っ赤なオープンカーに乗って休日にドライブする。
彼の愛車ポンティアック1948シルバーストリークというのは、こんな感じらしい。

彼に悪気はなくても、住む家も破壊され、その日の食べ物にも事欠く沖縄の人々が
そのこと自体に傷つけられたことは想像に難くない。
そしてそうしたことは、彼らの友情が続く中にも多々起きるのです。
悪気がなくてもどうしようもなく傷つけることが、あるのですね。
しかし貧しい沖縄の画家たちは、決して卑屈にならなかった。
そして彼らの類いまれなる才能をエドは素直に認め、彼らの絵を買い取り、
本国から絵の具などの材料を取り寄せては彼らに与えるのです。
そして同時に、彼らからは量り知れない芸術への情熱を受け取るのです。
画家の一人ヒガが米軍少佐から受けた残酷な仕打ちは、沖縄の悲劇を象徴しているのかも。
しかしそれを乗り越えようとする人々の力強さ、
芸術の力の重み、そして友情のあたたかさを、この本全編から感じ取りました。
そのこと自体に傷つけられたことは想像に難くない。
そしてそうしたことは、彼らの友情が続く中にも多々起きるのです。
悪気がなくてもどうしようもなく傷つけることが、あるのですね。
しかし貧しい沖縄の画家たちは、決して卑屈にならなかった。
そして彼らの類いまれなる才能をエドは素直に認め、彼らの絵を買い取り、
本国から絵の具などの材料を取り寄せては彼らに与えるのです。
そして同時に、彼らからは量り知れない芸術への情熱を受け取るのです。
画家の一人ヒガが米軍少佐から受けた残酷な仕打ちは、沖縄の悲劇を象徴しているのかも。
しかしそれを乗り越えようとする人々の力強さ、
芸術の力の重み、そして友情のあたたかさを、この本全編から感じ取りました。

読み終わった後に調べて分かったのですが
「ニシムイ・アートヴィレッジ」というのは戦後の沖縄に実存した芸術村で
この本の表紙の表も裏も、そこで描かれた実際の絵なのだそうです。
表紙は精神科医エドの顔。凛として意志の強そうな、しかし優し気な眼差し。
裏表紙はそれを描いた画家タイラの自画像。丸い眼鏡の奥の強い意志をたたえた眼。
エドが本国に持ち帰って大事に保管していた絵を借りて
こんな風に近年にも展覧会が行われたのだそうです。
「ニシムイ・アートヴィレッジ」というのは戦後の沖縄に実存した芸術村で
この本の表紙の表も裏も、そこで描かれた実際の絵なのだそうです。
表紙は精神科医エドの顔。凛として意志の強そうな、しかし優し気な眼差し。
裏表紙はそれを描いた画家タイラの自画像。丸い眼鏡の奥の強い意志をたたえた眼。
エドが本国に持ち帰って大事に保管していた絵を借りて
こんな風に近年にも展覧会が行われたのだそうです。

本書の序文。
”「私たちは、互いに、巡り合うとは夢にも思ってなかった」
None of us was preparedto meetースタンレー・スタインバーグ”
このスタンレー・スタインバーグ医師こそが、エド・ウィルソンその人だったのですね。
読み終わってすべてが腑に落ちました。
「太陽の棘」
”「私たちは、互いに、巡り合うとは夢にも思ってなかった」
None of us was preparedto meetースタンレー・スタインバーグ”
このスタンレー・スタインバーグ医師こそが、エド・ウィルソンその人だったのですね。
読み終わってすべてが腑に落ちました。
「太陽の棘」