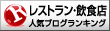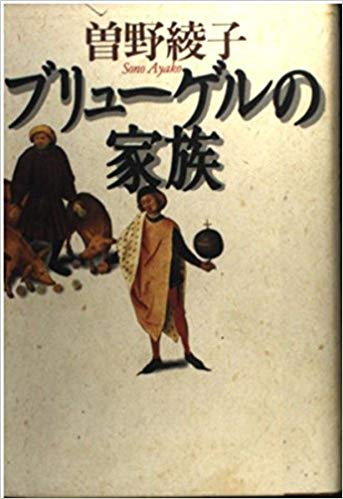先日観た映画「フォードvsフェラーリ」の原作本を読みました。
2011年の発刊、著者A.J.Beimeはプレイボーイ誌の編集者です。
映画がもっぱらフォード社側の目線から描かれていたのと違って、こちらはフォードとフェラーリ双方の立場から描かれています。
著者はアメリカ人なのですから、無論、フォード側に関する記述がずっと多いのですが。
イタリアの特権階級向けのスポーツカーを作るエンツォ・フェラーリが、小さな金属工場の息子として生まれ、小学校と職業訓練校にしか行っていないとは知りませんでした。
デトロイトの自動車王国の御曹司として生まれたヘンリー2世が、イェール大学でカンニングがばれ、卒業証書を貰えなかったことも知りませんでしたが。
その二人の闘いは、ル・マン24時間レースを舞台に、国同士の闘いにまで発展する。
ル・マンという、死と隣り合わせのあんな危ないレースに国をかけて血道を上げるというのが、女の私にはどうにも理解できないところなのですが
”1965年のアメリカは、スピード革命の真っ只中にあった。”
”スピードはセックスと同じだった。道に出たらアクセスを踏むのは当たり前。
危険を楽しむのは、自由になる手段だった。そんな彼らにとって、レーシング・ドライバーは自分の化身だった。男らしさと、はったりの究極。”
”初めて、レースがテレビで頻繁に放映されるようになった。度肝を抜くクラッシュやチェイスのスリルーカメラはスピードを全米のリビングルームに送り続けた。”
これらの文章を読んで、少しだけ納得した思いです。

(英語版)
映画ではあんなに悪役だったレオ・ビーブは、本書ではそんな風には書かれていない。
あの三台横並びのゴールについて、レオは確かに提案はしたようですが、シェルビーはその場ですぐに同意しているのです。
もっともそのことを、シェルビーは死ぬまで後悔していたようですが。
「ケンは一周半先を走っていたんだ。彼はレースに優勝する筈だった。
彼の心を傷つけてしまった。そして、そのまま彼は8月に亡くなってしまった」と。
自動車ビジネスの熾烈さ、自動車レースの過酷さ、そこに携わる人々の喜怒哀楽が、映画よりも詳細に読み取れます。
逆に言えば、映画はシェルビーとケン・マイルズの二人に焦点を当て、それ以外を斬り捨てた思い切りぶりが見事とも言えるのでしょうが。
原題の「Go like hell」は「 死ぬ気でぶっ飛ばせ!」といったような意味でしょうか。
「フォードvsフェラーリ伝説のルマン」