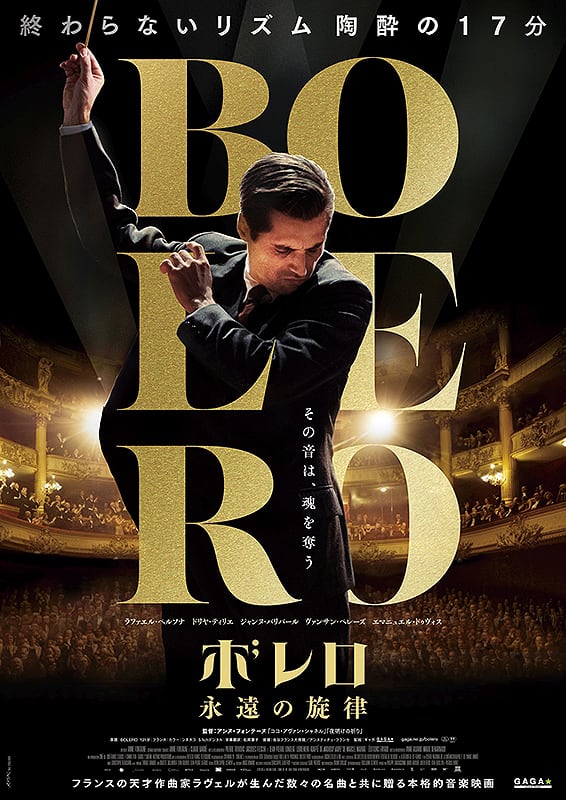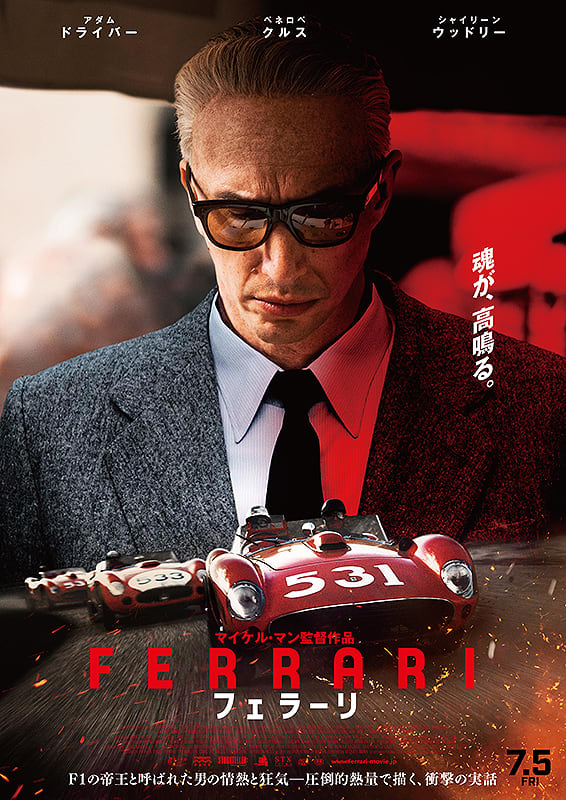恵比寿ガーデンプレイスはもう30周年を迎えたのですって。
こちらのガーデンシネマで映画を観て、ウエスティンホテルのラウンジでお茶を。
今年のウエスティンのクリスマスツリーは、白を基調とした、とってもシックな装い。

映画は1994年制作の「イル・ポスティーノ」。
実在したチリの詩人パブロ・ネルーダのイタリア亡命時代を元に描かれた、村の青年と詩人との友情がテーマのヒューマンドラマ。
製作30周年とパブロ・ネルーダ生誕120周年を記念して、4Kデジタルリマスター版でリバイバル公開したのだそうです。

内気で純朴な村の青年マリオは、世界的に有名な詩人パブロに郵便物を届けるという仕事を通して、詩人との友情を育んで行く。
パブロに教えて貰った詩のお陰で村一番の美人とも結婚するが、やがてパブロが帰国する日がやって来る。

それだけの話です。
思わぬ悲しい結末に驚きましたが、これは若い時に見たら物足りなく感じたかもしれない。
が、今となると、短い物語の裏のその時代の、チリやイタリアの政治的混乱が見えて来るし、帰国後軍部に殺されたというパブロへの鎮魂歌にも思えてくる。
そして、マリオ役のマッシモ・トロイージは心臓病を抱えながら撮影に参加し、撮影終了からわずか12時間後に41歳の若さで夭逝したという事実を知ると、それだけで胸がいっぱいになります。

お茶をしてホテルを出ると日はとっぷりと暮れ、バカラツリーが燦然と輝いていました。
「イル・ポスティーノ」公式HP
こちらのガーデンシネマで映画を観て、ウエスティンホテルのラウンジでお茶を。
今年のウエスティンのクリスマスツリーは、白を基調とした、とってもシックな装い。

映画は1994年制作の「イル・ポスティーノ」。
実在したチリの詩人パブロ・ネルーダのイタリア亡命時代を元に描かれた、村の青年と詩人との友情がテーマのヒューマンドラマ。
製作30周年とパブロ・ネルーダ生誕120周年を記念して、4Kデジタルリマスター版でリバイバル公開したのだそうです。

内気で純朴な村の青年マリオは、世界的に有名な詩人パブロに郵便物を届けるという仕事を通して、詩人との友情を育んで行く。
パブロに教えて貰った詩のお陰で村一番の美人とも結婚するが、やがてパブロが帰国する日がやって来る。

それだけの話です。
思わぬ悲しい結末に驚きましたが、これは若い時に見たら物足りなく感じたかもしれない。
が、今となると、短い物語の裏のその時代の、チリやイタリアの政治的混乱が見えて来るし、帰国後軍部に殺されたというパブロへの鎮魂歌にも思えてくる。
そして、マリオ役のマッシモ・トロイージは心臓病を抱えながら撮影に参加し、撮影終了からわずか12時間後に41歳の若さで夭逝したという事実を知ると、それだけで胸がいっぱいになります。

お茶をしてホテルを出ると日はとっぷりと暮れ、バカラツリーが燦然と輝いていました。
「イル・ポスティーノ」公式HP