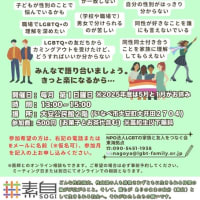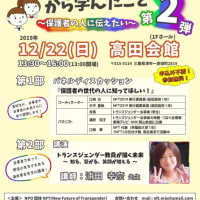平成28年3月19・20日、東京で第18回GID学会が開催されました。つなぐ会ではワークショップ「カミングアウトというバトン」を行いましたので報告します。
このワークショップではGIDの子どもを持つ母親、父親5人と親子一組(母親と当事者)の7人が発表者となりました。そこではカミングアウトをした時の子どもの心境やカミングアウトを受けた時の親の思い、感じたことなどが率直に話されました。たまたま全員FTMの子どもの親が集まりましたが、やはりカミングアウトを受けた時の親の対応は様々です。ただ、どの親も子どもが言っていることの意味がすぐに理解できたわけはなく、表面上は何とか平静さを装ってみたり、子どもが何か勘違いをしているのではないかと子どもの言うことを強く否定したりしています。
しかしその後子どもから渡されたGID関連の本を一生懸命に読んだり、とにかく子どもにいろんなことを問いかけてみたり、子どもの考え方を何度も確認をしてみたりと子どものことを何とか理解しようとする親の必死な行動が見られました。同時に子どもを守ろうとする親の本能的な行動なのか、専門医に受診させようとしたり、専門的な機関を探して相談しようとする前向きな行動も見られます。そして一度は子どものことを受け入れたと思ってみても、やはり何かのきっかけで気持ちがぐらついたり、思わず子どもに対して否定的な言動を取ってしまったりと子どもの状況を受けいれることはそう簡単ではないことがわかります。
子どもにしてもカミングアウトはしたものの、自分の状態が安定しているわけではないので悩みや葛藤は続いており、親にとりあえず宣言をして終わってしまいその後のコミュニケーションが途絶えていたりします。また中途半端なことを言って親を混乱させる場合もあるようです。
このように親子のコミュニケーションがうまくいかない時期もありますが、少しずつ親の気持ちが安定してきて考え方が変化してくると、今まで自分が知らなかった価値観に子どもが気付かせてくれたことに感謝する気持ちが生まれてきたりします。また子どもからも、最初は否定的であった親が今は自分を一番サポートしてくれる存在になってくれたことに感謝するようになります。
ワークショップの最後に、カミングアウトというバトンを受けとった親がこれから何をしていこうと思うか、親に課せられたミッションは何かとの問いかけがあり、それに対して多くの親が、自分と同じような親の相談相手になりたい、もっと一般的にGIDのことを知ってもらいたい、そのためには教育(学校)が大事である、とにかく親がやれることはやっていきたいと前向きに社会的な行動を起こそうとする気持ちを表していました。カミングアウトを受け入れる過程や時間の長さはいろいろですが、親が今そのような気持ちにであることを自分も同じ親として大変頼もしくまた印象深く感じました。
ヒロユキ