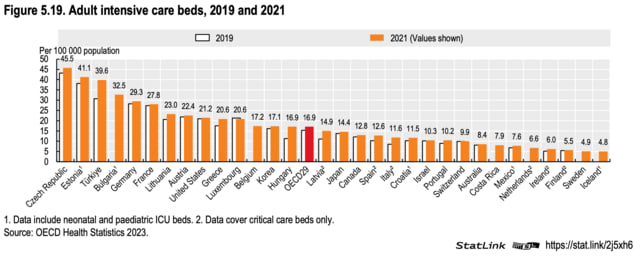昨日に続いて厚労省の統計ネタ。
こちらは今年の3月に発表されていたのを発見。
令和4(2022)年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況
令和4年と言えば、我々集中治療医にとって記念すべき年。
そう、「医師届出票の「従事する診療科名等」の欄に「集中治療科」がついに追加されました」の年です。
ついに、”自分が従事している診療科は集中治療です”と思っている人の数が分かった。
さて、何人でしょう?
ヒント:2024年4月1日現在で集中治療医学会認定専門医は2770名です。
正解は、、、
919名!医師の0.3%でした!
専門医を持っている人のうち約三割が”自分が従事している診療科は集中治療です”と思っているのか。想像よりちょっと多いかも。嬉しい限り。
ちなみに女性の割合は17.6%(病院に勤める医師の平均は24.5%)、平均年齢は42.8歳(同45.4歳)。
つまり若めの男性が多い。そんな感じ、するね。
こちらは今年の3月に発表されていたのを発見。
令和4(2022)年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況
令和4年と言えば、我々集中治療医にとって記念すべき年。
そう、「医師届出票の「従事する診療科名等」の欄に「集中治療科」がついに追加されました」の年です。
ついに、”自分が従事している診療科は集中治療です”と思っている人の数が分かった。
さて、何人でしょう?
ヒント:2024年4月1日現在で集中治療医学会認定専門医は2770名です。
正解は、、、
919名!医師の0.3%でした!
専門医を持っている人のうち約三割が”自分が従事している診療科は集中治療です”と思っているのか。想像よりちょっと多いかも。嬉しい限り。
ちなみに女性の割合は17.6%(病院に勤める医師の平均は24.5%)、平均年齢は42.8歳(同45.4歳)。
つまり若めの男性が多い。そんな感じ、するね。