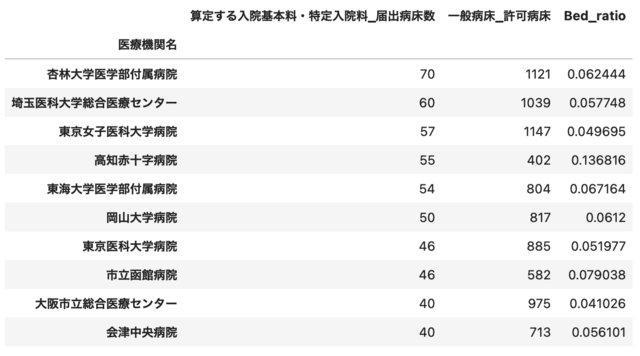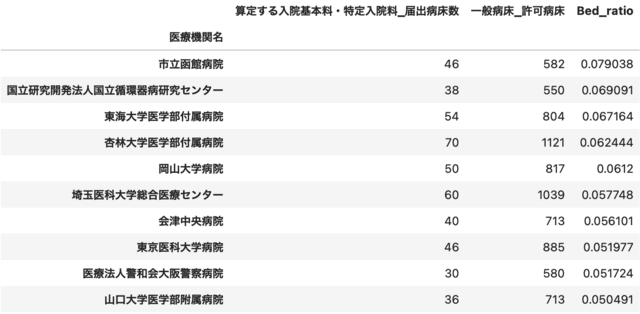Khan BA, Perkins AJ, Khan SH, et al.
Mobile Critical Care Recovery Program for Survivors of Acute Respiratory Failure: A Randomized Clinical Trial.
JAMA Netw Open. 2024 Jan 2;7(1):e2353158. PMID: 38289602.
呼吸不全でICUに入室し生存退院した患者さんを、最初の半年は2週に1回、その後は月に1回訪問して、身体的および精神的な評価と介入を行なった。その結果、QOLは改善せず、ER受診と入院の確率が増え、死亡率に有意差は認められなかった。
つまりはPICSに対する介入研究、と考えていいだろうか。
結論だけ見ると有効そうじゃないけど、死亡率は10.3% vs. 16.3%でp値は0.05。実際に計算してみるとChi squareで0.0562。確かに0.05を上回っているけど、定期的に訪問すると体調や病気に対する注意が払われて、「病院行った方がいいよ」とより頻回に言われ、もろもろの結果として死亡率が低下した、と考えるとスッと理解できるので、どちらかと言えば有効性を示した研究のように思える。
最近のAJRCCMにもこんな記事が載っていて、いわゆるICUサバイバーの長期管理の重要性について述べている。PICSの関心がいよいよ高まっている感じ。
ただ、PICSのフォローやケアはICUの仕事なのか、については疑問。
ICUに来なくても長期入院でADLが低下する人はたくさんいるし、AKI後のCKD管理の重要性なども言われているし、入院による状態悪化を長期フォローする仕組みが必要で、PICSはそこに含まれれば良いのではないか。
ICUリサーチの担当は、PICSという病態を世に知らしめて、より大きな仕組みの中に組み込んでもらうところまで、な気がするのだけど、
それってちょっと無責任か??
Mobile Critical Care Recovery Program for Survivors of Acute Respiratory Failure: A Randomized Clinical Trial.
JAMA Netw Open. 2024 Jan 2;7(1):e2353158. PMID: 38289602.
呼吸不全でICUに入室し生存退院した患者さんを、最初の半年は2週に1回、その後は月に1回訪問して、身体的および精神的な評価と介入を行なった。その結果、QOLは改善せず、ER受診と入院の確率が増え、死亡率に有意差は認められなかった。
つまりはPICSに対する介入研究、と考えていいだろうか。
結論だけ見ると有効そうじゃないけど、死亡率は10.3% vs. 16.3%でp値は0.05。実際に計算してみるとChi squareで0.0562。確かに0.05を上回っているけど、定期的に訪問すると体調や病気に対する注意が払われて、「病院行った方がいいよ」とより頻回に言われ、もろもろの結果として死亡率が低下した、と考えるとスッと理解できるので、どちらかと言えば有効性を示した研究のように思える。
最近のAJRCCMにもこんな記事が載っていて、いわゆるICUサバイバーの長期管理の重要性について述べている。PICSの関心がいよいよ高まっている感じ。
ただ、PICSのフォローやケアはICUの仕事なのか、については疑問。
ICUに来なくても長期入院でADLが低下する人はたくさんいるし、AKI後のCKD管理の重要性なども言われているし、入院による状態悪化を長期フォローする仕組みが必要で、PICSはそこに含まれれば良いのではないか。
ICUリサーチの担当は、PICSという病態を世に知らしめて、より大きな仕組みの中に組み込んでもらうところまで、な気がするのだけど、
それってちょっと無責任か??