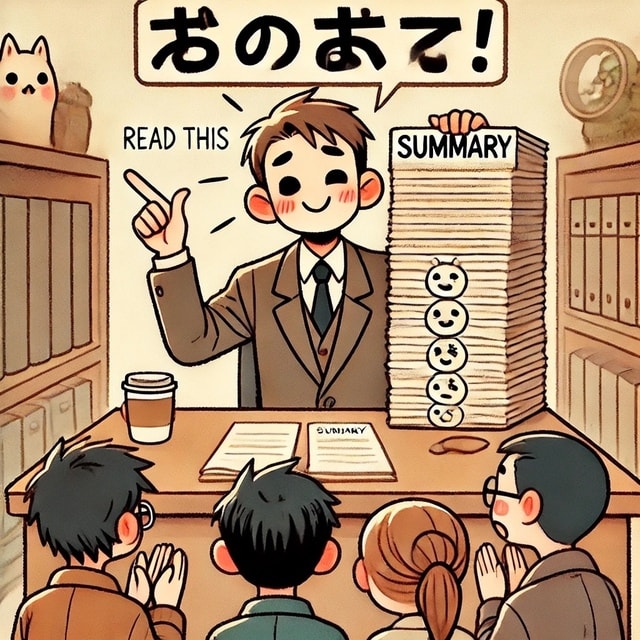初めてJIPADデータを使って研究する人に、毎回必ず言うことがある。
まとめて書いておけば、次からは「これを読め」と言えば済むので、ここにまとめておく。
・ICUでの手技を除外
入室形式が"ICUの手技"の症例はICU患者としての研究対象には含まない方がいいので、最初に除外する。
・Type of admissionの作り方
JIPADには、入室形式、入室経路、入室区分という、ちょっと似た感じの分類が3つある。このまま研究に使用すると、Table 1もそれを使った多変量解析も変な感じになってしまう。JIPADの収集項目は基本的に僕が決めたのだけど、これは手本となった ANZICS-APDが収集していた項目だからであって、僕のせいじゃない。で、研究するときはどうすれはいいかというと、主に入室経路を用いて分類し、手術室だけは入室区分を使って予定手術と緊急手術に分ける。最終形は、
予定手術、緊急手術、病棟、救急外来、転院直入、その他
になり、いい感じ。
・敗血症は使わない、infectionを使う
主病名コードにある敗血症は他のコードに分類できない感染症が対象となる(カテ感染とかフォーカス不明とか)。なのでそのまま利用してしまうと敗血症が数%しかいなくなり、Table 1が変な感じになる。なので、敗血症は”その他”に分類し、辞書の182ページにある感染症コード表を用いて"Infection"という項目を主病名コードとは別に作成する。
・副病名コードは使用しない
話が長くなるので理由は割愛するが、副病名コードはJIPADでは使用していない。具体的には年次レポートには含まれていないし、入力チェックのためのクエリ制度や不定期チェックでも対象になってない。じゃあ何のためにあるかというと、各施設で統計情報として好きに利用してもらうため。なので研究には使用しない。
・慢性疾患の分類方法
JIPADの慢性疾患は全部で10種類あるのだが、これはAPACHE IIとIIIとSAPS IIを全て算出可能にするため。なので研究で使用するときは少し工夫が必要。
1:白血病/多発性骨髄腫とリンパ腫が分かれているので、これを"hematological malignancy"として一つにまとめる。
2:肝不全は肝硬変がYesであることが前提なので、使用しない。
3:AIDSは症例数が極端に少ないので免疫抑制にまとめる。
最終的に、心不全、呼吸不全、肝硬変、血液悪性腫瘍、癌転移、免疫抑制、維持透析、の7種類にする。
・3.0に気を付ける
JIPADでは2018年度から収集項目が増えた(JIPAD 3.0)。ただしそれらが収集されていないデータを受け付けないようにしたのは2020年度から。なので施設によって時期が異なるが、カテコラミン、HFNC、Plt、Lacは欠損したデータが一定数存在する。対応方法は、これらが重要でない場合は2015年度からの全データを用い、これらが研究のメインになる場合は欠損データを全て削除、ちょっと重要な場合はどちらかを感度分析にする。ただ、症例数が年々増加しているので、数年後には必ず除外するようにしても困らなくなるけど。
・入室時気管切開は再挿管を検討するときに利用
JIPADでは人工呼吸の開始終了日時を入力する。なので終了日時と次の開始日時を比較すれば再挿管が行われたかどうかが分かりそうだけど、気管切開されていれば再挿管にはならない。気管切開施行日があるので、これを利用すればいいのだけど、入室時から気管切開があると再挿管を判断できない。そのため、3.0から入室時気管切開Yes/Noという項目を追加した。なので3.0から再挿管について検討することが可能になっている。
・入院ー入室を使うとモデル精度が向上
これはJIPADデータに限らないが、入院してから入室するまでの日数は予後と強い関連がある。何故なら、救急外来経由の患者よりも病棟に数日入院してからICUに来る症例の方が予後が悪いし、同じ入院患者でも病棟に長期入院してからICUに来る症例は予後が悪いから。
2020年2月からJIPADの研究利用が開始された。2024年11月の段階で73の申請があり、文献化されたものは
こんなにある。今後はデータが年に数十万例ずつ増えていって、どこかのタイミングでANZICSを抜くだろうから、研究価値は高まるばかり。
データは利用してなんぼだから、どんどん使ってあげてください。
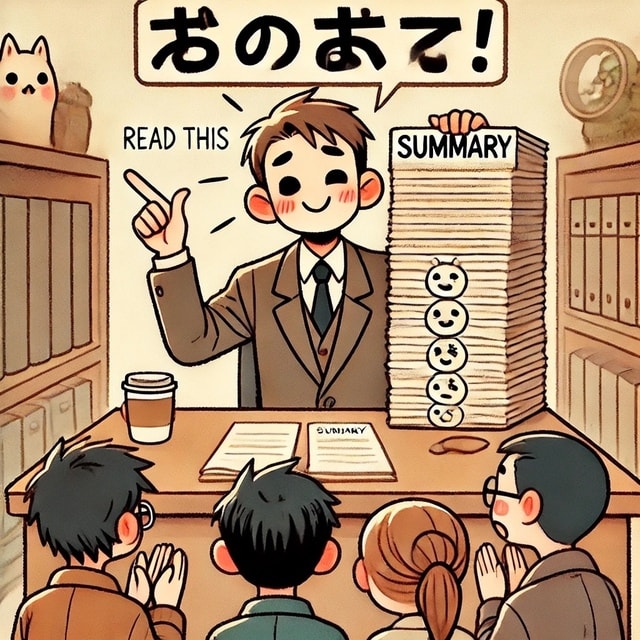
タイトル:「まとめて書いておけば、次からは"これを読め"と言えば済む」 by Chat-GPT 4o
相変わらず言葉がちゃんと書けないChat先生。英語が正しく書けているところは進歩かも。
あ、それ以前にタイトルと絵が一致していない気もするな。