7月11日上州武尊山に登ります。
今日の行程は、(標高差776m、13.4km、約6.5時間)
花咲温泉 =御沢登山口 ⇒前武尊 ⇒剣ヶ峰(巻道) ⇒中ノ岳分岐 ⇒武尊山
⇒中ノ岳分岐 ⇒セビオス岳 ⇒武尊牧場 ⇒スキー場下 =花咲の湯 =新宿へ
武尊をホタカと読める人は、山好き以外にはあまりいないだろう。
山名は 日本武尊(ヤマトタケルノミコト)からきたといわれている。
日本武尊(ヤマトタケルノミコト)からきたといわれている。
前武尊の頂上には高さ四尺くらいの 銅像が立っているが、それは日本武尊を現している。
銅像が立っているが、それは日本武尊を現している。
(中略)武尊山が昔から宗教の山であったことは、沖武尊の頂に御嶽山大神と刻んだ石が
立っていたり、剣が峰の頂に普賢菩薩が祀ってあるので察することができる。
(日本百名山:上州武尊山より)
天気予報は午前中 、午後から
、午後から 。
。
5:50 マイクロバスはスキー場の荒れた斜面を 喘ぐように登り、登山口に。
喘ぐように登り、登山口に。
バスを降りて歓迎してくれたのは、待ち受けていた 虫の大群だった。
虫の大群だった。
虫よけ スプレーをかけても、あらたな虫がまとわりついてくる。
スプレーをかけても、あらたな虫がまとわりついてくる。
彼らとはしばらく 付き合うことになる。
付き合うことになる。
急登、滑る道、最悪の登山と思いきや、シャクナゲをはじめとする花たちが 救ってくれた。
救ってくれた。
 :シャクナゲ
:シャクナゲ
 :燧ケ岳
:燧ケ岳
振り返ると遠く 燧ケ岳が見えた。
燧ケ岳が見えた。
 :ネットより
:ネットより
6:55 約1時間かけて前武尊山(2040m)へ
武尊山には4つの大きなピークがある、そのピークを 縦走していく。
縦走していく。
登るのは前武尊と(沖)武尊山の二つ、残りの二つは 巻いて行く。
巻いて行く。
 :(川場)剣ヶ峰
:(川場)剣ヶ峰
剣ヶ峰(2020m)、巻き道を行く。
かなりの悪路、ネマガリダケで 滑るし、灌木が前を
滑るし、灌木が前を 塞ぐ、キレットもあり
塞ぐ、キレットもあり スリリングな道だ。
スリリングな道だ。

これだけシャクナゲが多い山とは、うれしい 誤算だ。
誤算だ。
 :家の串
:家の串
8:00 家の串(2103m)通過、ガスも出てきたし、 湿った風も吹いてきた・・・・。
湿った風も吹いてきた・・・・。
 :中ノ岳分岐
:中ノ岳分岐

中ノ岳分岐から(沖)武尊山への途中に「三つ池」と呼ばれる湿地帯?がある。
水際にキヌガサソウとサンカヨウが咲いていた。
:キヌガサソウ(小振りだが) :サンカヨウ

右から前武尊、中央 (川場)剣ガ峰、左 中ノ岳(2144m)
 :(沖)武尊山頂
:(沖)武尊山頂
石がゴロゴロした登山道を登り、稜線に出ると 9:10 山頂へ。
360°の眺望だが雲に隠れて望めない・・・・。
「 下山します」の声を聞く頃には、
下山します」の声を聞く頃には、 雨がポツポツ落ちてきた。
雨がポツポツ落ちてきた。
 :ネットより
:ネットより
 :中ノ岳
:中ノ岳
中ノ岳分岐で、雨も本格的に落ちてきた、上衣のみ 合羽着用。
合羽着用。
中ノ岳分岐から 武尊牧場へ向かう。
武尊牧場へ向かう。
:ナナカマドの花 :イワカガミ
 :岩場(ネットより)
:岩場(ネットより)
下山路も悪路の連続、鎖場も2ケ所あった。
10:50 セビオス岳(岩峰)を臨む登山道で昼食、虫と雨にうたれて最悪の ランチだった。
ランチだった。
ここから武尊登山小屋までの道が、 ヌカルミの悪路、水溜りを通過するのに
ヌカルミの悪路、水溜りを通過するのに 気を使う。
気を使う。
:ギンリョウソウ(群生も) :マイズルソウ :エンレイソウ
 :ネットより
:ネットより
武尊避難 から武尊牧場への道も花が多かった。
から武尊牧場への道も花が多かった。
挙げれば、マイズルソウ、エンレイソウ、ツマトリソウ、ギンリョウソウ(群生)
 :ベニバナイチヤクソウ
:ベニバナイチヤクソウ
 :ヤマオダマキ
:ヤマオダマキ
13:00 武尊牧場へ、リフト乗り場への「散策路」にはベニバナイチヤクソウやヤマオダマキ等が。
13:40 武尊牧場スキー場で待つバスに乗り、花咲の 湯で体を癒し、帰途に着いた。
湯で体を癒し、帰途に着いた。
「虫・悪路・豊富な花たち」上州武尊山の印象である。
日本百名山 52 上州武尊山完登
**

 冬を越す”
冬を越す” の場合”
の場合” 

 :西洋タンポポ
:西洋タンポポ
葉を地面に放射状に広げた形を バラの花に見立てて*ロゼットと呼びます。
バラの花に見立てて*ロゼットと呼びます。
冬のロゼット植物は葉を地表にペッタリ広げて 凍える風を避け、
凍える風を避け、 日だまりの
日だまりの
暖かさを利用して*光合成を行います。うっかり伸びようものなら茎はたちまち
凍りつき、全体が破滅に向かいます。ロゼット植物が冬を越す” 知恵”です。
知恵”です。
春になり寒さが去ると、茎を伸ばし、葉を立体的に配置して成長を始めます。
やがて花を咲かせ、たくさんの種という成果を生み出し、種の保存をします
植物の「冬を生き残るための努力」 興味を呼びますね・・・。
興味を呼びますね・・・。
【ロゼット:rosette】 根生葉
根生葉
【光合成】生物、主に葉緑素を持つ植物が、 光エネルギーを用いて、吸収した
光エネルギーを用いて、吸収した
二酸化炭素(CO2)と 水分から有機化合物(
水分から有機化合物( でんぷん)を合成すること。
でんぷん)を合成すること。
( 広辞苑より)
広辞苑より)




















 理由あって、登山は休み、過去の記録から皇海山と上州武尊山を紹介します。
理由あって、登山は休み、過去の記録から皇海山と上州武尊山を紹介します。
 揺れる、適度な揺れが、
揺れる、適度な揺れが、 居眠りをさそう。
居眠りをさそう。 :
: 不動沢登山口」に着いた、不動沢沿いの道を歩く。
不動沢登山口」に着いた、不動沢沿いの道を歩く。 :不動沢
:不動沢 に
に 左に渡りながら登って行く。
左に渡りながら登って行く。



 烏帽子をかぶった
烏帽子をかぶった :沢
:沢 急登、雨でもふれば
急登、雨でもふれば :滑る急登
:滑る急登 一安心と思いきや、足元が緩い
一安心と思いきや、足元が緩い
 急登が待っていた。
急登が待っていた。 :鋸山
:鋸山 :
: 樹林帯を木の根に注意しながら登る。
樹林帯を木の根に注意しながら登る。 :青銅の剣(ネットより)
:青銅の剣(ネットより) 青銅の剣」が立っている。
青銅の剣」が立っている。 木村惟一」とある。
木村惟一」とある。 先達で、庚申山から
先達で、庚申山から :
: ブルー皇海」だった。
ブルー皇海」だった。 :カラマツ林
:カラマツ林 大騒ぎだった。
大騒ぎだった。 危険なタイミングはあった。
危険なタイミングはあった。 登りは先頭を行き、下りは
登りは先頭を行き、下りは 最後尾」そんな話をしながら歩いた。
最後尾」そんな話をしながら歩いた。 :
:


 という結果でこれといった決めてはなかった。
という結果でこれといった決めてはなかった。 納得いく理由はない”というのが結論だと思っている。
納得いく理由はない”というのが結論だと思っている。 富士山を背に従えた、「
富士山を背に従えた、「
 :
: :稜線
:稜線 :
: :紅葉
:紅葉 楓や紅葉は少ない、林床はスズタケ?
楓や紅葉は少ない、林床はスズタケ? クマザサ?
クマザサ? :今倉山
:今倉山 :菰釣山
:菰釣山
 顔を出していた。
顔を出していた。


 :尾根道
:尾根道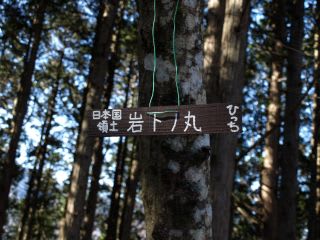 :岩下ノ丸
:岩下ノ丸 :
: りました。
りました。 :
: 倒れていた。
倒れていた。 :
: :ブナ林
:ブナ林 :
: :山頂
:山頂
 昼食。
昼食。 :
:

 今後の対応”を、このまま降りてバスに乗らずに駅まで歩く事に。
今後の対応”を、このまま降りてバスに乗らずに駅まで歩く事に。


 :
: 痕跡だ。
痕跡だ。 :
:


 :
: :下山道
:下山道 三輪神社へ降りる、単調な
三輪神社へ降りる、単調な 下りが続いた。
下りが続いた。 :上り登山道
:上り登山道 上り登山道、白井平分岐からの登りだろうか?
上り登山道、白井平分岐からの登りだろうか?
 :今倉山
:今倉山 :鞍部が分岐
:鞍部が分岐 :林道へ
:林道へ :ススキが
:ススキが :
: :アカマツ
:アカマツ :
: :
: 三輪神社に着いた、都留市駅へのバスは15:22発、
三輪神社に着いた、都留市駅へのバスは15:22発、 :
: :
: 時刻表を確認しながら歩いた、
時刻表を確認しながら歩いた、 熊井戸」バス停で
熊井戸」バス停で バスに乗ることにした。(バス
バスに乗ることにした。(バス ホリデー快速富士山2号は16:34発
ホリデー快速富士山2号は16:34発
 時間をつぶし、帰途に着いた。電車は
時間をつぶし、帰途に着いた。電車は


 混んでいた。
混んでいた。

 :
: 葉で、冬も葉を落とさず、
葉で、冬も葉を落とさず、 成長は、あまり速く
成長は、あまり速く 長く
長く 堅実に、それが常緑樹の生き方です。
堅実に、それが常緑樹の生き方です。
 Tさんです。
Tさんです。 :
: 人」が竿を垂れていた。
人」が竿を垂れていた。 :御前山
:御前山 :石尾根方面
:石尾根方面 :登山口
:登山口 :奥多摩湖
:奥多摩湖 :紅葉
:紅葉


 忙しい。
忙しい。 :深山橋
:深山橋 丹波山方面 ←渡れば
丹波山方面 ←渡れば :急登
:急登 :イヨ山
:イヨ山 :大菩薩方面
:大菩薩方面 :カラマツ
:カラマツ
 :糠指山
:糠指山
 :ブナ
:ブナ
 :鶴峠分岐
:鶴峠分岐 :西峰山頂
:西峰山頂



 :こんな
:こんな :不親切な看板
:不親切な看板 :ブナの路
:ブナの路 族
族 :ムシカリ峠
:ムシカリ峠



 スケッチです
スケッチです :三頭大滝
:三頭大滝 :滝上部
:滝上部 :中部
:中部 収めることはできません。
収めることはできません。 :チップの道
:チップの道 チップは必要ありません)
チップは必要ありません)

 :浅間尾根
:浅間尾根 :都民の森駐車場
:都民の森駐車場

 落葉樹の冬を越す選択
落葉樹の冬を越す選択 
 冬を迎え、それぞれ越冬の手段を
冬を迎え、それぞれ越冬の手段を 考えています。
考えています。 水が際限なく失われ、植物全体が干上がって、ついには
水が際限なく失われ、植物全体が干上がって、ついには 凍結防止策を講じますが
凍結防止策を講じますが エネルギーを
エネルギーを 必要とします。
必要とします。 決断をしています。
決断をしています。 春は巡ってきます。
春は巡ってきます。 礫岩
礫岩
 誤算だ。
誤算だ。 :map
:map :
: :
: :シンプルな表示
:シンプルな表示 巨
巨 岩が次々と現れる。
岩が次々と現れる。
 :鞍部
:鞍部 :登山道
:登山道 :
: :
: :
: 天狗の架け橋」に、小さいブリッジ状の岩で長さ3m、幅は60cm程度
天狗の架け橋」に、小さいブリッジ状の岩で長さ3m、幅は60cm程度 跳ぶと思うのだが)
跳ぶと思うのだが) :
: 危険だった。
危険だった。 :
: :
: :洞窟
:洞窟 :岩稜
:岩稜
 ジオラマのように展開し、”赤岩通り”の赤岩が上から見てとれる。
ジオラマのように展開し、”赤岩通り”の赤岩が上から見てとれる。 :山頂直下
:山頂直下 鞍部に。
鞍部に。 待って、ザックをデポし山頂への岩稜を、登る。
待って、ザックをデポし山頂への岩稜を、登る。
 :北峰(仮称)
:北峰(仮称) 一望できる。
一望できる。


 浅間山
浅間山 :グミを食べる
:グミを食べる :
: :北峰
:北峰 :天狗の手?
:天狗の手?
 :分岐
:分岐
 :一本松登山口
:一本松登山口



 数好くない花たちです。
数好くない花たちです。 バイパスする。
バイパスする。 :岩櫃山入口
:岩櫃山入口
 あきらめた。
あきらめた。
 つ
つ ぶし、14:42発の電車で帰途に着いた。
ぶし、14:42発の電車で帰途に着いた。 :黒谷金戒光明寺
:黒谷金戒光明寺 早いですけど)
早いですけど)