11月25日(日) 愛宕山(京都:三百名山)に登ってきました。
愛宕山(京都:三百名山)に登ってきました。
6:11新横浜 =( のぞみ)8:15京都 =8:23京都駅 (
のぞみ)8:15京都 =8:23京都駅 ( 京都バス)10:23清滝バス停着
京都バス)10:23清滝バス停着
3連休の最終日、紅葉時期、京都嵐山、 道路は大渋滞、時間は2倍かかった。
道路は大渋滞、時間は2倍かかった。

 紅葉も最盛期?
紅葉も最盛期?
 :愛宕山(神社)参道
:愛宕山(神社)参道
10:35 清滝橋を 渡って登山口へ
渡って登山口へ
 :東海自然歩道
:東海自然歩道
「東海自然歩道」も http://www.tokai-walk.jp/
”京都 一周トレイル”も通じている。
一周トレイル”も通じている。
http://kaiwai.city.kyoto.jp/raku/kanko_top/kyoto_trail.html
 :愛宕神社鳥居
:愛宕神社鳥居



: 表示板(1/40) :オフィシャル
表示板(1/40) :オフィシャル 表示柱(1/50)
表示柱(1/50)
 :標高はほぼ平地
:標高はほぼ平地
 :杉林
:杉林
まずは杉林を登って行く、ほぼ登り、階段が作られている。
 :火燧権現跡
:火燧権現跡
 愛宕山(924m)愛宕神社
愛宕山(924m)愛宕神社
山城国(京都南部)と丹波国(京都及び兵庫県)国境の愛宕山山頂に鎮座する。
古くより比叡山と共に信仰を集め、神仏習合時代は愛宕権現を祀る”白 雲寺”として知られた。
雲寺”として知られた。
火伏せ・防火に霊験のある 神社として知られ、「火迺要慎(ひのようじん)」と書かれた
神社として知られ、「火迺要慎(ひのようじん)」と書かれた
愛宕神社の火伏札は京都の多くの家庭の 台所や、飲食店の厨房などに貼られている。
台所や、飲食店の厨房などに貼られている。
また、「愛宕の三つ参り」として、3歳までに参拝すると一生火事に遭わないといわれる?
 :3世代登山
:3世代登山
登山者は多い、とくに家族連れ、

 3世代登山者結構いた。
3世代登山者結構いた。
 :休憩所(東屋)
:休憩所(東屋)
11:00 三合目付近の紅葉
11:30 大杉社へ、西側の眺望が開ける、道も平坦に。
 :嵐山
:嵐山
正面の桂川が流れ、右の起伏は 嵐山だろう。
嵐山だろう。
 :水尾別れ
:水尾別れ
11:50 水尾別れに、帰りはここから水尾の里へ下り、 JRで京都駅へ戻る予定だ。
JRで京都駅へ戻る予定だ。
 :山ガールも
:山ガールも
数は少ないが”山 ガール”も、袋にはドングリが入っていた。
ガール”も、袋にはドングリが入っていた。
 :ガンバリ坂
:ガンバリ坂
「四十四丁目ガンバリ坂」若千 急かな?という感じだった。
急かな?という感じだった。
 :黒門
:黒門
12:10 「黒門」

 :愛宕神社境内入口
:愛宕神社境内入口

 :ラスマエの階段
:ラスマエの階段
 :最後の鳥居
:最後の鳥居
 :最後の階段
:最後の階段
 :
: ゴール!!!
ゴール!!!
12:20 本殿へ、
:五千回登頂者 :二千五百回・・・ :千回・・・
愛宕神社に登り続けた人たちの「証」、 個人的にその意味は理解できないが。
個人的にその意味は理解できないが。
石碑も 自費で建立したのか?
自費で建立したのか?

境内へ戻って

 昼食、
昼食、 陽は差しているけど”
陽は差しているけど” 寒かった”
寒かった”
登山口に山頂との温度差は10℃あると書かれていたが、その 通りだった。
通りだった。
 :高雄分岐
:高雄分岐
昼食後、愛宕山三角点に 足を延ばす。
足を延ばす。
 :鉄塔の下が
:鉄塔の下が 三角点
三角点
 :三角点
:三角点
12:55 愛宕山三角点へ、南東側が開け、京都市内の眺望が見えた。
 :京都市内
:京都市内
肉眼では、京都タワー、西本願寺程度は判別できたが・・・?。
 :月輪寺方面分岐
:月輪寺方面分岐
各登山口への 所要時間が記されている、保津峡駅までは2時間の行程とある。
所要時間が記されている、保津峡駅までは2時間の行程とある。


 :水尾別れ
:水尾別れ
13:30 水尾別れへ、ここからは一気に

 下る。(本当に一気だった)
下る。(本当に一気だった)
 :杉林
:杉林
 :100m毎に表示が。
:100m毎に表示が。

愛宕神社と愛宕山について書かれている。
 四季実(しきみ)の話が面白いので紹介しよう。
四季実(しきみ)の話が面白いので紹介しよう。
古代は枝葉が繁茂する常緑木をすべて「栄え木」さかきいっていたが、その中でも
「しきみ」は芳香があって、四季に芽を出すので、「四季芽」→芽出度い木とされていた。
愛宕神社は昔も今も、しきみの 枝を神花とし、参拝者に授与されている。
枝を神花とし、参拝者に授与されている。
 しきみ【広辞苑では】
しきみ【広辞苑では】
シキミ科の常緑小高木。山地に自生し、墓地などに植える。
葉は平滑。春、葉の付け根に黄白色の花を開く。花弁は細く多数。
全体に香気があり、仏前に供え、また葉と樹皮を乾かした粉末で抹香や線香を作り
材は器具用に。果実は猛毒で、「悪しき実」が名の由来という。

「水尾の里」の紹介です。
14:00 「水尾の里」まで降りてきました。
 :
: 歴史の臭いが
歴史の臭いが プンプンしました。
プンプンしました。
 :柚子湯
:柚子湯 風呂
風呂

 :融
:融 雪剤置場
雪剤置場
水尾の里の冬は 厳しいようです。
厳しいようです。

 :保津峡橋
:保津峡橋
 :保津峡駅
:保津峡駅
保津峡駅は鉄橋の上にありました。
 :保津川
:保津川
トロッコ列車が見えました。 ( 明日乗車予定ですが)
明日乗車予定ですが)
 :保津峡駅
:保津峡駅
14:55 「保津峡駅」に着きました、15:02京都行きに乗って京都駅へ戻る。
今日の宿舎は大阪駅、 夕食は『
夕食は『 串揚げヨネヤ』で食べました。
串揚げヨネヤ』で食べました。
・・・・・・・・例の「二度漬け 禁止」
禁止」
*******
 行程:標高差840m、約12km、4時間30分
行程:標高差840m、約12km、4時間30分 

10:25 清滝バス停 ⇒10:35 登山口 ⇒11:00 二十丁目
⇒11:30 大杉社 ⇒11:50 水尾別れ ⇒12:20~12:40 愛宕神社(昼食)
⇒12:55 愛宕山 ⇒13:30 水尾別れ ⇒14:00 水尾の里 ⇒14:55 保津峡駅
**********
















 :大杉社
:大杉社 




 墓
墓






 日向山(ひなたやま)に登ってきました。
日向山(ひなたやま)に登ってきました。 バスは中央道を走り登山口へ向かいます。
バスは中央道を走り登山口へ向かいます。 雪をまとった南アルプスの山々が
雪をまとった南アルプスの山々が 迎えてくれます。
迎えてくれます。 荒川三山と
荒川三山と 夏登った山が勢ぞろいです。
夏登った山が勢ぞろいです。 急げ・・・・・。
急げ・・・・・。 竹宇駒ヶ岳神社駐車場へ向かいます。
竹宇駒ヶ岳神社駐車場へ向かいます。
 :
: 黒戸尾根登山口にもなります。
黒戸尾根登山口にもなります。

 :整列して進みます。
:整列して進みます。 :林道に出る
:林道に出る :再度登山道へ
:再度登山道へ

 家形のことで、三角形の石につけられることが多い。
家形のことで、三角形の石につけられることが多い。 戦いをするとき、この石を楯に
戦いをするとき、この石を楯に 弓をひいて戦った」という伝説。
弓をひいて戦った」という伝説。 :炭焼き釜跡
:炭焼き釜跡 影響か?
影響か?

 :八ヶ岳
:八ヶ岳 視界の先には「八ヶ岳」が姿を見せる。
視界の先には「八ヶ岳」が姿を見せる。 :富士山も
:富士山も :看板
:看板 :一旦鞍部に下る
:一旦鞍部に下る :三角点
:三角点 ない。
ない。


 風化した花崗岩の姿を見てください。
風化した花崗岩の姿を見てください。



 サルオガセに代表される「地衣類」いい機会なので
サルオガセに代表される「地衣類」いい機会なので 紹介します。
紹介します。





 水分を与えるかわりに、
水分を与えるかわりに、

 セピア色に変わっていた。(これもまたいい)
セピア色に変わっていた。(これもまたいい)
 告げて往路を下山する。
告げて往路を下山する。 :唯一みた
:唯一みた 地蔵さん
地蔵さん


 :皇太子登頂記念碑
:皇太子登頂記念碑 ラッセル」を楽しみながら無事下山。
ラッセル」を楽しみながら無事下山。 :
: 日帰り温泉に向かった。
日帰り温泉に向かった。 山が姿を見せた。
山が姿を見せた。 記憶に撮って」
記憶に撮って」 帰途に着いた。
帰途に着いた。 いい登山だった。
いい登山だった。 歩いてきました。
歩いてきました。 曇り後
曇り後 晴れ”朝は雲が多かったが、歩き始める頃には陽もさしてきました。
晴れ”朝は雲が多かったが、歩き始める頃には陽もさしてきました。 田崎さん同行です)
田崎さん同行です) :奥多摩駅
:奥多摩駅 事故防止のチラシ”を配っていた。
事故防止のチラシ”を配っていた。 :多摩川
:多摩川 


 180段ありました。
180段ありました。  アップにはちょうどよかった?
アップにはちょうどよかった? 都合のいい、人間の拡大解釈ですね)
都合のいい、人間の拡大解釈ですね) 神社に参る覚悟のない者、来るべからず」
神社に参る覚悟のない者、来るべからず」 者のみ来るべし」 といっているようです。
者のみ来るべし」 といっているようです。

 :登計峠
:登計峠 鋸尾根ここから始まる。
鋸尾根ここから始まる。 :杉の植林帯
:杉の植林帯 :726m峰
:726m峰 :北側の山並み
:北側の山並み
 紅葉がはじまっていた。(
紅葉がはじまっていた。( ~
~ 分ぐらいか?)
分ぐらいか?)



 :鎖場のトラバース
:鎖場のトラバース :1047m三角点
:1047m三角点 :北側の展望
:北側の展望 鷹巣山あたりか?
鷹巣山あたりか? 山・
山・ 山・
山・ 山ばかりだ。
山ばかりだ。 :天地山分岐(イワウチワの群落がある)
:天地山分岐(イワウチワの群落がある)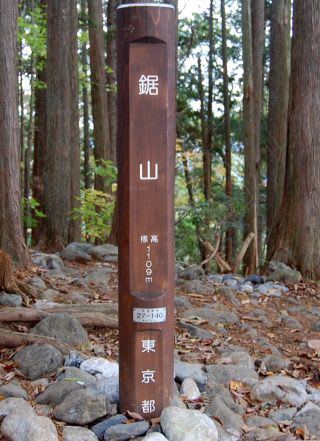 :鋸山頂
:鋸山頂 




 :右へ行くと”大ダワ”を経て御前山
:右へ行くと”大ダワ”を経て御前山 :馬頭刈尾根分岐
:馬頭刈尾根分岐 昼食、鋸山へ向かう登山者が圧倒的に多い。
昼食、鋸山へ向かう登山者が圧倒的に多い。 :大きな岩
:大きな岩 緊張感をもって歩く。
緊張感をもって歩く。
 撮っても人が入ってしまう。
撮っても人が入ってしまう。 休日・
休日・





 :
: 鳥(コガラ)への注意喚起!
鳥(コガラ)への注意喚起! :急登の岩場
:急登の岩場 :大岳神社
:大岳神社 荒れている)
荒れている) :芥陽峠
:芥陽峠 分岐、ロックガーデンへ寄る。
分岐、ロックガーデンへ寄る。 :ロックガーデン看板
:ロックガーデン看板 :綾広ノ滝
:綾広ノ滝 落差10mあり、「武蔵御嶽神社」の
落差10mあり、「武蔵御嶽神社」の

 小説「大菩薩峠」に出てくる。
小説「大菩薩峠」に出てくる。 :山ガール
:山ガール 観光客が
観光客が ケーブルカーに乗り、ここまで歩いてくる。
ケーブルカーに乗り、ここまで歩いてくる。 :天狗岩
:天狗岩 人・
人・ 人・・・・人が多いでしょう。
人・・・・人が多いでしょう。 :七代の滝
:七代の滝 時間がかかった。
時間がかかった。 :渋滞する階段
:渋滞する階段 :奥ノ院からの合流点
:奥ノ院からの合流点
 :武蔵御嶽神社
:武蔵御嶽神社 宝物館」の前(西側)、有料
宝物館」の前(西側)、有料 双眼鏡が設置されているあたりだそうです。
双眼鏡が設置されているあたりだそうです。
 :「願」
:「願」 。
。 :日の出山
:日の出山



 :
:



 チョコレート? :
チョコレート? : 棒アイス
棒アイス

 :登山道入口鳥居
:登山道入口鳥居 :
: 夕暮れ迫る
夕暮れ迫る 多摩川
多摩川