「メジャーリーグ」 1989年 アメリカ
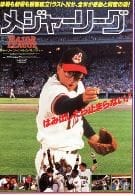
監督 デイヴィッド・S・ウォード
出演 トム・ベレンジャー
チャーリー・シーン
コービン・バーンセン
マーガレット・ウィットン
ジェームズ・ギャモン
レネ・ルッソ
ストーリー
アメリカンリーグ、東地区クリーブランド・インディアンズは伝統こそあるが、ここ34年間優勝から遠ざかり、Aクラスすら叶わない有様である。
急死した夫の跡を継いで新オーナーとなったダンサー上がりのレイチェル・フェルプスは、本拠地をマイアミに移すため、市の条約に従い、1年間の観客動員数80万人を下回らせようと企んでいた。
彼女はマネージャーのチャーリー・ドノヴァンに新チームのリストを渡し、監督のルー・ブラウンを始めとする一癖も二癖もある連中を集めさせた。
メキシカンリーグのキャッチャー、ジェイク・テーラーや刑務所から仮出所してきたピッチャーのリッキー・ボーンたちは、憧れのメジャーリーグ入りに張り切るが、もとより実力のない彼らの戦いぶりは惨めで、連戦連敗を繰り返していた。
ある日ジェイクは、町で別れた妻リンと出会った。
彼女には新しい婚約者がいたが、彼は想いが断ち切れないためにプレーにより熱がこもっていった。
そしてノーコンに悩むリッキーがメガネをかけて登板するや、見違えるようなピッチングを披露し、チームに勝利をもたらした。
チャーリーたちは事の真相を知り、以後チームの結束は一段と強まり、士気はますます高まった。
一転してチームは連戦連勝の快進撃、ついにインディアンズは首位のヤンキーズに並び、優勝の行方は本拠地クリーブランド・ムニシバル・スタジアムでの最終戦に持ち込まれる・・・。
寸評
野球を題材にして大真面目なコメディを作ってしまうアメリカ映画の底力を感じさせる。
しかも描かれるのが実際のメジャーリーグの球団であるクリーブランド・インディアンスで、その相手となるのもニューヨーク・ヤンキースである。
万年下位争いの弱小球団と常勝軍団の対決というのはお決まりと言えばお決まりなのだが、実際の球団で描かれると説明を受けなくても状況が呑み込めてしまう。
約束通りの始まりで、オーナーの目論見によってポンコツ選手が参集してくるところから始まる。
膝を怪我していてまともに2塁送球が出来ないキャッチャーのジェイク・テーラー。
球は速いがコントロールがままならない投手のリッキー・ボーンは刑務所から出てきたばかり。
紛れ込んだウィリー・メイズ・ヘイズは足は速いが、ボールを前に飛ばすことが出来ない。
打撃は健在だが、守備ではかつて重傷を負ったこともあって怠慢プレーが目立つ3塁手のロジャー・ドーン。
ペドロ・セラノは直球ならホームランを連発するが、変化球はからっきしダメで三振ばかりのバッターだ。
エディー・ハリスというベテランピッチャーは肩や腹に食用油脂やローションなどを塗って不正投球をする。
一癖も二癖もある連中と言うのはこの手の映画のパターンの一つだし、最初はそれらの弱点が出て負けているが、やがて徐々に勝ちだしていくのも期待通りだ。
これにジェイクと別れた元恋人のリン・ウェルズとのよりを戻していく話がしっとりとさせるパートを受け持っている。
リンは婚約者がおり、相手は約束通り真面目で金持ちの男である。
ジェイクがリンに再アタックする様子は青春映画の様でもあり微笑ましい。
女性はオーナーのレイチェル・フェルプス以外に、ドーンの奥さんが登場するが、なぜボーンと関係を持ったのか、詳しく描かれていない。
単に浮気性でボーンに興味を持ったためなのか、浮気を自らドーンに告げているので、もしかしたらオーナー女性の差し金でチーム内に不協和音を起こしたかったのかもしれない。
経緯を描いておいても良かったのではないかと思う。
ペナントレースの方は、これまたお決まりの通りインディアンスが追い上げてヤンキースと並んでしまう。
プレーオフとなり、しかも同点で9回表ヤンキースの攻撃は2アウト満塁という局面を迎える。
ここで「WILD THING」の歌声が球場にこだまする中を、チャーリー・シーンのボーンが黒縁眼鏡をかけ颯爽と登場するのだが、このシーンは何度見ても身震いがする。
球場の全員がインディアンスファンといった様相で、皆がダンスして大いに盛り上げる。
そして劇的幕切れとなるのだが、球場の臨場感を出す演出はいつもながらアメリカ映画は上手い。
実況中継を行っている地元のアナウンサーがコメディに拍車をかけるような中継で笑わせる。
ボーンに代わって先発したハリスは自慢の不正投球を一度も見せなかった。
そんなわけで、ちょっと雑なところもあるけれど、野球映画ファンなら楽しめる仕上がりになっている。
インディアンスはこの映画が作られたころは弱小チームの代名詞になっていたようだが、映画のヒットと共に観客数も増え、チームも強くなっていき黄金期を迎えることになったから、映画の貢献は計り知れないと思う。
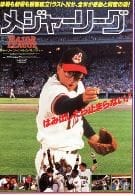
監督 デイヴィッド・S・ウォード
出演 トム・ベレンジャー
チャーリー・シーン
コービン・バーンセン
マーガレット・ウィットン
ジェームズ・ギャモン
レネ・ルッソ
ストーリー
アメリカンリーグ、東地区クリーブランド・インディアンズは伝統こそあるが、ここ34年間優勝から遠ざかり、Aクラスすら叶わない有様である。
急死した夫の跡を継いで新オーナーとなったダンサー上がりのレイチェル・フェルプスは、本拠地をマイアミに移すため、市の条約に従い、1年間の観客動員数80万人を下回らせようと企んでいた。
彼女はマネージャーのチャーリー・ドノヴァンに新チームのリストを渡し、監督のルー・ブラウンを始めとする一癖も二癖もある連中を集めさせた。
メキシカンリーグのキャッチャー、ジェイク・テーラーや刑務所から仮出所してきたピッチャーのリッキー・ボーンたちは、憧れのメジャーリーグ入りに張り切るが、もとより実力のない彼らの戦いぶりは惨めで、連戦連敗を繰り返していた。
ある日ジェイクは、町で別れた妻リンと出会った。
彼女には新しい婚約者がいたが、彼は想いが断ち切れないためにプレーにより熱がこもっていった。
そしてノーコンに悩むリッキーがメガネをかけて登板するや、見違えるようなピッチングを披露し、チームに勝利をもたらした。
チャーリーたちは事の真相を知り、以後チームの結束は一段と強まり、士気はますます高まった。
一転してチームは連戦連勝の快進撃、ついにインディアンズは首位のヤンキーズに並び、優勝の行方は本拠地クリーブランド・ムニシバル・スタジアムでの最終戦に持ち込まれる・・・。
寸評
野球を題材にして大真面目なコメディを作ってしまうアメリカ映画の底力を感じさせる。
しかも描かれるのが実際のメジャーリーグの球団であるクリーブランド・インディアンスで、その相手となるのもニューヨーク・ヤンキースである。
万年下位争いの弱小球団と常勝軍団の対決というのはお決まりと言えばお決まりなのだが、実際の球団で描かれると説明を受けなくても状況が呑み込めてしまう。
約束通りの始まりで、オーナーの目論見によってポンコツ選手が参集してくるところから始まる。
膝を怪我していてまともに2塁送球が出来ないキャッチャーのジェイク・テーラー。
球は速いがコントロールがままならない投手のリッキー・ボーンは刑務所から出てきたばかり。
紛れ込んだウィリー・メイズ・ヘイズは足は速いが、ボールを前に飛ばすことが出来ない。
打撃は健在だが、守備ではかつて重傷を負ったこともあって怠慢プレーが目立つ3塁手のロジャー・ドーン。
ペドロ・セラノは直球ならホームランを連発するが、変化球はからっきしダメで三振ばかりのバッターだ。
エディー・ハリスというベテランピッチャーは肩や腹に食用油脂やローションなどを塗って不正投球をする。
一癖も二癖もある連中と言うのはこの手の映画のパターンの一つだし、最初はそれらの弱点が出て負けているが、やがて徐々に勝ちだしていくのも期待通りだ。
これにジェイクと別れた元恋人のリン・ウェルズとのよりを戻していく話がしっとりとさせるパートを受け持っている。
リンは婚約者がおり、相手は約束通り真面目で金持ちの男である。
ジェイクがリンに再アタックする様子は青春映画の様でもあり微笑ましい。
女性はオーナーのレイチェル・フェルプス以外に、ドーンの奥さんが登場するが、なぜボーンと関係を持ったのか、詳しく描かれていない。
単に浮気性でボーンに興味を持ったためなのか、浮気を自らドーンに告げているので、もしかしたらオーナー女性の差し金でチーム内に不協和音を起こしたかったのかもしれない。
経緯を描いておいても良かったのではないかと思う。
ペナントレースの方は、これまたお決まりの通りインディアンスが追い上げてヤンキースと並んでしまう。
プレーオフとなり、しかも同点で9回表ヤンキースの攻撃は2アウト満塁という局面を迎える。
ここで「WILD THING」の歌声が球場にこだまする中を、チャーリー・シーンのボーンが黒縁眼鏡をかけ颯爽と登場するのだが、このシーンは何度見ても身震いがする。
球場の全員がインディアンスファンといった様相で、皆がダンスして大いに盛り上げる。
そして劇的幕切れとなるのだが、球場の臨場感を出す演出はいつもながらアメリカ映画は上手い。
実況中継を行っている地元のアナウンサーがコメディに拍車をかけるような中継で笑わせる。
ボーンに代わって先発したハリスは自慢の不正投球を一度も見せなかった。
そんなわけで、ちょっと雑なところもあるけれど、野球映画ファンなら楽しめる仕上がりになっている。
インディアンスはこの映画が作られたころは弱小チームの代名詞になっていたようだが、映画のヒットと共に観客数も増え、チームも強くなっていき黄金期を迎えることになったから、映画の貢献は計り知れないと思う。























