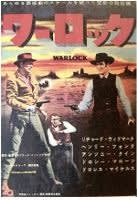「ああ爆弾」 1964年 日本

監督 岡本喜八
出演 伊藤雄之助 高橋正 越路吹雪 砂塚秀夫 中谷一郎
沢村いき雄 本間文子 重山規子 北あけみ 天本英世 有島一郎
ストーリー
大名組六代目組長の大名大作(伊藤雄之助)は、子分の太郎(砂塚秀夫)をつれて、三年振りで娑婆に出て来たが、俗界のようすは一変していた。
大勢の子分をかかえた大名組は、市会議員に立候補する矢東弥三郎(中谷一郎)にのっとられていたのだ。
そして二号のミナコ(重山規子)まで、子分のテツ(天本英世)に寝取られて、大作は悄然とした。
大名の家には矢東の表札がかけられ、妻の梅子(越路吹雪)は新しい宗教にこって太鼓を叩き、息子の健作(高橋正)は新聞配達をしているという落ちぶれように大作は愕然とする。
思い余った大作はドスを片手に殴り込んだが果せず、幼馴染のシイタケこと椎野(沢村いき雄)に助けられた。
シイタケは、矢東の運転手で毎週銀行に預金をおろしに行くという。
話を聞いた大作は、矢東の口癖の“ぺンは文化の生命なり”の不愉快な仮面を剥ぎ、平和産業の看板をかける組をわがものにしようと、太郎が爆弾作りの名人なのを利用して万年筆に爆弾を仕組んで、矢東を狙った。
矢東が床屋に行ったのを機会に、清掃員に化けた大作と太郎は、矢東の背広の万年筆をすりかえたが、丁度一緒に来ていたシイタケが、その背広を持つと銀行に出かけていったので二人は青くなった。
貧乏に敗けたシイタケは、預金の金をもってドロンをきめていたが、折しも、銀行ギャングに会い、万年筆も金も置いて逃げ出した。
翌朝、爆弾仕掛けの万年筆は掃除婦の手に渡り、健作はそれを300円で買って大得意。
大作も見覚えのある万年筆に、ようやくの思いで捨てさせた。
一方矢東は選挙に敗れたが、一案を思いついた大作はゴルフボールに爆弾をしかけ、当選議員の命とひきかえに、500万でボールを矢東に売った。
身代り当選に喜んだ矢東だが、またも健作がキャディーとして市会議員についていると知り、太郎はゴルフ場に車を走らせたが、一瞬早くボールは場外に飛び、太郎の車の傍で爆発した。
寸評
これをミュージカルと言って良いのか悪いのか分からないが、ドタバタもドタバタのバタクサイ喜劇であることだけは確かと言える作品で、岡本喜八が映画という媒体を使って思いっきり遊んでいる。
なんといってもこの作品の見所は狂言舞台の如き監獄の中での伊藤雄之助と砂塚秀夫の立ち回りに始まる種々雑多な音楽を使いまくる佐藤勝の音楽と、馬鹿げたシーンを真面目に演じる役者たちの姿であろう。
狂言をメインに全編ミュージカル調のノリで進められ、どこまで本気なのかよくわからないという作品である。
伊藤雄之助の狂言が結構な時間を割いて描かれ、それが終わってやっとタイトルが表示される。
ストーリーは獄中のヤクザの親分(伊藤雄之助)と爆弾作りの犯人(砂塚秀夫)が出所するところから始まる。
親分は出所したもののどうも勝手が違い、組に帰ればすっかり企業化しており違う社長までいる始末。
自分の居場所も無く、やけくそになった伊藤雄之助と砂塚秀夫が「ボールペン爆弾」で社長を木っ端微塵に企てるという支離滅裂な話である。
伊藤雄之助と砂塚秀夫が同じ牢屋に入っているが、その牢屋はまるで能舞台のようであり、伊藤雄之助がいきなり狂言をやりだす。
同房の太郎を太郎冠者と呼び、伊藤雄之助はすっかり狂言師である。
伊藤雄之助も砂塚秀夫もアクの強い役者で、アクの強い作品に拍車をかけている。
このアクの強さについていけるかどうかがこの作品への好みに大いに影響するであろう。
僕はこの作品の面白さを頭の中で理解はできるのだが、胸の内にある感性としては相容れないものを感じる。
狂言で始まった音楽は、南無妙法蓮華経と唱えて太鼓をたたくお題目へと引き継がれ、ジャズやロックが現れたかと思えば浪曲も語られ、ダンス・ミュージックまで登場する。
ごった煮であるが音楽映画の感じはしない。
むしろ完全ミュージカルの音楽映画とした方がウケたのではないかと思う。
東宝はよくこのような作品を撮ることを許したものだと思う。
伊藤雄之助が出所してきたところ、自分を取り巻く環境がすっかり変わってしまっていることに重点を置いた前半のテンポは、作品の性格からすれば遅いと感じる。
それが万年筆爆弾が登場してから改善されて、作品自体の面白さが成長していく。
銀行では残高が10円合わないためのやり取りがミュージカル調で描かれる。
当選と思ってすっかり準備していた中谷一郎が次点と分かり、大暴れが始まるパーティ会場のドタバタもミュージカル映画のような描き方である。
せっかく伊藤雄之助の女房として越路吹雪が出演しているのだから、彼女が本格的に唄うシーンがあっても良かったような気がした。
結局、中谷一郎には何事も起こらず、大作とシイタケがタクシー会社を始めるつもりで買った車は爆弾で燃えてしまい、これでは悪事ははびこると言っているようなものだが、だから喜劇なのかもしれない。
僕は余り評価しないが、岡本喜八ファンは「鴛鴦歌合戦」と並ぶミュージカルの傑作だと評価しているらしい。
十人十色である。