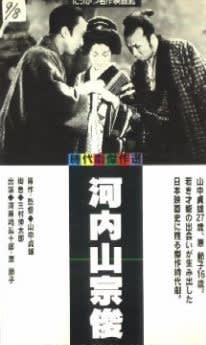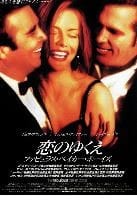「ゴジラ」

監督 本多猪四郎
出演 志村喬 河内桃子 宝田明 平田昭彦
堺左千夫 村上冬樹 山本廉 鈴木豊明
馬野都留子 岡部正 小川虎之助
手塚勝己 中島春雄 林幹 恩田清二郎
菅井きん 榊田敬二 高堂國典 東静子
ストーリー
太平洋の北緯二十四度、東経百四十一度の地点で、次々と船舶が原因不明の沈没をした。
新聞記者萩原(堺左千夫)は遭難地点に近い大戸島へヘリコプターで飛んだ。
島では奇蹟的に一人だけ生残った政治(山本廉)が、海から出た巨大な怪物に火を吐きかけられて沈んだというが、誰一人信じない。
只一人、島の老漁夫だけは昔からの云い伝えを信じ、近頃の不漁もその怪物が魚類を食い荒すせいだという。
海中に食物がなくなれば、怪物は陸へ上って家畜や人間まで食べると伝えられている。
萩原は信じなかったが、暴風雨の夜、果して怪物は島を襲って人家を破壊した。
国会は大戸島の被害と原因を確かめる調査団を派遣した。
古生物学者山根博士(志村喬)を先頭に、その娘で助手の恵美子(河内桃子)、彼女の恋人でサルベージ会社の尾形(宝田明)、原子物理学の田辺博士(村上冬樹)に萩原と政治の弟新吉(鈴木豊明)も加った。
そして調査団は伝説の怪物が、悠々と巨大な姿を海中に没するのを見た。
帰国した山根博士は200万年前の海棲爬虫類から陸上獣類に進化する過程の生物ゴジラが、海底の洞窟にひそんで現代まで生存していたが、度々の水爆実験に生活環境を破壊されて移動し、而も水爆の放射能を蓄積して火を吐くのだと説明した。
フリゲート艦が出動して爆雷を投下したが何の効果もなく、ゴジラは復讐するかの如く海上遥かに浮上り、東京に向って進んだ。
直ちに対策本部が設けられたが一夜にして東京は惨澹たる街となった。
寸評
なかなか登場しないゴジラのシチュエーションなんか、スピルバーグの「ジョーズ」などよりもいい。
初めて登場するときの、目ん玉だけがギョロリとするところなんか最高だ。
白黒映画のせいか、前半部分なんかやけにリアリティがあって、ゴジラの存在が現実味を帯びていたように思う。
僕は、日本のSF映画でこの「ゴジラ」を追い抜く映画が、いまだ出現していないように思うのだが・・・。
「ゴジラ」はシリーズ化されて何本も作られたが、断然この第一作が光っている。
やはりゴジラは怖くなくてはならない。
1952年(昭和27年)11月1日、アメリカはマーシャル諸島エニウェトク環礁にあるエルゲラップ島で、史上初の水爆実験を行った。
実験でエルゲラップ島は粉塵となって海上から消滅し、海底には直径1600メートルで深さ70メートルの巨大なクレーターができあがったそうだ。
広島の原爆の700倍以上の威力を持つものだった。
そして1954年3月1日に再びビキニ環礁で実験が有り、日本のマグロ漁船「第五福竜丸」が被爆してしまう。
映画「ゴジラ」は偶然の産物か、まさに時を同じくして3月13日に封切られた。
核戦争への警鐘をテーマに据えながら、悲劇としか言いようのない出来事とともにゴジラが我々の目の前に登場したのだ。
水爆実験はたびたび行われていたので、先見性が有ったと言えるかどうかわからないが、その登場した時代背景を考え合わせると、娯楽性に富みながらも社会的テーマを持たせた正しく第一級の作品だ。
キャラクターで目立っているのが芹沢博士の平田昭彦で、彼が作り出したオキシジェン・デストロイヤーを通じて核に対するメッセージが直接的に語られる。
言い換えればオキシジェン・デストロイヤーは核兵器そのものである。
その芹沢博士と山根博士の娘の恵美子、そして彼女の恋人である尾形の微妙な関係が大人の鑑賞に耐えさせていたように思う。
ゴジラは人間によって生み出された悲劇と恐怖の象徴だが、生み出しておきながら滅ぼさざるを得ない人間の身勝手さも感じ取れる。
最後はついにやっつけたという感覚より、ゴジラに対して感情移入してしまっているのはそんな自責の念を感じ取ってしまっていたためだろう。
ゴジラと戦った怪獣たち
キングコング、モスラ、キングギドラ、ラドン、エビラ、カマキラス、クモンガ、ガバラ、ヘドラ、ガイガン、メカゴジラ、ビオランテなどだが、ともに戦ったミニラやアンギラスもいる。
1995年12月公開の「ゴジラVSデストロイア」で戦うデストロイアは、実に30年も前の第一作で使用されたオキシジェン・デストロイヤーの化身。
最大ヒットは、第三作の「キングコング対ゴジラ」。
この成功が以降のゴジラとの対戦カードの変化だけになってしまった原因と思う。

監督 本多猪四郎
出演 志村喬 河内桃子 宝田明 平田昭彦
堺左千夫 村上冬樹 山本廉 鈴木豊明
馬野都留子 岡部正 小川虎之助
手塚勝己 中島春雄 林幹 恩田清二郎
菅井きん 榊田敬二 高堂國典 東静子
ストーリー
太平洋の北緯二十四度、東経百四十一度の地点で、次々と船舶が原因不明の沈没をした。
新聞記者萩原(堺左千夫)は遭難地点に近い大戸島へヘリコプターで飛んだ。
島では奇蹟的に一人だけ生残った政治(山本廉)が、海から出た巨大な怪物に火を吐きかけられて沈んだというが、誰一人信じない。
只一人、島の老漁夫だけは昔からの云い伝えを信じ、近頃の不漁もその怪物が魚類を食い荒すせいだという。
海中に食物がなくなれば、怪物は陸へ上って家畜や人間まで食べると伝えられている。
萩原は信じなかったが、暴風雨の夜、果して怪物は島を襲って人家を破壊した。
国会は大戸島の被害と原因を確かめる調査団を派遣した。
古生物学者山根博士(志村喬)を先頭に、その娘で助手の恵美子(河内桃子)、彼女の恋人でサルベージ会社の尾形(宝田明)、原子物理学の田辺博士(村上冬樹)に萩原と政治の弟新吉(鈴木豊明)も加った。
そして調査団は伝説の怪物が、悠々と巨大な姿を海中に没するのを見た。
帰国した山根博士は200万年前の海棲爬虫類から陸上獣類に進化する過程の生物ゴジラが、海底の洞窟にひそんで現代まで生存していたが、度々の水爆実験に生活環境を破壊されて移動し、而も水爆の放射能を蓄積して火を吐くのだと説明した。
フリゲート艦が出動して爆雷を投下したが何の効果もなく、ゴジラは復讐するかの如く海上遥かに浮上り、東京に向って進んだ。
直ちに対策本部が設けられたが一夜にして東京は惨澹たる街となった。
寸評
なかなか登場しないゴジラのシチュエーションなんか、スピルバーグの「ジョーズ」などよりもいい。
初めて登場するときの、目ん玉だけがギョロリとするところなんか最高だ。
白黒映画のせいか、前半部分なんかやけにリアリティがあって、ゴジラの存在が現実味を帯びていたように思う。
僕は、日本のSF映画でこの「ゴジラ」を追い抜く映画が、いまだ出現していないように思うのだが・・・。
「ゴジラ」はシリーズ化されて何本も作られたが、断然この第一作が光っている。
やはりゴジラは怖くなくてはならない。
1952年(昭和27年)11月1日、アメリカはマーシャル諸島エニウェトク環礁にあるエルゲラップ島で、史上初の水爆実験を行った。
実験でエルゲラップ島は粉塵となって海上から消滅し、海底には直径1600メートルで深さ70メートルの巨大なクレーターができあがったそうだ。
広島の原爆の700倍以上の威力を持つものだった。
そして1954年3月1日に再びビキニ環礁で実験が有り、日本のマグロ漁船「第五福竜丸」が被爆してしまう。
映画「ゴジラ」は偶然の産物か、まさに時を同じくして3月13日に封切られた。
核戦争への警鐘をテーマに据えながら、悲劇としか言いようのない出来事とともにゴジラが我々の目の前に登場したのだ。
水爆実験はたびたび行われていたので、先見性が有ったと言えるかどうかわからないが、その登場した時代背景を考え合わせると、娯楽性に富みながらも社会的テーマを持たせた正しく第一級の作品だ。
キャラクターで目立っているのが芹沢博士の平田昭彦で、彼が作り出したオキシジェン・デストロイヤーを通じて核に対するメッセージが直接的に語られる。
言い換えればオキシジェン・デストロイヤーは核兵器そのものである。
その芹沢博士と山根博士の娘の恵美子、そして彼女の恋人である尾形の微妙な関係が大人の鑑賞に耐えさせていたように思う。
ゴジラは人間によって生み出された悲劇と恐怖の象徴だが、生み出しておきながら滅ぼさざるを得ない人間の身勝手さも感じ取れる。
最後はついにやっつけたという感覚より、ゴジラに対して感情移入してしまっているのはそんな自責の念を感じ取ってしまっていたためだろう。
ゴジラと戦った怪獣たち
キングコング、モスラ、キングギドラ、ラドン、エビラ、カマキラス、クモンガ、ガバラ、ヘドラ、ガイガン、メカゴジラ、ビオランテなどだが、ともに戦ったミニラやアンギラスもいる。
1995年12月公開の「ゴジラVSデストロイア」で戦うデストロイアは、実に30年も前の第一作で使用されたオキシジェン・デストロイヤーの化身。
最大ヒットは、第三作の「キングコング対ゴジラ」。
この成功が以降のゴジラとの対戦カードの変化だけになってしまった原因と思う。