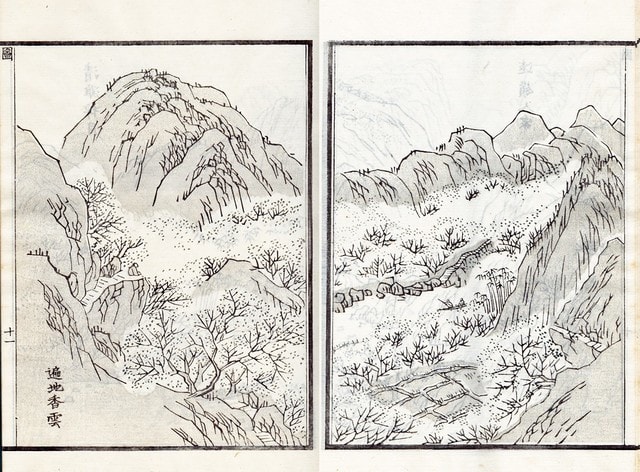様々な伝統芸術の道が廃れてゆく原因には「内部からの崩壊」もあれば、「外部からの侵食」もあるに違いない。前者の原因は皮肉にも、先哲が探求し創造した型を継承してゆくという、伝統芸術が担う使命の中に萌芽する。型を盲目的に踏襲してゆく中で、何時しかその規矩を生み出した本質を取り落としてゆく形骸化、《型の空洞化》である。後者の原因の一つは、時代の潮流への迎合姿勢に始まる《型の歪曲》である。江戸時代の漢方医家、和田東郭著『蕉窓雑話』の中で糾弾されている、いわゆる“人そばえの花”が好例である。“人そばえの花”が持て囃される時、型は社会風潮に媚びたものに歪められてゆく。いや媚びなんとする姿勢の発露こそが既に内部崩壊の序章である。
現代の趨勢である、“私探し”、“only one”を「正」とする価値観に裏打ちされた、個性を生かすという錦の御旗の下、模範とする既成の型は“私らしさ”を縛る前近代的な桎梏と貶められて、「譎」の烙印が押されることがある。『風姿花伝』序章の末尾に「稽古は強かれ、情識(じょうしき)は勿れとなり。」という言葉がある。強かれはたゆみなくの意味である。情識とは凡夫が持つ迷いの心であり、良い意見に耳をかさず自分勝手な考えに凝り固まることを意味し、師の御教えを守る稽古に対する反語として挙げられている。芸の修行に際して生悟りの我流に流れてはならぬという戒めである。平成最後の日にあたり、自戒の意味を込めて、拳拳服膺すべき言葉として此処に残して置こうと思う。
"A great civilization is not conquered from without until it has destroyed itself from within.” (文明が征服される根本原因は内部からの崩壊である。)
これは映画『Apocalypto』(メル・ギブソン監督、2006)のオープニングに引用された、歴史家、哲学者ウィル・デュラントがローマ帝国について語った言葉である。『アポカリプト』は、マヤ帝国の崩壊前夜、主人公の青年ジャガー・パウが風前の灯に置かれた捕虜の身から一人脱出し、ジャングルの中を追撃する傭兵団を討ち果たし、故郷で彼を待ち続けていた妻子とともに新天地を求めて彼方へと旅立つまでの大活劇である。ラストシーンは、帝国征服に押し寄せた、海上に浮かぶ西洋艦隊の木の間越しの姿であった。
「内因為本、外因為輔」という諺がある。外襲は崩壊の最後の引き金に過ぎないことがある。『黄帝内経素問』における「不相染者、正気存内、邪不可干、避其毒気。」(正気が充実していれば、外邪の侵入は起らない、感染も発症も防げるのである。)の論述もまた同義である。