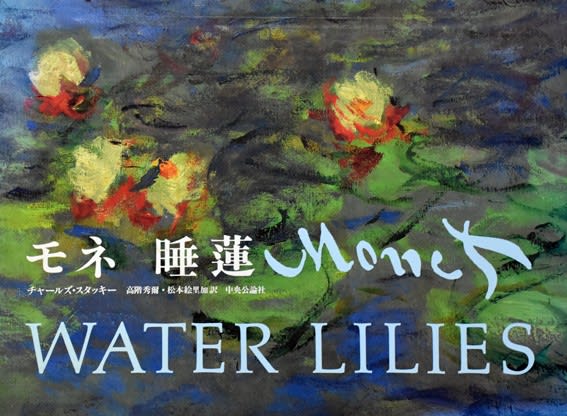
「あるとき、《睡蓮》の主題を装飾的に使ってみたいという誘惑にかられた。室内全体が壁の長さいっぱいに広がる睡蓮のみで包み込まれ、そこに終わりのない全体、水平性も岸もない水面の幻影が生まれる。心落ち着く静かな水を眺めることは疲れ切った神経を休め、だれにせよそこに生きる者にとっては、花に埋もれた水槽の中で平和な瞑想に浸る避難所ができあがるだろう。」
(モネの《睡蓮》│「モネ 睡蓮」, p18)

気象庁は本年の猛暑を「災害と認識」との見解を示す異例の記者会見を開いた。大暑をはるかに凌ぐ酷暑が日本を焼き尽くした次は、列島を西進する異例のコースをとる台風12号が西日本を蹂躙している。第二弾・松竹水聲涼は画集『モネ 睡蓮』を取上げて、せめて風水面に来る時の清意と参りたい。本書はオランジュリー美術館壁面を飾るモネの「睡蓮」連作や数多くの各地の関連作品が収録され、広げれば折りたたまれた長さが1mを越える紙面で作品を拝することができる。冒頭はモネ自身の言葉で、以下に続くのは本画集のモネ論からの一節である。
「日本のやりかたのように、《睡蓮》は自然の断片によって、全体を包み込むようなさらに広い空間を暗示している。この意味でモネの作品の根本には、彼のよき先導者であったエドゥアール・マネの《フォリー・ベルジェールの酒場》(1881-82)がある。視界の外にあるものが、背景の鏡によって視界に入る場所に移されているのである。《睡蓮》にみられる鏡に映したような上下逆さのイメージと上下が正しいイメージの二重の共存は、祈りが思想を超えるように、<上><下><前><後>などの通常の空間的な限定を超越して、見る者の視覚を二重の意味で意識させるのである。」
(モネの《睡蓮》│「モネ 睡蓮」, p18)
訳者の美術史学者、高階秀爾名誉教授は、著書『日本美術を見る眼』、枝垂れモティーフの章で、《睡蓮》展に寄せられた批評に対するモネの反論の言辞、「作品の源泉をどうしても知りたいというなら、そのひとつとして、昔の日本人たちと結びつけてほしい。彼らの稀に見る洗練された趣味は、いつも私を魅了してきた。影によって存在を、部分によってその全体を暗示するその美学は、私の意にかなった-----。」を提示され、「モネが的確に見抜いたように「部分によって全体を暗示する」というやり方は、日本美術の大きな特色である。」と、ジャポニスムが西洋にもたらした美学に関する詳細な論説を述べておられる。
ところで先の「自然の断片」という言葉に些か抵抗を感じたのは、私が日本人であるからか。果たして「部分」は「全体」から切り取られた断片か、全体集合に含まれる部分集合(下位集合)か。事によると「部分によって全体を暗示する」というやり方の理解が、東洋と西洋では些か異なるのかもしれない。「部分」はあるがままの自然の美の一部に注目して取り出された部分(fragment)ではなく、縮小図(miniature)でもない。東洋の「部分」には「全体」がそのままに顕露する。そして「部分」が生起する過程に連動して、「全体」は限定された枠を超えてゆく。生け花で言うならば、「部分」がかきつばたの作品とすれば「全体」は何と捉えるべきだろう。初めに想起されるのが仮に太田神社や小堤西池のかきつばたであるならば、次には何処か群れ咲くかきつばた、さらには永遠の花、生きとし生けるもの、あるいは遥かにこれらを越えたものに対応するかもしれない。いまだ私が至れぬままの、華道大和未生流で斯くあるべしと御示唆いただいた生け花はそのような花である。興味深いことに、東西医学における「部分」と「全体」の捉え方にも、東西美術の絵画観において指摘される差異と似通った点がある。
参考資料:
チャールズ・スタッキー著, 高階秀爾・松本絵里加訳:「モネ 睡蓮」, 中央公論社, 1988
高階秀爾著:「日本美術を見る眼」, 岩波書店, 1991
















