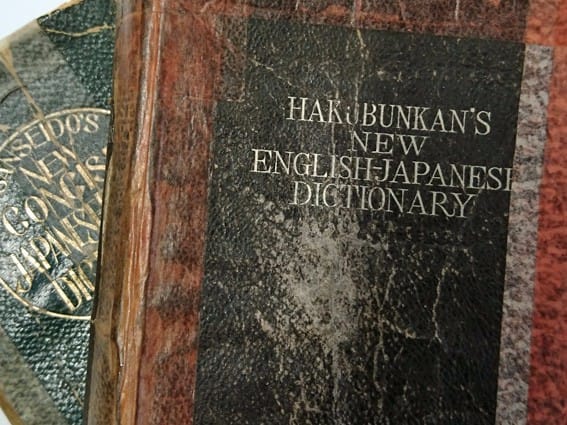
黄葉がこの地で黄葉医院を開業して四十有余年、開業の年に生まれた雄二は地方病院勤務を辞してクリニックを新設した。一緒にやろうという雄二の提案を黄葉は断ったのである。
雄二のクリニックが完成した時、黄葉は白亜の正面玄関をくぐるなり、揃いのベビーピンクの制服をまとってずらりと並んだスタッフ一同に「大先生、おはようございます。」と一斉に呼びかけられた。院内には真新しい医療器械が所狭しと並び、電子カルテがどうのこうのと説明してくれた代物を始め、黄葉の眼にはどれもが御大層な玩具に見えた。道具に使われやがってと思わず独りごちたが、得意満面な新院長の耳には届かない。
定時にはきっかり診療終了となる黄葉医院に対し、向こうは門前市をなす盛業ぶりだと聞く。これはこれで第一ラウンド終了というべきか。もし反対の状況ならば、それはそれで親として心配に違いない。先輩医として言ってやりたいことは幾つもあるが、所詮代わりに歩いてやることも、また反対に歩いてもらうことも出来ない道である。車輪を削る技の伝授にあたり、子に喩すこと能わず、また子も受くること能わず。あれは誰の言葉であったか。
さて黄葉医院の受付であるが、何十年にもわたり医療事務兼看護助手を担当してくれているのが、黄葉より六歳年下のヨネさんである。院長がすっかりくたびれた爺さんになったように、向こうも負けじ劣らず、まぎれもない婆さんになった。雄二との親子喧嘩の時も心得たもので、聞いているのかいないのか、肩がこったと言わんばかりにぶんぶんと右腕をわざと振り回してみせる。このところ年々腰痛が酷くなり、退職をほのめかされてはや五年である。治療の傍らもう一年と勤め続けてくれたが、他に家庭の事情もあり今年がもう限界なのだろう。
その様な訳ではるか以前、医院の門脇に求人のプレートをぶらさげたのである。今やすっかり失念していたプレートを見てと、とある昼下がり、千賀子という名の一人の女性が履歴書を携えて黄葉医院にやって来た。長い付き合いの中で同性を終ぞ褒めたことのないヨネさんである。本採用を決めた後も大いに気を揉んだのだが、黄葉の心配は全く杞憂に終わった。何処がうまくいったのか、ヨネさんの仏頂面が次第に和んできた。
「まったく何とやらに鶴だね。つくづく物好きだ。」
黄葉と同い年の平さんが診察室のベッドで腹を晒したまま声を挙げると、間髪入れず聞きなれたどら声が返って来た。
「こちとらすっかり羽が抜けた老け鶴で悪うござんしたね。」
平素は柔らかくへこむ平さんの臍下の腹壁もいつになく弾力のある硬さを示し、関元に置いた黄葉の腹診の掌を押し返してくるのである。
そうしてしばらく老若の鶴に守られていた黄葉医院であったが、ついにヨネさんが翔び立つ日が来た。一段と秋めいて来た日の夕暮れ、黄葉、ヨネさんと千賀子の三人でささやかな餞の宴を設けた。持病があった連れ合いの入院時には子守までしてもらった雄二にも声をかけていたが、診療が終わらない、くれぐれも宜しく伝えてくれと終宴間際に連絡が入った。
沿線の駅まで見送り、体を大切になあ、長い間今まで本当に有難うと述べた時、ヨネさんは黄葉や千賀子の手を何度も何度も確かめるように握り返した。
「老鶴はただ消え去るのみ。」
そして最後の笑顔を見せて改札口に消えていった。
千賀子が一人で担当する様になり二ヶ月経過した頃である。
「今お時間宜しいですか。」
山の様な書類を前に、どれから片付けようかと頭をひねっていた日の午後、黄葉の背に向かって千賀子が声をかけてきた。
「申し上げたいことがあります。」
振り返った黄葉は黙って千賀子の次の言葉を待った。
「わたし、女性ではありません。」
俯いた肩口にはらりと切りそろえた髪が揺れた。
それから一ヶ月後の医院の休診日、いくつもの器械や端末、様々なパーツを車に積み込んで凱旋してきた千賀子は、ただちに黄葉医院におけるIT化に向けての整備を開始した。診療室の一隅から見やる眼に映った遺漏のない果断な一連の手際には、自分とはまた異なる世界で「きちんと飯を喰ってきた」匂いがした。
XX年Y月、黄葉医院の様な小さな医院にも、診療報酬請求明細書、いわゆるレセプトのオンラインでの完全提出が義務付けられる日が来る。共に厳しい時代を生き抜いてきた旧友の中には、それを機に勇退すると心に決めている者がいる。
北窓を開ければ、はるか昔、このように見上げた時と同じ色に澄んだ、雨過天晴の天空が広がっていた。ふいに眼前を横切って一羽の鳥が彼方へと飛び去った。
「鳥空を飛ぶに、飛ぶといえども空の際なし、か。」
黄葉は振り返り、一息いれようやと新たな一人の僚友に呼び掛けた。
(医療施設の規模により段階的に推し進められてきた電子レセプト請求(オンラインまたは電子媒体による請求)の猶予措置は平成27年3月31日で終了した。同年4月診療分以降の請求は電子レセプト請求が原則義務化となっている。)

六味地黄丸:熟地黄、山薬、山茱萸の三補薬と、沢瀉、茯苓、牡丹皮の三瀉薬から構成される。腎陰不足に対する基本方剤であるが、加えすぎず減じすぎず、切れ味が特別に優れるという方剤ではない。何を聞かれても、はい、よろしいですねと答えるような人の様だという意味で「好好先生」と称すると、かつて方剤学の講義で伺った。むしろこのような方剤の方が処方医の手並みを静かに見ているのである。












