一年を通して日本全国の各市町村で何らかのお祭りが必ずあります。
故郷を思うとき、まず思い出されるのが祭りではないでしょうか?
ただ世の中には、地元の人には普通で真剣なんだけれど、
外部の人から見ると摩訶不思議な世界に見えてしまう祭りがあります。
これを世の人は「奇祭」と呼びます。
奇祭とは、独特の習俗を持った、風変わりな祭りのことと解説されています。
これを、人によっては「とんまつり(トンマな祭)」
「トンデモ祭」とも呼んでいるようで、
奇祭に関する関連書物も数多く出版されています。
よく取り上げられるのは、視覚的にインパクトがある祭り
(性器をかたどった神輿を担ぐ祭りなど)がよく話題になりますが、
ほかにも火を使った祭りや裸祭り、地元の人でさえ起源を知らない祭りや、
開催日が不明な祭りなど、謎に包まれた祭りはたくさんあるようです。
これから数回に渡って奇祭を特集していきます。
その多彩さに驚くとともに、祭りは日本人の心と言われるゆえんが、
祭りの中に詰まっていることが理解できるでしょう。
特に言う必要はないと思いますが、
以下にふざけて見えようと馬鹿にしているように見えようと、
れっきとした郷土芸能であり、
日本の無形民俗文化財だということは間違いありません。
今回は、福岡県の苅田山笠と京都府の祇園祭です。
苅田山笠(宇原神社:福岡県京都郡苅田町)
苅田山笠は、福岡県京都郡苅田町で、
約570年の伝統を持つ宇原神社の神幸祭で、
毎年9月下旬から10月の第1日曜日までの15日間にわたって開催されます。
最終日の10月第1日曜日には、
勇壮・華麗な山笠14基が苅田っ子に曳かれて町を練り歩き、
苅田町役場の駐車場に勢揃いした後、山笠のぶつけ合いが激しく行われます。
このことから、苅田山笠は「けんか山笠」とも呼ばれ、
福岡県の無形民族文化財に指定されています。

苅田山笠の歴史は、神社から人間が住む里(御旅所)へ一時的に居を移し、
人々の願い事を聞かれ、また、御帰りになることを「神幸(みゆき)」といい、
その間の神事を神幸神事といいます。
神が降臨する場所はある「物」に降りると考えられ、
その物を「依代」といわれます。
一般的には「常磐木」や「大きな岩」とされています。
神幸には必ずその依代が必要で、それらを乗せる乗り物が山車、
山笠といったものへと発展したとされています。
そのため、神幸祭と山笠は切っても切れない関係にあるといえます。
宇原神社では嘉吉二年(1442)に初めて、神幸が行われ、
慶長二年(1597)以来、山笠が出るようになったといわれています。
苅田山笠は古くからの伝統を受け継いでいる稀少なものとされています。
宇原神社の御神輿は「集区」の山笠に先導され、
「浮殿の地」へ行幸されるのにお供して、
各区の山笠が神事場に全て勢揃いします。
一番最初に神事場に入るのは、神事場のお膝元である南原区の山笠となります。
「浮殿の地」は、昔、宇原神社があった場所とされ、
苅田町役場横の九州最大古墳付近を指すという資料もありますが、
現在の苅田図書館の横辺りであったともいわれています。
そのこともあり、現在、苅田町役場の駐車場で神事を行っています。

500年以上続く苅田山笠の歴史において、
昔から山笠をぶつけ合う「喧嘩山笠」だった訳ではありません。
山笠には車輪が付き、道路事情も良くなったころがその始まりといわれています。
【交通アクセス】
電車:JR日豊本線「苅田」駅下車、南へ徒歩15分。
航空:北九州空港から車で約20分。
祇園祭(八坂神社:京都府京都市東山区)
日本の三大祭の一つに挙げられる祇園祭は、
毎年7月1日から31日までの1ヶ月間、
京都市内の中心部や八坂神社で行われます。
クライマックスとなる山鉾巡行と神幸祭をはじめ、
多彩な祭事が繰り広げられます。

平安時代の前期の869年、京で疫病が流行した際、
広大な庭園だった神泉苑に、当時の国の数にちなんで66本の鉾を立て、
祇園の神を迎えて災厄が取り除かれるよう祈ったことが始まりとされています。
応仁の乱で祭りは途絶えましたが、1500年に町衆の手で再興されました。
以後、中国やペルシャ、ベルギーなどからもたらされたタペストリーなどを
各山鉾に飾るようになりました。
これらの装飾品の豪華さゆえに、山鉾は「動く美術館」とも呼ばれます。
江戸時代にも火災に見舞われましたが、
町衆の力によって祭りの伝統は現代まで守られています。

毎年、各山鉾町では、7月1日の「吉符入り」で幕を開け、
2日には山鉾巡行の順番を決める「くじ取り式」が京都市役所で行われます。
10日ごろから鉾建てが始まり、12日ごろには鉾の「曳初め」があります。
15日の宵々山、16日の宵山を経て、
17日に祇園囃子にのって山鉾が京のメインストリートをを巡行します。
夕方には、八坂神社の祭神を乗せた3基の神輿が四条寺町の御旅所に向かう
神幸祭があり、24日には神輿が御旅所から神社に戻る還幸祭が行われます。
12日ごろの「曳初め」には、女性を含む一般市民も参加できます。
16日の宵山までは、
各山鉾町ではちょうちんの明かりに照らされた山や鉾が楽しめます。
各山鉾では、病気除けとされるちまきや、
学問成就や立身出世などのお守りを手に入れることもできます。

17日の山鉾巡行の日は、午前9時、計32基の四条河原町付近を出発します。
四条通を東へ向かった後、河原町通を北上し、御池通を西進します。
四条麩屋町では、長刀鉾稚児による「注連縄切り」や、
鉾が各交差点を曲がる際の「辻回し」がハイライトとなります。

祇園祭の「ちまき」は、厄除けのために各山鉾町で売られています。
ちまきが厄除けの役割を担っているのは、
八坂神社の祭神・須佐之男命が旅の途中でもてなしてくれた蘇民将来に対し、
お礼として「子孫に疫病を免れさせる」と約束し、
その印として「茅の輪」をつけさせたのが始まりと言われています。
その後、茅の輪が変化して「ちまき」になったのではとされています。
授かったちまきは、家の門口に吊るしておき、
翌年の祇園祭で新しいちまきと取り替えるまでの1年間、
厄除け・災難除けとして重宝されています。
祇園祭のちまきは、食べ物ではありません。
通常は、笹の葉をい草で巻き、束にして作られます。
しかし2006年には黒主山保存会が、
祇園祭で初の「食べられるちまき」を販売しました。
「食べられる」と勘違いする人もいることから発想を転換し、
生麩でちまきを作り、話題になりました。

各山鉾では、お守りも販売されています。
お守りのご利益は、山鉾の由来によってそれぞれ異なります。
役行者山のお守りは、疫病除けや安産、交通安全をもたらすといいます。
鯉山は立身出世、浄妙山は勝ち守りとされています。
浄妙山は、源平合戦のきっかけとなった、
1180年の宇治橋の戦いで奮闘した筒井浄妙明秀に由来しますが、
この合戦を機に源氏が立ち上がり、平家を打ち破ったことから、
勝ち運を呼ぶ山といわれています。
露天神山では、京都が大火に見舞われた際、急に霰が降って鎮火しましたが、
霰とともに天神像が降りてきたと伝えられることから、
火除けや雷除けなどのご利益があるとされています。
【交通アクセス】
電車:JR京都駅より車で約15分。
阪急河原町駅より徒歩で約8分。
京阪祇園四条駅より徒歩で約5分。
バス:JR京都駅より市バス46・201・203・206・207番「祇園」下車すぐ。
いかがでしたか。
祭りには底知れない魅力と気分を高揚させる何かがあります。
長年にわたって受け継がれてきた祭りには、
理屈では割り切れない人々の思いが詰まっているように思います。
たかが祭り、されど祭りといったところでしょうか?










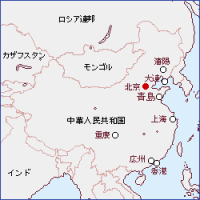
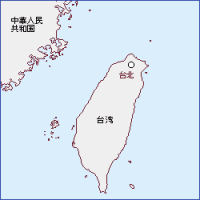
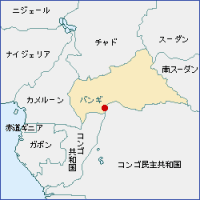
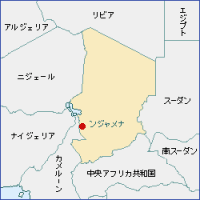
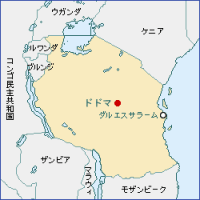
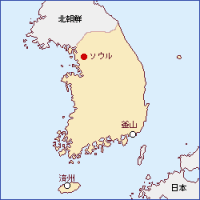

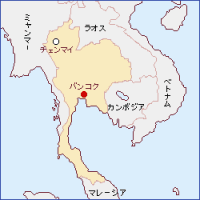
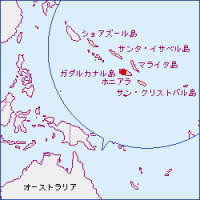
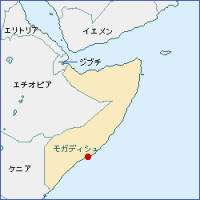
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます