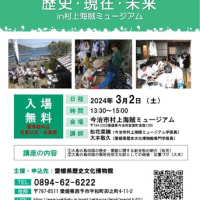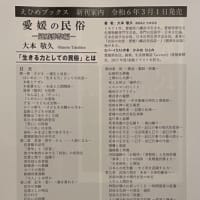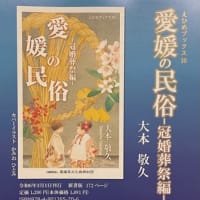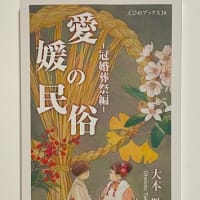「カワウソと人の交流誌」というコラムを1999年10月21日付の南海日日新聞で書いたことがある。その後、この文章は拙著『民俗の知恵』にも入れ込んだ思い入れのあるエッセイだ。昨日のニュースでカワウソは絶滅種だということになったが、心情的にはまだ宇和海のどこかにいることを願っている。完全に絶滅したと自身で受け入れるにも心の準備ができていない。
そのエッセイをここに再掲しておく。
県獣であるカワウソは、動物では県内唯一の天然記念物である。このカワウソについては、戦前は宇和海を中心に各地で生息が確認されていたが、昭和四十年代以降、目撃例がごくわずかとなってしまった。カワウソの絶滅の危機は必ずしも自然現象とは言い切れず、戦前は毛皮にするため乱獲されたり、戦後、急激に環境が破壊されるなど人為的な要因も無視できない。そもそも、弥生時代後期の神奈川県猿島洞穴出土動物遺体の中にカワウソの骨が発見されるなど、人間とのつきあいは原始・古代に遡ることがわかっている。また、平安時代中期成立の『延喜式』巻三十七典薬寮によると、カワウソが薬として朝廷に献上され、また、室町時代には塩辛にされるカワウソの史料も残っている。近代になっても、毛皮のために乱獲されるだけでなく、結核や眼病の薬としても捕られていたようである。戦後、絶滅の危機に直面すると、天然記念物に指定され、目撃例があると一躍新聞紙面を賑わすなど、一転、稀少で、しかも愛敬のある動物、人間に親しみにある動物として祀りあげられた。原始以来の人間とカワウソとの交流の歴史を見ていくと、実に、人間に翻弄されるカワウソの姿が浮び上がるのである。
人に翻弄されてきたカワウソであるが、八幡浜地方に伝わる数多くのカワウソに関する伝承を確認してみると、逆に人間の側が彼らに悪戯され、翻弄されている例が多いので面白い。この種の話は海岸部に住む戦前生まれの人であれば誰でも聞いた経験があるというくらい、枚挙にいとまがないが、数例挙げてみると次のような話がある。
「漁師が沖で漁をしていると、カワウソがこっちこい、こっちこいと手招きするので、行って見ると、船が陸に上がってしまい、難儀した。」
「島の人がカワウソを捕獲して家に連れてかえると、捕獲されたカワウソの親が、毎晩、子供をかえせ、子供かえせと言いに来た。」
「夜二時ごろ、海岸をあるいていると、防波堤の上にはちまきをして、子守をしている女性がいた。不気味に思ったがこれはカワウソが化けたものに違いないと思い、『お前はカワウソじゃろうが』と叫ぶと、消えてしまった。」(以上、大島)
「カワウソに化かされて、一晩中、山中を歩かされた。」
「カワウソが手招きして、風呂を沸かしたから入れというから入ってみると、実はお湯ではなく、枯れ葉だった。」(以上、真穴)
天然記念物に指定され、絶滅が危惧されているカワウソ。生物としての絶滅危惧とともに、身近に伝承されてきたカワウソとの交流話も消えうせる可能性がある。八幡浜地方は愛媛県内でも遅くまでカワウソが生息していた地域として、この種の話も継承していく必要があるのではないだろうか。
そのエッセイをここに再掲しておく。
県獣であるカワウソは、動物では県内唯一の天然記念物である。このカワウソについては、戦前は宇和海を中心に各地で生息が確認されていたが、昭和四十年代以降、目撃例がごくわずかとなってしまった。カワウソの絶滅の危機は必ずしも自然現象とは言い切れず、戦前は毛皮にするため乱獲されたり、戦後、急激に環境が破壊されるなど人為的な要因も無視できない。そもそも、弥生時代後期の神奈川県猿島洞穴出土動物遺体の中にカワウソの骨が発見されるなど、人間とのつきあいは原始・古代に遡ることがわかっている。また、平安時代中期成立の『延喜式』巻三十七典薬寮によると、カワウソが薬として朝廷に献上され、また、室町時代には塩辛にされるカワウソの史料も残っている。近代になっても、毛皮のために乱獲されるだけでなく、結核や眼病の薬としても捕られていたようである。戦後、絶滅の危機に直面すると、天然記念物に指定され、目撃例があると一躍新聞紙面を賑わすなど、一転、稀少で、しかも愛敬のある動物、人間に親しみにある動物として祀りあげられた。原始以来の人間とカワウソとの交流の歴史を見ていくと、実に、人間に翻弄されるカワウソの姿が浮び上がるのである。
人に翻弄されてきたカワウソであるが、八幡浜地方に伝わる数多くのカワウソに関する伝承を確認してみると、逆に人間の側が彼らに悪戯され、翻弄されている例が多いので面白い。この種の話は海岸部に住む戦前生まれの人であれば誰でも聞いた経験があるというくらい、枚挙にいとまがないが、数例挙げてみると次のような話がある。
「漁師が沖で漁をしていると、カワウソがこっちこい、こっちこいと手招きするので、行って見ると、船が陸に上がってしまい、難儀した。」
「島の人がカワウソを捕獲して家に連れてかえると、捕獲されたカワウソの親が、毎晩、子供をかえせ、子供かえせと言いに来た。」
「夜二時ごろ、海岸をあるいていると、防波堤の上にはちまきをして、子守をしている女性がいた。不気味に思ったがこれはカワウソが化けたものに違いないと思い、『お前はカワウソじゃろうが』と叫ぶと、消えてしまった。」(以上、大島)
「カワウソに化かされて、一晩中、山中を歩かされた。」
「カワウソが手招きして、風呂を沸かしたから入れというから入ってみると、実はお湯ではなく、枯れ葉だった。」(以上、真穴)
天然記念物に指定され、絶滅が危惧されているカワウソ。生物としての絶滅危惧とともに、身近に伝承されてきたカワウソとの交流話も消えうせる可能性がある。八幡浜地方は愛媛県内でも遅くまでカワウソが生息していた地域として、この種の話も継承していく必要があるのではないだろうか。