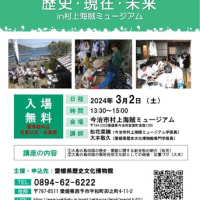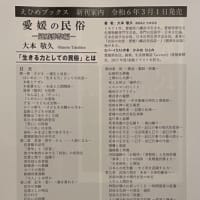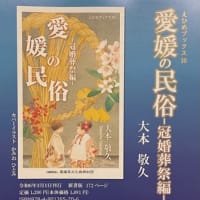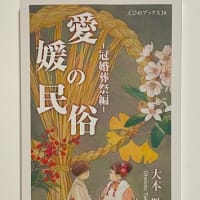生名村には戦国時代に水軍が入島し、帰農したという伝承がのこっている。入島した家のことを地元では「七軒株」と呼んでおり、今回、これについて現地調査を実施した。
これまで生名七軒株については、『伊予水軍関係資料調査報告書』に既に報告されている。その記述内容は次の通りである。
家名・入島年代・系統・屋号・字
久保・天正13・河野氏・久保屋・久保の谷
上村・同上・同上・伊予屋・同上
村上・慶長5、秋・因島村上氏・水地・中の谷
村上・同上・同上・空屋・岡庄
岡本・同上・同上・片平・岡庄
山本・同上・同上・白木屋・中後
大本・同上・同上・こうじゅう屋・尾又
池本・同上・同上・小田本屋・中の谷
このほかに、前田、田尾の二軒が古いが、不明
以上のように紹介されている。
今回聞き取りしたところでは、地元では、村上は水地が総本家であるといわれ、現在で16代目である。この村上(水地)が入島する時に、家臣としてついてきたのが、名字に「本」がつく家(岡本、山本、大本、池本)である。
村上(水地)は、はじめ正福寺の上にある大日堂の近くに居を構え、その周囲に「本」の付く姓の者も住んだといわれる。現在、残っている池本家の墓石には「慶長五年能島村上水軍ノ部将タリシ祖先、此ノ地ニ移住帰農シ代々村役人ヲ勤メタリシ謂フ、屋号ヲ小田本屋ト称ス」とあり、根強い伝承が残っているようだ。
生名村の村上一族が作成した「生名村上氏族勢一覧」によると、「初代、村上次郎太夫、慶長5(1600)年、能島村上武慶ら毛利輝元に従ひて長州萩に移りし時、七家臣と共に生名島に来住し、岡庄の台上(大日堂あり)に居を構え、帰農せり。元和2(1616)八和田八幡宮建立、寛永6(1629)年没」、「水地2代 村上助太夫、慶長5(1600)年、因島村上家11代元充、因島村上の族長として毛利輝元に従ひて萩に移るとき、その一族太夫、幼少にして、因島中庄に居住しあり。生名島次郎太夫嗣子なきため、その養嗣子となる。生名島を支配。大日堂建立 寛文9(1662)、正福寺建立 延宝元年(1673)」と記されており、村上および「本」の付く姓はもともと能島村上氏の系統であり、二代目に因島村上氏から養子をとったようだ。
なお、この村上水軍以外の系統として、河野水軍の系統といわれる久保、上村姓がある。これらは、村上氏が入島する前から居住していたようである。
以上の久保、上村、村上、岡本、池本、大本、山本をもって「生名七軒株」と呼んでいるようだ。
ただし、この七軒株では、年中行事として先祖祭りを行っているかどうか聞き取りしてみたが、それは確認できなかった。
ともあれ、戦国時代の水軍の帰農伝承としては、情報が豊富な事例であり、貴重であるといえるだろう。
2001年03月31日
これまで生名七軒株については、『伊予水軍関係資料調査報告書』に既に報告されている。その記述内容は次の通りである。
家名・入島年代・系統・屋号・字
久保・天正13・河野氏・久保屋・久保の谷
上村・同上・同上・伊予屋・同上
村上・慶長5、秋・因島村上氏・水地・中の谷
村上・同上・同上・空屋・岡庄
岡本・同上・同上・片平・岡庄
山本・同上・同上・白木屋・中後
大本・同上・同上・こうじゅう屋・尾又
池本・同上・同上・小田本屋・中の谷
このほかに、前田、田尾の二軒が古いが、不明
以上のように紹介されている。
今回聞き取りしたところでは、地元では、村上は水地が総本家であるといわれ、現在で16代目である。この村上(水地)が入島する時に、家臣としてついてきたのが、名字に「本」がつく家(岡本、山本、大本、池本)である。
村上(水地)は、はじめ正福寺の上にある大日堂の近くに居を構え、その周囲に「本」の付く姓の者も住んだといわれる。現在、残っている池本家の墓石には「慶長五年能島村上水軍ノ部将タリシ祖先、此ノ地ニ移住帰農シ代々村役人ヲ勤メタリシ謂フ、屋号ヲ小田本屋ト称ス」とあり、根強い伝承が残っているようだ。
生名村の村上一族が作成した「生名村上氏族勢一覧」によると、「初代、村上次郎太夫、慶長5(1600)年、能島村上武慶ら毛利輝元に従ひて長州萩に移りし時、七家臣と共に生名島に来住し、岡庄の台上(大日堂あり)に居を構え、帰農せり。元和2(1616)八和田八幡宮建立、寛永6(1629)年没」、「水地2代 村上助太夫、慶長5(1600)年、因島村上家11代元充、因島村上の族長として毛利輝元に従ひて萩に移るとき、その一族太夫、幼少にして、因島中庄に居住しあり。生名島次郎太夫嗣子なきため、その養嗣子となる。生名島を支配。大日堂建立 寛文9(1662)、正福寺建立 延宝元年(1673)」と記されており、村上および「本」の付く姓はもともと能島村上氏の系統であり、二代目に因島村上氏から養子をとったようだ。
なお、この村上水軍以外の系統として、河野水軍の系統といわれる久保、上村姓がある。これらは、村上氏が入島する前から居住していたようである。
以上の久保、上村、村上、岡本、池本、大本、山本をもって「生名七軒株」と呼んでいるようだ。
ただし、この七軒株では、年中行事として先祖祭りを行っているかどうか聞き取りしてみたが、それは確認できなかった。
ともあれ、戦国時代の水軍の帰農伝承としては、情報が豊富な事例であり、貴重であるといえるだろう。
2001年03月31日