1.明治維新後の西洋模倣と伝統文化切り捨て.
2.第二次世界大戦と終戦直後の飢え.
3.戦後のアメリカ文化の模倣と日本文化切り捨て.
4.80年代バブル期のグルメと、その後の平成不況、家族崩壊.
知るだけでも歴史的にたくさんの要因が重なっている。以前、あるTV番組で「戦後、進駐軍が来たお陰で日本の食の伝統は失われた」と聞いた事があるが、原因を一つに特定できるだけ、単純なものではない。根は多数ある。
しかし、飲まない・食べない人も増えたかもしれないが、みそ汁と納豆、豆腐が残り、世界的に評価された事は明るい材料。それらは大豆加工品だが、イソフラボンという免疫力を高める物質が含まれているから。風邪やインフルエンザにかかった時は、豆腐の味噌汁を飲めば治りも早くなる。TVで放送される子供食堂には、必ず味噌汁も出る。必要なことだし、それを運営する大人たちも味噌汁を飲むわけだから、大人にも広がるはず。その他、玄米や大麦入りのご飯も復活させるといい。夕食用の僕のとっている宅配弁当はなぜか、今は玄米シリーズ。そこに納豆を掛けて食べるとおいしい。1960年代までは大麦も盛んに食べられ、小学時代を思い出しても、僕も食べた記憶がある。でも、その後、大麦もなぜか廃れた。
納豆、味噌、豆腐の発祥は南中国。日本も模倣したが、平和が続いた江戸時代に非常に発達し、みそ汁をだれでも飲むようになり、また、漬物などの発行食は世界一作られるようになり、それらも日本の伝統食になった。カスピ海付近やブルガリアのヨーグルトなど、世界の伝統食は免疫をあげるものばかりだが、戦争があるとかなりが途絶える。途絶えなかったが、第二次世界大戦から終戦直後に「配給された大豆をそのままご飯と一緒に炊いて食べた」例も非常に多く、その後も大豆をそのまま煮て食べる例が家族を通して伝えられていた。大豆は煮たり、焼いても栄養素は全く消化しないわけであるが。とにかく、1940年代の日本の食はデタラメでもあったし、国土が戦場になる国はもっと食の崩壊が起きている。今のウクライナもそれが懸念されるし、食の基礎も「平和」である。
2.第二次世界大戦と終戦直後の飢え.
3.戦後のアメリカ文化の模倣と日本文化切り捨て.
4.80年代バブル期のグルメと、その後の平成不況、家族崩壊.
知るだけでも歴史的にたくさんの要因が重なっている。以前、あるTV番組で「戦後、進駐軍が来たお陰で日本の食の伝統は失われた」と聞いた事があるが、原因を一つに特定できるだけ、単純なものではない。根は多数ある。
しかし、飲まない・食べない人も増えたかもしれないが、みそ汁と納豆、豆腐が残り、世界的に評価された事は明るい材料。それらは大豆加工品だが、イソフラボンという免疫力を高める物質が含まれているから。風邪やインフルエンザにかかった時は、豆腐の味噌汁を飲めば治りも早くなる。TVで放送される子供食堂には、必ず味噌汁も出る。必要なことだし、それを運営する大人たちも味噌汁を飲むわけだから、大人にも広がるはず。その他、玄米や大麦入りのご飯も復活させるといい。夕食用の僕のとっている宅配弁当はなぜか、今は玄米シリーズ。そこに納豆を掛けて食べるとおいしい。1960年代までは大麦も盛んに食べられ、小学時代を思い出しても、僕も食べた記憶がある。でも、その後、大麦もなぜか廃れた。
納豆、味噌、豆腐の発祥は南中国。日本も模倣したが、平和が続いた江戸時代に非常に発達し、みそ汁をだれでも飲むようになり、また、漬物などの発行食は世界一作られるようになり、それらも日本の伝統食になった。カスピ海付近やブルガリアのヨーグルトなど、世界の伝統食は免疫をあげるものばかりだが、戦争があるとかなりが途絶える。途絶えなかったが、第二次世界大戦から終戦直後に「配給された大豆をそのままご飯と一緒に炊いて食べた」例も非常に多く、その後も大豆をそのまま煮て食べる例が家族を通して伝えられていた。大豆は煮たり、焼いても栄養素は全く消化しないわけであるが。とにかく、1940年代の日本の食はデタラメでもあったし、国土が戦場になる国はもっと食の崩壊が起きている。今のウクライナもそれが懸念されるし、食の基礎も「平和」である。










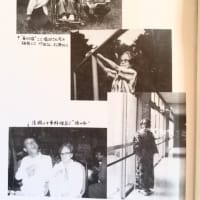

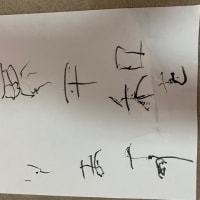



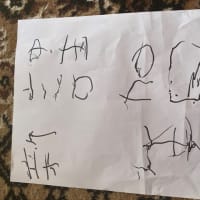
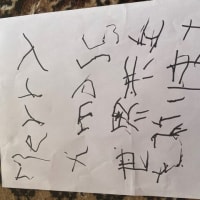

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます