昭和24年、沖縄タイムスの太田良博記者は『鉄の暴風』の取材のため、山城安次郎氏(当時の座間味村助役)に取材している。
太田記者の執筆手法には証言や史料の収集を基本とする新聞記者の姿勢はない。
渡嘉敷島や座間味島での現地取材をしていないことは勿論、取材といえば専ら「米軍」が集めた人々の話が主で、それも発言者の名前を記したメモの類もないという。
新聞記者の太田良博氏が、ドキュメンタリー作品の基本ともいえる当事者への取材もないずさんな記述で『鉄の暴風』を書き上げたのに対して、それを批判する立場で『ある神話の背景』を書いた作家・曽野綾子氏のルポルタージュ的記述手法は極めて対照的であった。
曽野氏は伝聞に頼る太田氏のずさんさんな取材手法を同書の中で次のように指摘している。
<太田氏が辛うじて那覇で《捕えた》証言者は二人であった。一人は、当時の座間味の助役であり現在の沖縄テレビ社長である山城安次郎氏と、南方から復員して島に帰って来ていた宮平栄治氏であった。宮平氏は事件当時、南方にあり、山城氏は同じような集団自決の目撃者ではあったが、それは渡嘉敷島で起こった事件ではなく、隣の座間味という島での体験であった。もちろん、二人とも、渡嘉敷の話は人から詳しく聞いてはいたが、直接の経験者ではなかった>
この部分に関して太田氏は、後に沖縄タイムス紙上の曽野氏との論争で宮平、山城の両氏は辛うじて那覇で《捕えた》証言者ではなく、「(両氏が)沖縄タイムス社に訪ねてきて、私と会い、渡嘉敷島の赤松大尉の暴状について語り、ぜひ、そのことを戦記に載せてくれとたのんだことである。そのとき、はじめて私は『赤松事件』を知った」と反論し、「(両氏は)証言者ではなく情報提供者」とも述べている。
太田氏が宮平、山城の両氏とどのように接触したかはともかく、そのとき山城氏は渡嘉敷島の伝聞情報である「赤松大尉の暴状」について語り、「そのことを戦記に載せてくれ」と頼んでおきながら、何ゆえ自分が体験した座間味島のことを語らなかったのか。それが大きな問題なのである。
戦時中、南方に居たという宮平栄治氏のことは論外としても、山城安次郎氏は太田記者が言う情報提供者の枠を超えた実体験者であり、座間味島の集団自決を証言できる証言者のはずである。
事件を追う事件記者が、飛び込んできた事件の当事者を目前にして、他の事件の情報提供だけを受けて、実体験の事件に関しては何の取材もしなかった。
これは記者としてはいかにも不自然である。
太田氏の言うように、その時、何のメモも取らなかったということも、にわかには信じがたいことである。
■大田良博と沖縄タイムスの関係
このように新聞記者としては不適格にも思える太田氏が何ゆえ沖縄タイムスが社を上げて企画をした『鉄の暴風』の執筆を委ねられたのか。
その謎を解く鍵は太田氏の沖縄タイムス入社直前の職にあった。
太田良博記者の略歴を見ると、『鉄の暴風』の監修者の豊平良顕氏や共著者の牧港篤三氏のような戦前からの新聞記者ではない。
そもそも太田記者と沖縄タイムスとの関係は、沖縄タイムスの月刊誌にエッセイ、詩などを寄稿していたが、昭和24年に発表した『黒ダイヤ』という短編小説で注目を引いた、いわば投稿者と新聞社という関係だったという。
太田氏が戦後米民政府に勤務しているとき、沖縄タイムスの豊平良顕氏に呼ばれ、企画中の『鉄の暴風』の執筆を始めたことになっている。
米軍政府が沖縄の統治権を米民政府に移管するのは太田氏が沖縄タイムスに職を変えた後の昭和24年の12月15日以降になっている。
『鉄の暴風』の執筆時に米軍側と沖縄タイムスそして太田氏の間に「共通の思惑」があったと考えても不思議ではないだろう。
曽野氏は『ある神話の背景』の取材で太田氏に会ったとき、米軍と『鉄の暴風』の関係について、同書の中で次のように述べている。
≪太田氏は、この戦記について、まことに玄人らしい分析を試みている。 太田氏によれば、この戦記は当時の空気を反映しているという。 当時の社会事情は、アメリカ軍をヒューマニスティックに扱い、日本軍閥の旧悪をあばくという空気が濃厚であった。太田氏は、それを私情をまじえずに書き留める側にあった。「述べて作らず」である。とすれば、当時のそのような空気を、そっくりその儘、記録することもまた、筆者としての当然の義務の一つであったと思われる。
「時代が違うと見方が違う」
と太田氏はいう。 最近沖縄県史の編纂をしている資料編纂所あたりでは、又見方がちがうという。 違うのはまちがいなのか自然なのか。≫
驚いたことに太田氏は『鉄の暴風』を執筆したとき、その頃の米軍の思惑を執筆に反映させて「アメリカ軍をヒューマニスティックに扱い、日本軍閥の旧悪をあばく」といった論旨で同書を書いたと正直に吐露していたのである。
このとき太田氏は後年曽野氏と論争することになるとは夢にも思わず、『鉄の暴風』を書いた本音をつい洩らしてしまったのだろう。
この時点で曽野氏は太田氏が記者としては素人であることを先刻見抜いていながら、「玄人らしい分析」と「褒め殺し」をして『鉄の暴風』の本質を語らしめたのであろうか。
曽野氏は、後年の太田氏との論争で,「新聞社が伝聞証拠を採用するはずがない」と反論する太田氏のことを「いやしくもジャーナリズムにかかわる人が、新聞は間違えないものだとなどという、素人のたわごとのようなことを言うべきではない」と「玄人」から一変して、今度は、「素人」だと一刀両断している。
◇
以下引用の太田記者の「伝聞取材」という批判に対する反論は、「はずがない」の連発と、「でたらめではない」とか「不まじめではない」とまるで記者とも思えない弁解の羅列。
これでは曽野氏に「素人のたわごと」と一刀両断されるのも仕方のないことである。
「沖縄戦に“神話”はない」(太田良博・沖縄タイムス)」連載4回目
<体験者の証言記録
『鉄の暴風」の渡嘉敷島に関する記録が、伝聞証拠によるものでないことは、その文章をよく読めばわかることである。
直接体験者でないものが、あんなにくわしく事実を知っていたはずもなければ、直接体験者でもないものが、直接体験者をさしおいて、そのような重要な事件の証言を、新聞社に対して買って出るはずがないし、記録者である私も、直接体験者でないものの言葉を「証言」として採用するほどでたらめではなかった。永久に残る戦記として新聞社が真剣にとり組んでいた事業に、私(『鉄の暴風』には「伊佐」としてある)は、そんな不まじめな態度でのぞんだのではなかった。 >
「「沖縄戦」から未来へ向ってー太田良博氏へのお答え(3)」
(曽野綾子氏の太田良博氏への反論、沖縄タイムス 昭和60年5月2日から五回掲載)
<ジャーナリストか
太田氏のジャーナリズムに対する態度には、私などには想像もできない甘さがある。
太田氏は連載の第三回目で、「新聞社が責任をもって証言者を集める以上、直接体験者でない者の伝聞証拠などを採用するはずがない」と書いている。
もしこの文章が、家庭の主婦の書いたものであったら、私は許すであろう。しかし太田氏はジャーナリズムの出身ではないか。そして日本人として、ベトナム戦争、中国報道にいささかでも関心を持ち続けていれば、新聞社の集めた「直接体験者の証言」なるものの中にはどれほど不正確なものがあったかをつい昨日のことのように思いだせるはずだ、また、極く最近では、朝日新聞社が中国大陸で日本軍が毒ガスを使った証拠写真だ、というものを掲載したが、それは直接体験者の売り込みだという触れ込みだったにもかかわらず、おおかたの戦争体験者はその写真を一目見ただけで、こんなに高く立ち上る煙が毒ガスであるわけがなく、こんなに開けた地形でしかもこちらがこれから渡河して攻撃する場合に前方に毒ガスなど使うわけがない、と言った。そして間もなく朝日自身がこれは間違いだったということを承認した例がある。いやしくもジャーナリズムにかかわる人が、新聞は間違えないものだとなどという、素人のたわごとのようなことを言うべきではない。 >
太田 良博
本名、伊佐良博。1918年、沖縄県那覇市に生まれる。早大中退。沖縄民政府、沖縄タイムス、琉球放送局、琉球大学図書館、琉球新報などに勤務。その間詩、小説、随筆、評論など発表。2002年死去

 ⇒最初にクリックお願いします
⇒最初にクリックお願いします











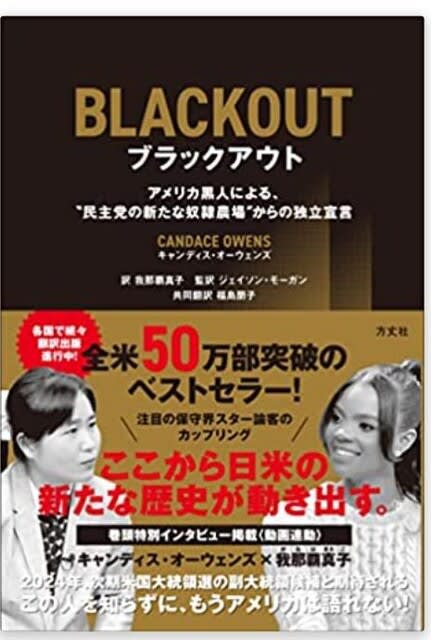

.jpg)
.jpg)






