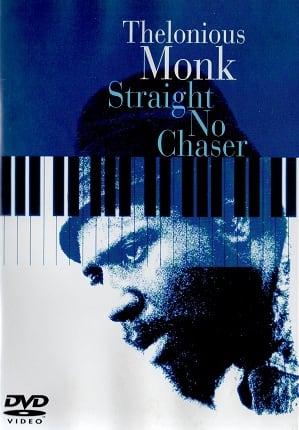(1)より続く
■ 桜井国俊 (沖縄大学長) 「辺野古移設問題―特に環境の視点から」
私としては、普天間や辺野古が大手メディアの大きな話題となって以来、ジュゴンを含め、環境影響に関する報道がぴたりと無くなってしまったことが不可解であり、この講演に期待した。桜井氏は、沖縄への「アメとムチ」政策が誤りで失敗に終わっていること、そして環境アセスの問題点を指摘した。

講演の要旨は以下の通り。
○今朝の沖縄2紙には、「普天間2案、最終調整」とある。キャンプ・シュワブ陸上案と、勝連半島沖合案(ホワイトビーチ)だ。両方とも過去に出たことのある案だ。3月29日のG8外相会議を控え、岡田外相はゲーツ国防長官・クリントン国務長官と調整に入るのだろう。
○2案はそれぞれ沖縄出身の代議士(下地議員)と沖縄の経済界から出された案であり、このことは鳩山政権にとって都合が良いはずだ。しかし、先が見えない泥沼であり、アセスにも時間がかかり迷走するだろう。
○基地負担を負わせるために、沖縄にあらゆるアメが与えられてきた。95年の米兵少女暴行事件およびその後の米軍再編計画以降、15年間アメとして辺野古に600億円以上がつぎ込まれた。その結果、ハコ物はできたが維持のための借金がかさみ、雇用は低迷したままだ。われわれの未来はこのような形ではないし、沖縄に負担を押し付けるのはもはや不可能だ。
○それでも安保が必要と判断されるなら、本土でやってくれ、というのが沖縄のメッセージだろう。
○施政権返還後、表面化しただけでも5,500件の米兵による事件が起きている。そのうち550件は凶悪犯罪だ。
○先日のひき逃げ事件も、女性兵士が吐くほど泥酔し、軍の車を勝手に持ち出したものだとされた。私服ゆえ、警察は軍だと気が付かなかった。
○本土の平和は、憲法9条、安保、沖縄の3つの条件により成り立っている。そして、沖縄は米軍の侵略戦争に加担させられてきた。
○海兵隊の抑止力とは神話にすぎない。有事の際に海兵隊を運ぶとしても、佐世保から揚陸艦が来ないと意味がない。すなわち、沖縄に駐留することの意味はない。
○キャンプ・シュワブ陸上案の場合、人々の真上を危険なオスプレイが飛ぶことになるだろう(2000年時点で、15機のうち4機が墜落した)。辺野古V字案より生活と生命を侵害するものだ。また、赤土が流出し、大浦湾の生態系に大きな影響を与えるだろう。
○大浦湾は、ラッパ状に切れ込んでおり、サンゴ礁、海草、マングローブなど多様な生態系が存在する。それぞれの場所に、それぞれの生き物が自らの場所を見つけている。アオサンゴは石垣島・白保のそれに匹敵する。
○辺野古沖の海草は多く、ジュゴンの目撃も多い。しかし、防衛省の調査では、嘉陽では観察されても、辺野古沖では観察されていない。これは、キャンプ・シュワブの米軍の上陸演習による撹乱、そして調査自体による撹乱が考えられる。
○辺野古のアセスの間、オスプレイ配備のことが隠され続けていた。「方法書」、「準備書」を経て、ようやく2009年8月に明らかになった。
○これが日本のアセス法の大きな欠陥であり、日本政府が基地をつくることの調査は行ったとしても、米軍が基地をつかうことに関しては対象外となってしまう。そのために、情報開示を要求しても、「米軍から聞いていない」という回答がまかり通ってしまう。昨日(3/19)、アセス法の改定案が閣議決定されたが、その欠陥には触れられていない。
○世界遺産の候補ともなりうるやんばるの森でも、東村高江にヘリパッドが増設されそうになっており、やはりオスプレイが想定されている。住民の水瓶となるダムがある場所でもあり、極めて異常なことだ。また、国は、反対する住民を司法という手段で排除する前代未聞の行動に出ている。
○辺野古のアセスはアセスではない。オスプレイ想定の飛行機について、「方法書」ではたった1行しか書かれていなかった。このような「後だしジャンケン」があってはアセス法が成り立たない。実際に28条で「後だし」を禁止しているが、それが問われることはなかった。閣議決定された改定案でも、28条問題は放置されている。
○このままアセスの問題を放置することは、やがて日本国民全体の問題となることだろう。
(つづく)
※各氏の発言については、当方の解釈に基づき記載しております。