アイルランド・ダブリンの低所得者層の住む界隈には、よどんだ目をした子供達が、怪しげな売人から薬を買っていた。注射器は散乱し、麻薬にからんだ犯罪は後を経たず、麻薬中毒で命を落とす子供も少なくなかった。しかし、政府は麻薬の取り締まりに本腰を入れず、どんどんと泥沼にはまっていた。
サンデー・インデペンデント紙の記者であるヴェロニカは、その惨状を何とかして伝え、子供達を助けたいとの一心から、麻薬売買の大物、ジョン・ギリガンに迫ろうとしていた。しかし、それは命がけの仕事。母であり、妻であるジャーナリストのヴェロニカは女であるという心の弱みを絶対に見せずに、巨悪に立ち向かっていた。
人間は、どうしてこんなことができるのかと思うほど残酷な生き物だと、哀しいながらいつも思う。戦争、リンチ、虐待、いじめ、殺人。どんな行為も、ちょっと自分がされてみろと思うのだが、麻薬を売る行為ほど、自分は直接手を下してない、と思える犯罪はない。売人は薬を売るだけ。それも買う方は、もしかしたら感謝して買ったりもする。「俺は薬を売るだけ。打つかどうかまで責任なんか負ってねえよ」などと思える犯罪だ。目の前で人が死ぬわけじゃない。自分が直接手を下したわけではない。しかし、これほどひどいことがあろうか。死よりもひどい苦しみを味わい、犯罪に走り、心も体もぼろぼろになる。そして、犯罪者には自覚がものすごく少ない。ひどすぎる。
麻薬を売るなどという極悪人だから、自分の利権を守るためにはなんでもする。ヴェロニカはそれを身を持って暴露しようとして、結局は命を落としたわけだが、私がこの映画を見て一番感じたのは政府の怠慢だ。死んでからじゃ遅すぎるのに、いつもそう。政府のやることなど起こってからじゃ遅いのに、いつも後手後手だ。命を落とさなきゃわかんないのか。犠牲にならなければ本腰をあげないのか。アイルランドでは、いろいろな問題が山積し、すべてを網羅するのは難しい、というのはいいわけだ。
ヴェロニカの死によって世界は変わった、というが、ヴェロニカは本当に悔しかったと思う。いくら自分の死によって世界は変わった、政府の対応は変わったといっても、それは死によってだ。彼女が言わんとした記事によって、取材によって直接動いたのではない。いや、その動きがあったからこそ、事件が起こり、結果として政府が動いたのかもしれないが、どこかに彼女の無念さが感じ取られてならなかった。
私は女性であることに何の引け目もないが、女性であるというだけでたくさんの悔しさや恐怖や損も味わってきた。ヴェロニカの一つ一つの表情や、行動にもそれが表されていた。しかし、その恐怖感を絶対に他人に見せない。そう偽って生きていくだけで、人生は変わる。彼女に人生にはそれが見えた。それを自然に、かつ力強く感じさせたのは、相変わらずのブランシェットの名演だったが、今回の映画で目を引いたのは、ヴェロニカの夫、母、ギリガン、記者仲間役などの脇役たち。ほとんど知らない俳優さん達だったが、意気込みと迫力が違った。さすがシューマッカー。配役がうまい。ブラッカイマーも、妙な歴史大作なんか撮らせないで、いい素材探して、思いっきり監督に撮らせるといい作品ができると思うんですけどね。
『ヴェロニカ・ゲリン』
原題「Veronica Guerin」
監督 ジョエル・シュマッカー 製作 ジェリー・ブラッカイマー
出演 ケイト・ブランシェット ブレンダ・フリッカー ジェラルド・マクソーレイ 2003年 アメリカ作品
サンデー・インデペンデント紙の記者であるヴェロニカは、その惨状を何とかして伝え、子供達を助けたいとの一心から、麻薬売買の大物、ジョン・ギリガンに迫ろうとしていた。しかし、それは命がけの仕事。母であり、妻であるジャーナリストのヴェロニカは女であるという心の弱みを絶対に見せずに、巨悪に立ち向かっていた。
人間は、どうしてこんなことができるのかと思うほど残酷な生き物だと、哀しいながらいつも思う。戦争、リンチ、虐待、いじめ、殺人。どんな行為も、ちょっと自分がされてみろと思うのだが、麻薬を売る行為ほど、自分は直接手を下してない、と思える犯罪はない。売人は薬を売るだけ。それも買う方は、もしかしたら感謝して買ったりもする。「俺は薬を売るだけ。打つかどうかまで責任なんか負ってねえよ」などと思える犯罪だ。目の前で人が死ぬわけじゃない。自分が直接手を下したわけではない。しかし、これほどひどいことがあろうか。死よりもひどい苦しみを味わい、犯罪に走り、心も体もぼろぼろになる。そして、犯罪者には自覚がものすごく少ない。ひどすぎる。
麻薬を売るなどという極悪人だから、自分の利権を守るためにはなんでもする。ヴェロニカはそれを身を持って暴露しようとして、結局は命を落としたわけだが、私がこの映画を見て一番感じたのは政府の怠慢だ。死んでからじゃ遅すぎるのに、いつもそう。政府のやることなど起こってからじゃ遅いのに、いつも後手後手だ。命を落とさなきゃわかんないのか。犠牲にならなければ本腰をあげないのか。アイルランドでは、いろいろな問題が山積し、すべてを網羅するのは難しい、というのはいいわけだ。
ヴェロニカの死によって世界は変わった、というが、ヴェロニカは本当に悔しかったと思う。いくら自分の死によって世界は変わった、政府の対応は変わったといっても、それは死によってだ。彼女が言わんとした記事によって、取材によって直接動いたのではない。いや、その動きがあったからこそ、事件が起こり、結果として政府が動いたのかもしれないが、どこかに彼女の無念さが感じ取られてならなかった。
私は女性であることに何の引け目もないが、女性であるというだけでたくさんの悔しさや恐怖や損も味わってきた。ヴェロニカの一つ一つの表情や、行動にもそれが表されていた。しかし、その恐怖感を絶対に他人に見せない。そう偽って生きていくだけで、人生は変わる。彼女に人生にはそれが見えた。それを自然に、かつ力強く感じさせたのは、相変わらずのブランシェットの名演だったが、今回の映画で目を引いたのは、ヴェロニカの夫、母、ギリガン、記者仲間役などの脇役たち。ほとんど知らない俳優さん達だったが、意気込みと迫力が違った。さすがシューマッカー。配役がうまい。ブラッカイマーも、妙な歴史大作なんか撮らせないで、いい素材探して、思いっきり監督に撮らせるといい作品ができると思うんですけどね。
『ヴェロニカ・ゲリン』
原題「Veronica Guerin」
監督 ジョエル・シュマッカー 製作 ジェリー・ブラッカイマー
出演 ケイト・ブランシェット ブレンダ・フリッカー ジェラルド・マクソーレイ 2003年 アメリカ作品










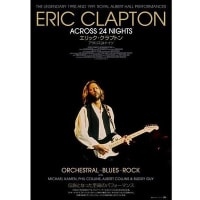









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます