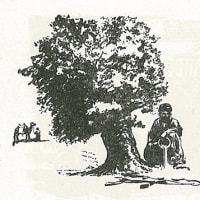作家の半藤一利さん(以下、「氏」)は、昭和史を中心に、本格的著作、エッセイを数多く世に送り出してこられました。常々愛読していたこともあり、当ブログでも何度か取り上げてきました(文末に直近の記事へのリンクを貼っています)。今回のネタ元は、「歴史のくずかご」(文春文庫)です。氏が文藝春秋社の編集者当時に、業界向け月刊パンフレットに連載(1999~2014年)していたコラムを編集したものです。「くずかご」と謙遜されていますが、コンパクトで、痛快な歴史小噺が満載です。私なりに選んだ3つのエピソードをお届けします。どうぞ最後までお付き合いください・
★デマのスピード★
昭和13年、日中戦争は泥沼化し、国民は戦争に倦み始め、法律で禁じられているはずの流言飛語(デマ)が飛び交うようになっていました。その年の暮れのある日、参謀本部の部員のひとりが、民間の友人にチラリとこんな話をしました。
「戦時下の国民の士気に関することなので、春場所が始まるまで伏せているが、実は双葉山が昨日死んだんだ」(本書から)

もちろんウソ。でも、泣く子も黙る参謀本部が出処で、連勝街道爆進中の双葉山に関する情報です。信じるな、という方が無理。実は参謀本部が仕掛けたデマだったのです。国内外の陸軍部隊に指令しました。24時間内にこの噂話が入ったら、ただちに報告せよ、と。
結果は驚くべきものでした。一番遠くは、満州の北部、ソ連国境に近い黒河の司令部からの報告だったのです。悪事ならぬデマが、ほぼ口コミだけで千里を走ることが実証され、参謀本部もギクッとなったといいます。今や、真偽取り交ぜ様々な情報がネット上で飛び交う時代。くれぐれもデマ、怪しい話には騙されないよう心がけたいものです。
★ネーミングは難しい★
氏は、「文藝春秋」の昭和6(1931)年6月号から「奇姓珍名物語」という記事を引いています。それによりますと・・・
奈良県矢田村には、「沢井麿鬼久寿老八重千代子」さんがいたり、栃木県藤原村には、「十二月(姓)甲乙丙丁戊己庚申壬癸之助」氏がおり、姫路連隊に、「野田(姓)江川富士一二三四五日左衛門助太郎」殿がいたりする、というのです。昔のキラキラ(ギラギラ?)ネームといったところでしょうか。だいぶ前のことですが、「悪魔」という名前で出生届けをしようとしたところ、受付を拒否されたという「事件」にも触れています。(随分話題になりましたから、私も覚えています。確か「亜駆」で決着したはず。読みは「あく」ですが、亜(あ)、区(く)、馬(ま)の3文字を入れ込むという奇策を弄した智慧者がいたのですね。)
ことほど名付けは難しいもの。氏は、国文学者にして、平家物語の権威である長野嘗一先生の例を持ち出しています。源平時代にゾッコンですから、長男が生まれたら八幡太郎義家にちなんで「太郎義宗」、次男は熊谷次郎直実にちなむなど、以下五男まで歴史上の人物にちなむ名前を用意していました。でも、奥様は猛反対。結論が出ないまま、「長野太郎義宗」君の誕生かと思いきや、生まれてきたのはなんと女の子。「長野先生、しばし天を仰いで声もなかったという。」(同前)
★「山の神」の創作者★
1910年10月18日、文豪トルストイは意を決して家出をしました。時に82歳。その原因をめぐって、作家・正宗白鳥と評論家・小林秀雄との論争を、氏は再読します。「妻君のヒステリーを怖がって逃げたのだ」と白鳥。「それがきっかけかも知れないが、思想との闘いの果て」と反駁する小林。そんな主張を読みながら、氏はふと、妻のことを冗談っぽく「山の神」と呼ぶいわれを知りたくなったのです。調べたところ、これを一番最初に使ったのは、「忠臣蔵」の山鹿流陣太鼓で知られる山鹿素行だとわかりました。吉原でドンチャン騒ぎの誘いが悪友からあった時、「「今日は山の上(かみ)がいるからあかん」と返書したのが本邦初らしい」(同前)
当時、妻君のことを上流の家庭では「奥」と呼んでいました。ここで、いろは歌の登場です。「うゐのおくやまけふこえて」で、「やま」の上にあるのが「おく」です。「奥」=「山の上(かみ)」から「山の神」になったというのです。
ついでに、氏はこんな笑い話を紹介しています。商家で下働きをしていた「お若さん」なる女性。祝いの席で思わず「ぷう」とやったため、店をクビになりました。出て行く時、一首詠みました。
「いろはにほとの間(あい)でしくぢって 私やこの家をちりぬるおわか」旦那はその頓才にびっくりし、元通り働いてもらうことになったそうな。めでたし、めでたし?
お楽しみいただけましたか?冒頭でご紹介した記事へのリンクは、<第617回 超人ー司馬さんと清張さん>です。あわせてご覧いただければ幸いです。なお、もう少しご紹介したいネタがありますので、いずれ続編をお届けする予定です。それでは次回をお楽しみに。