薩長公英陰謀論者さんから、歴史に関する仮説の問題、また歴史認識に関する非専門家の役割について、長大な論文をいただきました。コメント欄にとどめておくのはもったいないので、そのまま新記事として転載させていただきます。比叡山焼き討ち事件を例にとって、この問題を掘り下げて下さっています。
*****以下、薩長公英陰謀論者さんのコメントの枢要部分を転載*******
転載元の記事は以下
http://blog.goo.ne.jp/reforestation/e/dc79258fffc940d937834114e0c550a2
歴史における仮説の問題について「(1)歴史的事実それ自体」についての仮説(「新史実=真実」の発見)と「(2)歴史的事実の認識」にかかわる仮説とに区分して考えてみました。
しかし「歴史学」における決定的な困難は(1)が(2)に吸収されていることです。歴史学においておそらく最も重視されるソースであろう当事者および目撃者の「証言・叙述」は、その人の認識の言語による表現であって事実それ自体ではありませんし、事実のごく一部を反映したものであろうと思います。まして、このソースを対象とした研究が乗数効果で事実から離れることは当然のことです。
とりわけ21世紀になってから(そのように意識して見るようになったためでしょうか。最近とくに極端になったような気がしますが)報道の記事・テロップ・ナレーションのみならず画像や映像が事実・真相の追求のためのものではなく「権威側からの特定の認識の流布」となっていることを痛感するようになりました。これらを主たる一次史料とするであろう将来の歴史学的記述が現在の時代をどう描き出すかを想像すると、翻って、現在までの歴史叙述についても絶望感を抱いてしまいます。
おそらく「理系」における仮説は、原理や法則、またその現れ方に関するものであり、事象をその仮説によっていかに理論的に説明することができるか、また、事象の再現において、つまり実験や観察・観測によって、その仮説の有効性を検証することができるかということが問題になるのではないだろうかと思います。さらにまたその仮説を理論として応用したり、より大きな領域に適合するものに発展させることができるか、ということが重要になるのだろうと推察します。
しかし、科学を自称する経済学はともかく(自己の理論が仮説であり検証されるべきものであることを認めない経済学を関良基先生はカルトとお呼びになっているのではないかと思います)自然史は措くとして少なくとも人間社会の歴史、つまり社会の変化は、不可逆であることは当然として(誰かのようにこれを認めないこともカルトですね)自然現象におけるような再現性がまったくないものだと思います(「自然=宇宙」の歴史は再現性はないものなのかもしれませんが)。
ただし、歴史における「原理や法則」として、かっては史的唯物論による「生産力と生産関係の変化としての社会発展」史観が大きな影響力を持ち、またそれに代わって現代の支配的理念となっている「自由主義・民主主義・グローバリズムへの改革原理」というものがあります。後者は「歴史の終わり」というように、歴史不在というよりむしろ歴史を否定する特質・思考方法を持っていますが、両方とも普遍性・再現性・原理的永遠性を謳っているわけで、そのような決定論は歴史学における仮説の存在を許さないものだと思えます。
つまり歴史学における仮説は再現性をめぐって両翼から挟み撃ちにあっているわけです。そこで、歴史学における仮説とは何であり、またどのように形成され、また検証されうるのかと、途方に暮れました。が、かの「長州史観」や「司馬史観」のように歴史認識をカルト化させないために、歴史における事実と認識との関係、またこの双方における仮説と検証について非力ながら考えざるを得ませんでした。
この間に、以下の「比叡山焼討ち」問題に目を惹かれて触発されたことから、歴史における仮説ならびに専門家と非専門家の違いについて考えた「仮説的結論」を、早とちりではあれ、まず記しますと:
01 「(1)歴史的事実それ自体」については、仮説の設定(「新史実=真実」の発見)とその検証を含めて非専門家には手におえるものではない。
02 「(2)歴史的事実の認識」については、非専門家にとって現在における同時代的連関を意識した仮説の設定のみが可能である。
03 「(2)歴史的事実の認識」に関する専門家の検討・検証は、同時代的問題意識や同時代の感覚による人間観・社会観が直接影響しないように、対象となる当時の一次史料に厳格に準拠して行われる。
04 「(2)歴史的事実の認識」に関する非専門家による仮説は、同時代における「生きるスタンス」つまり将来に関する問題意識にリンクするために、歴史専門家の手による検証・検討・批判にはなじまない。
ということになるかと思います。
推察しますに歴史専門家の目は、その歴史家の生活のあり方、それに大きな影響を及ぼした事件、その中で形成された人間と社会に対する洞察を基礎としていると思います。アカデミックな訓練を受け教育・研究機関の中で一貫して生活する専門家と、それとはまったく異なる生活・社会体験を持つ非専門家との相違は、理系の仮説設定とその検証において可能である専門家と非専門家の連携を挫くものであろうと思います。
この困難を克服するには、アカデミックな歴史専門家のサイドで、同時代的問題意識を明確に掲げ、将来を見出そうと見つめる目でそのまま現在と「歴史」を見るということが可能でなければならないと思えます。
そのようなことがアカデミズムと歴史「業界」の中の歴史専門家にありうることなのか、門前の小僧にもなることができない素人には推し量ることができません。
なお上述の仮説は、下述の「比叡山焼討ち」問題に加えて、キューバ大使、ウクライナ大使を経験されて防衛大学教授となった馬渕睦夫という方に対する、ウクライナ問題への関心から見ましたインタビューの後記にあった、同氏の次のような言葉に深く強く触発されたことにもとづいています。
http://chizai-tank.com/interview/interview201405.htm
「私は特別な情報ソースを持っているわけではありません。寧ろ特別な情報ソースを持っているという人は、反対にそのソースから操られている可能性も高いものです。だから我々は、まず今起こっていることを自分で考え、過去に起ったことを実体験と結び付け、公開情報をもとに自らの世界観で解釈していくことが大切、そうすれば隠されている本当に重要な事も見えてきます」
さて、「(2)歴史的事実の認識」にリンクした「(1)歴史的事実それ自体」について挑戦をした興味深い例があります。織田信長による比叡山焼き討ち事件に関する兼康保明氏の報告です。
兼康氏は1949年生まれで大学の史学科を卒業後、滋賀県教育委員会に所属して遺跡調査を専門となさった方で、比叡山延暦寺の史跡地内での発掘調査に直接携わっておられます。氏の報告は「織田信長比叡山焼き討ちの考古学的検討」(『滋賀考古学論叢第1集』、滋賀考古学論叢刊行会、1981年)にまとめられているとのことですが、私にはアクセスを含めて手におえないと思われますので、この論文をもとにして兼康氏が書かれた「比叡山焼き討ちの真相」(兼坂保明『考古学推理帖』大巧社、1996年;p130~142)から抜粋引用しつつ弊見を付してみます。
> ・・・東塔で現在まで約二〇カ所ほどの堂、坊跡を調査しているが、遺構や遺物から元亀の焼き討ちを証明できるのは、根本中堂と大講堂の二カ所だけである。・・・西塔も・・・常行堂の北部で伴出遺物から元亀の焼討ちの焼土層ではないかと考えられるものが発見されているだけで、他の場所で発掘された遺構や遺物は、室町時代以前のものと江戸時代のものばかりである。
<弊見> 平安貴族仏教のメッカであり、また禅宗や浄土宗の母ともなった比叡山延暦寺の権威の象徴であった根本中堂と大講堂だけを焼くだけで十分であり、しかもそれはきわめて容易なこと、しかし、その政治的・心理戦略的効果は絶大だったと。
比叡山各所の発掘調査は比叡山縦走ドライブウェイの建設という全山調査に絶好の機会を含め、建物の建て替えや修理にあたって繰り返し行われ、発掘調査において「元亀の比叡山焼き討ち」は一貫して強い関心の対象であったと調査に参加した兼康氏は証言しています。
「なかった」ということを物証的に確認するのは容易ではないと思いますが、文献資料にあたりながら発掘調査を実地に行った専門家の兼康保明氏の仕事から、語り継がれた「比叡全山炎上大虐殺」がフィクションであるのは明らかではないでしょうか。
> ・・・三塔各所の発掘調査の結果から結論づけるなら、元亀二年の織田信長による延暦寺焼討ちのさい、比叡山に所在した堂舎の数は少なく、また16世紀代の遺物の少ないことから『多聞院日記』などにみられるように、僧衆の多くは坂本に降り、生活の場もすでに山を離れていたと考えざるをえないのである。つまり、山上においては、全山数百の諸堂が紅蓮の炎に包まれ、大殺戮がくりひろげられたとするイメージを生み出すのとはうって変わった、閑散たる光景しか存在しなかったのが現実である。このことは、山上の放火、掃討がわずか二~三日ときわめて短期間であったことからもうかがえよう。
<弊見> 先のコメントで先回りしてしまいましたが、「比叡山全山炎上と炎の中での数千人の虐殺」は、延暦寺に体現された貴族的天台宗から浄土宗系の庶民仏教、すなわち「旧体制支配者側」の政治文化と、同時に「反体制民衆側」の精神的支柱を一挙に否定し葬り去るための「神話の創出」であったということになります。
> ・・・信長の右筆、太田牛一が自らの見聞をもとに記したとしてよく引用される『信長公記』の「叡山御退治の事」をよく注意して読むと、比叡山上をも攻めてはいるが具体的な戦いの様子は、実は山麓にある坂本のできごとである。有名な虐殺については・・・坂本の日吉社の神体山で標高380メートルほどの八王子山でのできごとで、峻険な比叡山上の・・・山腹にある諸堂でのできごとではない。
<弊見> 兼康保明氏は、信長の事績についての基準的文献とされている『信長公記』の該当箇所が意図的に比叡山上と山麓の坂本での出来事を混同させるように書かれていることを、発掘調査にもとづいて指摘しています。
比叡山焼き討ちのイメージ形成において『信長公記』よりむしろ決定的な役割を果たしたと思われる『言継卿記』の元亀二年九月一二日の伝聞体の叙述を見てみます。小和田哲男著『歴史ドラマと時代考証』(中経出版、2010年・中経文庫、2012年)の電子版から抜粋転載しますと:
>> ・・・織田弾正忠、暁天より上坂本を破られ火を放つ。次いで日吉社残さず、山上東塔、西塔、無童子(寺)残さず火を放つ。山衆悉く討死と云々。・・・講堂以下諸堂に火を放ち、僧俗男女三四千人を伐り捨て、堅田等に火を放つ。・・・大講堂、中堂、谷々伽藍一宇も残さず火を放つと云々。
と、あるとのことです。山麓にある坂本の里坊と日吉大社、さらに北東にJRで二駅離れた琵琶湖岸の港町堅田と、標高800mを越える比叡山全域が境内の延暦寺とをすっかり一体にしながら(西塔下のケーブルカーの駅は標高654m、山麓の駅との高低差は484mだとか)、強いイメージを畳みかけ重ねて、伝聞「云々」を多用しつつ、3~4千人もの虐殺をともなう全面焼き討ちが比叡山上の延暦寺において行われたように印象づけられています。
> 信長の真のねらいは、弱体化しながらも伝統的な権威を保持していた延暦寺を攻めることによって、労せずして天下に自らの力を誇示することにあったのである。今日われわれが抱いている焼討ちのイメージは、四百年前に信長が考えた戦略的効果のなかに、時を越えてなお呪縛されていたのである。
<兼康保明氏引用と弊見以上>
当然に抱く「なぜ当事者の一方である比叡山延暦寺側の記録証言がまったくないのか」ということが疑問なまま、比叡山延暦寺のサイト「歴史」のところを見ましたら「織田信長によって比叡山は全山焼き討ちされ、堂塔伽藍はことごとく灰燼に帰しました」とあって、天井を仰ぎました。
Wikipedia「比叡山焼き討ち」を見ますと、最初の概要部分に「なお一方、近年の発掘調査から、施設の多くはこれ以前に廃絶していた可能性が指摘されている」という一文が挿入されています。紀伊國屋書店(新宿本店ではありません)で、比叡山焼き討ちを取り上げている歴史関係の本を見てゆきましたところ、三分の一くらいが兼康氏の発見を認識して叙述に取り入れているように思われました。
氏の「比叡山焼き討ち」検証が知られるようになったのは1980年代以降であると思われますが、現在になってようやく兼康氏の発見が定着し始めているように思えます。
ともあれ、織田信長が「革命の寵児」として徹底的な近代的合理主義者、既成権威=アンシャン・レジームの破壊者であることを謳うには「比叡山焼討ち」は最高の演出です。そのようなイメージで信長が注目されたのは戦後のことで、とりわけ例によって司馬遼太郎が、『国盗り物語』で描いた信長像が決定的と言えるインパクトを持ったと思われます。司馬遼太郎は、信長と、そして坂本龍馬を「時代に先駆けた悲劇の革命児」に謳いあげたわけです。
先の引用の最後にある兼康保明氏の結論的コメントにうなづきながら、幾日かあとになって肩をおとしました。まさに専門家でしかできない「(1)歴史的事実それ自体」の発見、しかも史料文献を現場の発掘結果によって吟味検証したもので、文献学によらないものであるという意味で特異と言える成果が、おそらく当時(1960年代から70年代)の日本史学の発展段階に制約されて、当時の「国家統一をめざした最強の革命児」としての信長の像に取り込まれていると気がついたからです。
歴史専門家の兼康保明氏は発掘を武器とする歴史専門家ならではの「(1)歴史的事実それ自体」の発見を果敢に行いながら、「(2)歴史的事実の認識」においては、司馬遼太郎が商品化した既定の信長像を裏書きすることになっています。近年の研究の発展によって「宗教的権威の破壊者でもあった近代的合理主義者、国家統一をめざした革命児」という信長像は(戦後につくられたイメージであって)信長の実像とは異なるものであることが明らかにされているようです。兼康保明氏が信長神話を見破る物証をつかみながら、手の上に乗った物証を地に落としてその音を聴くことができなかったのはなぜだろうかと考えてしまいます。
http://www4.plala.or.jp/kawa-k/kyoukasyo/3-4.htm
「信長は『旧体制』の再編強化を図ったー『旧体制』の破壊者という信長像の誤り」という記事に、2000年前後の信長研究の成果がまとめられており、大変参考になりました。ただし内容はこのタイトルそのままではないように思えます。機会をあらためて突っ込んで考えて(「倒幕維新」を対比して考えるために)報告することができればよいのですが。
前述の勝手な仮説01~04のようにひとりですくんでしまっていますが、さらに考えますに次のような仮説を立てることができるかもしれないと思っております。
05 アカデミックな歴史学(日本史学)はあらたな発展段階にあり、徐々に時代にキャッチアップしてゆきはじめる段階にある。
06 時代そのものが深く混迷・閉塞しているなかで時代の先に出ることができるかどうかが歴史学の躓きの石になると思われる。
07 それゆえにこそ、時代の先に出ようとする、あるいは、近代的な見方(その裏返しに思える「ポスト・モダン」系思考を含めて)の先に出ようとする歴史研究者が存在する、あるいは現れるのではないだろうか。
成田龍一著『近現代日本史と歴史学』(中公新書、2012年)によれば、日本史研究は1980年前後から氏が戦後第3期に区分するあらたな段階に入ったとされています(同書p3~p14)。成田龍一氏の言う第3期、その終わりであろう21世紀に入ってから、少なくとも近世から近代を対象とする日本史研究はさらにあらたな展開に入っているという感じがします。
そのなかでいわゆる「司馬史観」と、かの「長州史観」的な見方は、少なくとも専門的な日本史研究においてはまったく問題にされなくなったと思えます。このことと、関様がいまウェブログで「長州史観」を問題にせざるを得ないという現実との奇妙なほどの乖離が「歴史学のあり方」の重大な問題ではないかと思いますが。
以上の報告をあらかたまとめたところで、歴史家(家近良樹氏)による著作と、歴史家(成田龍一氏)と社会哲学者(大澤真幸氏)の対談を知りました。
「薩長中心史観」の枠組みを取り払って幕末政治史を再構築することを追求して来られた家近良樹氏は『老いと病でみる幕末維新(人びとはどのように生きたか)』(人文書院、2014年)の<まえがき>において、氏が直面した大事故(日航機撃墜事件)と甚大災害(阪神・淡路大震災)、それに若い頃にぶつかった東大の入試中止が、氏の歴史を見る目の形成に大きな影響を与えたこと、さらに近年に重大な疾患を体験したことが、本書『老いと病でみる幕末維新(人びとはどのように生きたか)』を書く視点ときっかけをもたらしたことを述べておられます。
大澤真幸氏と成田龍一氏の対談『現代思想の時代 <歴史の読み方>を問う 』(青土社、2014年)の大澤真幸氏による「あとがき」によれば、成田龍一氏は「・・・一般の歴史学者とは少し違って・・・歴史学者として歴史を記述すると同時に、まさにその歴史(学)そのものがどのような意味で成り立ちうるのか、をつねに問い続けている人である」とのことです。
この対談において、同時代の問題(具体的には「3・11」)から歴史認識の転換をはかるべきこと、また未来(「未来の他者」)を契機に過去がまったく違って見えてくるということが提起されており、意を強くしました。
両氏による「3・11」の歴史と歴史観に対する措定が当惑するほどに哲学的といいますか思弁的で、肩すかしを喰らった感じがすることにかえって力づけられました。
かようなことで、たんさいぼう影の会長様に勝手に約しました「同時代的感覚と将来に対する問題意識による明治維新に関する仮説」を追って遅からずとりまとめ報告すべく、浅草十二階からの飛び降りを踏み切ることにいたします。
<追記>
山本博文ほか『こんなに変わった歴史教科書』(新潮文庫、2011年)という面白い本があります。「比叡山焼き討ち」のことが何かあるかと立ち読みし、それは期待はずれでしたが、二つのことが強く記憶に残りました。うろ覚えをご容赦ください。
<「鎖国」という言い方が消えた>
平成の中学歴史教科書になってから、江戸時代に外交・貿易についての「鎖国」という言葉が消えたそうです。これは、歴史研究者の目が欧米一辺倒から東アジアを重視するように向きを変え始めたことを反映するものであるとのことです。関良基先生が膝を打たれる話ではないかと思いますが・・・。
<「倒幕の偽勅」に目が向けられるようになった>
平成の中学歴史教科書になってから、薩長に交付された徳川慶喜追討の密勅が薩長と結託した公家のねつ造であったこと、そしてそれが重要な役割を果たしたことに、80年代以降の日本史研究の進展によって目を向けられるようになったことの反映であるとのことです。
中学教科書の文を見ますと、やわらかな表現ではあれ、倒幕の偽勅が薩長の謀略によるものであったことが示されています。
!むかしナマかじりした「法的思考(リーガル・マインド)」的に考えますに、偽勅、これはきわめて重大な問題だろうと思います。それ自体が天皇の公的な権威を決定的に蹂躙するものであり、さらに、この偽勅を正当性の根拠として正統性のある政権を暴力で打倒したわけですから、明治維新はまがいもなく法的には「犯罪」以外の何ものでもないことになります。このような「犯罪」を唯一法的に正当化する「暴政に対する人民の抵抗権(革命権)」というのは薩長の軍事クーデターには到底該当しません。
と、いうことで、明治維新は薩長による強引な武力クーデターであったこと(その背後の存在についてはともかく)、そこまでもう一歩です、中学歴史教科書において!驚くべきことでは。
教科書の執筆者を含めた歴史研究者の方々の真摯な姿勢と誠実なご努力に敬意を表します。
*****以下、薩長公英陰謀論者さんのコメントの枢要部分を転載*******
転載元の記事は以下
http://blog.goo.ne.jp/reforestation/e/dc79258fffc940d937834114e0c550a2
歴史における仮説の問題について「(1)歴史的事実それ自体」についての仮説(「新史実=真実」の発見)と「(2)歴史的事実の認識」にかかわる仮説とに区分して考えてみました。
しかし「歴史学」における決定的な困難は(1)が(2)に吸収されていることです。歴史学においておそらく最も重視されるソースであろう当事者および目撃者の「証言・叙述」は、その人の認識の言語による表現であって事実それ自体ではありませんし、事実のごく一部を反映したものであろうと思います。まして、このソースを対象とした研究が乗数効果で事実から離れることは当然のことです。
とりわけ21世紀になってから(そのように意識して見るようになったためでしょうか。最近とくに極端になったような気がしますが)報道の記事・テロップ・ナレーションのみならず画像や映像が事実・真相の追求のためのものではなく「権威側からの特定の認識の流布」となっていることを痛感するようになりました。これらを主たる一次史料とするであろう将来の歴史学的記述が現在の時代をどう描き出すかを想像すると、翻って、現在までの歴史叙述についても絶望感を抱いてしまいます。
おそらく「理系」における仮説は、原理や法則、またその現れ方に関するものであり、事象をその仮説によっていかに理論的に説明することができるか、また、事象の再現において、つまり実験や観察・観測によって、その仮説の有効性を検証することができるかということが問題になるのではないだろうかと思います。さらにまたその仮説を理論として応用したり、より大きな領域に適合するものに発展させることができるか、ということが重要になるのだろうと推察します。
しかし、科学を自称する経済学はともかく(自己の理論が仮説であり検証されるべきものであることを認めない経済学を関良基先生はカルトとお呼びになっているのではないかと思います)自然史は措くとして少なくとも人間社会の歴史、つまり社会の変化は、不可逆であることは当然として(誰かのようにこれを認めないこともカルトですね)自然現象におけるような再現性がまったくないものだと思います(「自然=宇宙」の歴史は再現性はないものなのかもしれませんが)。
ただし、歴史における「原理や法則」として、かっては史的唯物論による「生産力と生産関係の変化としての社会発展」史観が大きな影響力を持ち、またそれに代わって現代の支配的理念となっている「自由主義・民主主義・グローバリズムへの改革原理」というものがあります。後者は「歴史の終わり」というように、歴史不在というよりむしろ歴史を否定する特質・思考方法を持っていますが、両方とも普遍性・再現性・原理的永遠性を謳っているわけで、そのような決定論は歴史学における仮説の存在を許さないものだと思えます。
つまり歴史学における仮説は再現性をめぐって両翼から挟み撃ちにあっているわけです。そこで、歴史学における仮説とは何であり、またどのように形成され、また検証されうるのかと、途方に暮れました。が、かの「長州史観」や「司馬史観」のように歴史認識をカルト化させないために、歴史における事実と認識との関係、またこの双方における仮説と検証について非力ながら考えざるを得ませんでした。
この間に、以下の「比叡山焼討ち」問題に目を惹かれて触発されたことから、歴史における仮説ならびに専門家と非専門家の違いについて考えた「仮説的結論」を、早とちりではあれ、まず記しますと:
01 「(1)歴史的事実それ自体」については、仮説の設定(「新史実=真実」の発見)とその検証を含めて非専門家には手におえるものではない。
02 「(2)歴史的事実の認識」については、非専門家にとって現在における同時代的連関を意識した仮説の設定のみが可能である。
03 「(2)歴史的事実の認識」に関する専門家の検討・検証は、同時代的問題意識や同時代の感覚による人間観・社会観が直接影響しないように、対象となる当時の一次史料に厳格に準拠して行われる。
04 「(2)歴史的事実の認識」に関する非専門家による仮説は、同時代における「生きるスタンス」つまり将来に関する問題意識にリンクするために、歴史専門家の手による検証・検討・批判にはなじまない。
ということになるかと思います。
推察しますに歴史専門家の目は、その歴史家の生活のあり方、それに大きな影響を及ぼした事件、その中で形成された人間と社会に対する洞察を基礎としていると思います。アカデミックな訓練を受け教育・研究機関の中で一貫して生活する専門家と、それとはまったく異なる生活・社会体験を持つ非専門家との相違は、理系の仮説設定とその検証において可能である専門家と非専門家の連携を挫くものであろうと思います。
この困難を克服するには、アカデミックな歴史専門家のサイドで、同時代的問題意識を明確に掲げ、将来を見出そうと見つめる目でそのまま現在と「歴史」を見るということが可能でなければならないと思えます。
そのようなことがアカデミズムと歴史「業界」の中の歴史専門家にありうることなのか、門前の小僧にもなることができない素人には推し量ることができません。
なお上述の仮説は、下述の「比叡山焼討ち」問題に加えて、キューバ大使、ウクライナ大使を経験されて防衛大学教授となった馬渕睦夫という方に対する、ウクライナ問題への関心から見ましたインタビューの後記にあった、同氏の次のような言葉に深く強く触発されたことにもとづいています。
http://chizai-tank.com/interview/interview201405.htm
「私は特別な情報ソースを持っているわけではありません。寧ろ特別な情報ソースを持っているという人は、反対にそのソースから操られている可能性も高いものです。だから我々は、まず今起こっていることを自分で考え、過去に起ったことを実体験と結び付け、公開情報をもとに自らの世界観で解釈していくことが大切、そうすれば隠されている本当に重要な事も見えてきます」
さて、「(2)歴史的事実の認識」にリンクした「(1)歴史的事実それ自体」について挑戦をした興味深い例があります。織田信長による比叡山焼き討ち事件に関する兼康保明氏の報告です。
兼康氏は1949年生まれで大学の史学科を卒業後、滋賀県教育委員会に所属して遺跡調査を専門となさった方で、比叡山延暦寺の史跡地内での発掘調査に直接携わっておられます。氏の報告は「織田信長比叡山焼き討ちの考古学的検討」(『滋賀考古学論叢第1集』、滋賀考古学論叢刊行会、1981年)にまとめられているとのことですが、私にはアクセスを含めて手におえないと思われますので、この論文をもとにして兼康氏が書かれた「比叡山焼き討ちの真相」(兼坂保明『考古学推理帖』大巧社、1996年;p130~142)から抜粋引用しつつ弊見を付してみます。
> ・・・東塔で現在まで約二〇カ所ほどの堂、坊跡を調査しているが、遺構や遺物から元亀の焼き討ちを証明できるのは、根本中堂と大講堂の二カ所だけである。・・・西塔も・・・常行堂の北部で伴出遺物から元亀の焼討ちの焼土層ではないかと考えられるものが発見されているだけで、他の場所で発掘された遺構や遺物は、室町時代以前のものと江戸時代のものばかりである。
<弊見> 平安貴族仏教のメッカであり、また禅宗や浄土宗の母ともなった比叡山延暦寺の権威の象徴であった根本中堂と大講堂だけを焼くだけで十分であり、しかもそれはきわめて容易なこと、しかし、その政治的・心理戦略的効果は絶大だったと。
比叡山各所の発掘調査は比叡山縦走ドライブウェイの建設という全山調査に絶好の機会を含め、建物の建て替えや修理にあたって繰り返し行われ、発掘調査において「元亀の比叡山焼き討ち」は一貫して強い関心の対象であったと調査に参加した兼康氏は証言しています。
「なかった」ということを物証的に確認するのは容易ではないと思いますが、文献資料にあたりながら発掘調査を実地に行った専門家の兼康保明氏の仕事から、語り継がれた「比叡全山炎上大虐殺」がフィクションであるのは明らかではないでしょうか。
> ・・・三塔各所の発掘調査の結果から結論づけるなら、元亀二年の織田信長による延暦寺焼討ちのさい、比叡山に所在した堂舎の数は少なく、また16世紀代の遺物の少ないことから『多聞院日記』などにみられるように、僧衆の多くは坂本に降り、生活の場もすでに山を離れていたと考えざるをえないのである。つまり、山上においては、全山数百の諸堂が紅蓮の炎に包まれ、大殺戮がくりひろげられたとするイメージを生み出すのとはうって変わった、閑散たる光景しか存在しなかったのが現実である。このことは、山上の放火、掃討がわずか二~三日ときわめて短期間であったことからもうかがえよう。
<弊見> 先のコメントで先回りしてしまいましたが、「比叡山全山炎上と炎の中での数千人の虐殺」は、延暦寺に体現された貴族的天台宗から浄土宗系の庶民仏教、すなわち「旧体制支配者側」の政治文化と、同時に「反体制民衆側」の精神的支柱を一挙に否定し葬り去るための「神話の創出」であったということになります。
> ・・・信長の右筆、太田牛一が自らの見聞をもとに記したとしてよく引用される『信長公記』の「叡山御退治の事」をよく注意して読むと、比叡山上をも攻めてはいるが具体的な戦いの様子は、実は山麓にある坂本のできごとである。有名な虐殺については・・・坂本の日吉社の神体山で標高380メートルほどの八王子山でのできごとで、峻険な比叡山上の・・・山腹にある諸堂でのできごとではない。
<弊見> 兼康保明氏は、信長の事績についての基準的文献とされている『信長公記』の該当箇所が意図的に比叡山上と山麓の坂本での出来事を混同させるように書かれていることを、発掘調査にもとづいて指摘しています。
比叡山焼き討ちのイメージ形成において『信長公記』よりむしろ決定的な役割を果たしたと思われる『言継卿記』の元亀二年九月一二日の伝聞体の叙述を見てみます。小和田哲男著『歴史ドラマと時代考証』(中経出版、2010年・中経文庫、2012年)の電子版から抜粋転載しますと:
>> ・・・織田弾正忠、暁天より上坂本を破られ火を放つ。次いで日吉社残さず、山上東塔、西塔、無童子(寺)残さず火を放つ。山衆悉く討死と云々。・・・講堂以下諸堂に火を放ち、僧俗男女三四千人を伐り捨て、堅田等に火を放つ。・・・大講堂、中堂、谷々伽藍一宇も残さず火を放つと云々。
と、あるとのことです。山麓にある坂本の里坊と日吉大社、さらに北東にJRで二駅離れた琵琶湖岸の港町堅田と、標高800mを越える比叡山全域が境内の延暦寺とをすっかり一体にしながら(西塔下のケーブルカーの駅は標高654m、山麓の駅との高低差は484mだとか)、強いイメージを畳みかけ重ねて、伝聞「云々」を多用しつつ、3~4千人もの虐殺をともなう全面焼き討ちが比叡山上の延暦寺において行われたように印象づけられています。
> 信長の真のねらいは、弱体化しながらも伝統的な権威を保持していた延暦寺を攻めることによって、労せずして天下に自らの力を誇示することにあったのである。今日われわれが抱いている焼討ちのイメージは、四百年前に信長が考えた戦略的効果のなかに、時を越えてなお呪縛されていたのである。
<兼康保明氏引用と弊見以上>
当然に抱く「なぜ当事者の一方である比叡山延暦寺側の記録証言がまったくないのか」ということが疑問なまま、比叡山延暦寺のサイト「歴史」のところを見ましたら「織田信長によって比叡山は全山焼き討ちされ、堂塔伽藍はことごとく灰燼に帰しました」とあって、天井を仰ぎました。
Wikipedia「比叡山焼き討ち」を見ますと、最初の概要部分に「なお一方、近年の発掘調査から、施設の多くはこれ以前に廃絶していた可能性が指摘されている」という一文が挿入されています。紀伊國屋書店(新宿本店ではありません)で、比叡山焼き討ちを取り上げている歴史関係の本を見てゆきましたところ、三分の一くらいが兼康氏の発見を認識して叙述に取り入れているように思われました。
氏の「比叡山焼き討ち」検証が知られるようになったのは1980年代以降であると思われますが、現在になってようやく兼康氏の発見が定着し始めているように思えます。
ともあれ、織田信長が「革命の寵児」として徹底的な近代的合理主義者、既成権威=アンシャン・レジームの破壊者であることを謳うには「比叡山焼討ち」は最高の演出です。そのようなイメージで信長が注目されたのは戦後のことで、とりわけ例によって司馬遼太郎が、『国盗り物語』で描いた信長像が決定的と言えるインパクトを持ったと思われます。司馬遼太郎は、信長と、そして坂本龍馬を「時代に先駆けた悲劇の革命児」に謳いあげたわけです。
先の引用の最後にある兼康保明氏の結論的コメントにうなづきながら、幾日かあとになって肩をおとしました。まさに専門家でしかできない「(1)歴史的事実それ自体」の発見、しかも史料文献を現場の発掘結果によって吟味検証したもので、文献学によらないものであるという意味で特異と言える成果が、おそらく当時(1960年代から70年代)の日本史学の発展段階に制約されて、当時の「国家統一をめざした最強の革命児」としての信長の像に取り込まれていると気がついたからです。
歴史専門家の兼康保明氏は発掘を武器とする歴史専門家ならではの「(1)歴史的事実それ自体」の発見を果敢に行いながら、「(2)歴史的事実の認識」においては、司馬遼太郎が商品化した既定の信長像を裏書きすることになっています。近年の研究の発展によって「宗教的権威の破壊者でもあった近代的合理主義者、国家統一をめざした革命児」という信長像は(戦後につくられたイメージであって)信長の実像とは異なるものであることが明らかにされているようです。兼康保明氏が信長神話を見破る物証をつかみながら、手の上に乗った物証を地に落としてその音を聴くことができなかったのはなぜだろうかと考えてしまいます。
http://www4.plala.or.jp/kawa-k/kyoukasyo/3-4.htm
「信長は『旧体制』の再編強化を図ったー『旧体制』の破壊者という信長像の誤り」という記事に、2000年前後の信長研究の成果がまとめられており、大変参考になりました。ただし内容はこのタイトルそのままではないように思えます。機会をあらためて突っ込んで考えて(「倒幕維新」を対比して考えるために)報告することができればよいのですが。
前述の勝手な仮説01~04のようにひとりですくんでしまっていますが、さらに考えますに次のような仮説を立てることができるかもしれないと思っております。
05 アカデミックな歴史学(日本史学)はあらたな発展段階にあり、徐々に時代にキャッチアップしてゆきはじめる段階にある。
06 時代そのものが深く混迷・閉塞しているなかで時代の先に出ることができるかどうかが歴史学の躓きの石になると思われる。
07 それゆえにこそ、時代の先に出ようとする、あるいは、近代的な見方(その裏返しに思える「ポスト・モダン」系思考を含めて)の先に出ようとする歴史研究者が存在する、あるいは現れるのではないだろうか。
成田龍一著『近現代日本史と歴史学』(中公新書、2012年)によれば、日本史研究は1980年前後から氏が戦後第3期に区分するあらたな段階に入ったとされています(同書p3~p14)。成田龍一氏の言う第3期、その終わりであろう21世紀に入ってから、少なくとも近世から近代を対象とする日本史研究はさらにあらたな展開に入っているという感じがします。
そのなかでいわゆる「司馬史観」と、かの「長州史観」的な見方は、少なくとも専門的な日本史研究においてはまったく問題にされなくなったと思えます。このことと、関様がいまウェブログで「長州史観」を問題にせざるを得ないという現実との奇妙なほどの乖離が「歴史学のあり方」の重大な問題ではないかと思いますが。
以上の報告をあらかたまとめたところで、歴史家(家近良樹氏)による著作と、歴史家(成田龍一氏)と社会哲学者(大澤真幸氏)の対談を知りました。
「薩長中心史観」の枠組みを取り払って幕末政治史を再構築することを追求して来られた家近良樹氏は『老いと病でみる幕末維新(人びとはどのように生きたか)』(人文書院、2014年)の<まえがき>において、氏が直面した大事故(日航機撃墜事件)と甚大災害(阪神・淡路大震災)、それに若い頃にぶつかった東大の入試中止が、氏の歴史を見る目の形成に大きな影響を与えたこと、さらに近年に重大な疾患を体験したことが、本書『老いと病でみる幕末維新(人びとはどのように生きたか)』を書く視点ときっかけをもたらしたことを述べておられます。
大澤真幸氏と成田龍一氏の対談『現代思想の時代 <歴史の読み方>を問う 』(青土社、2014年)の大澤真幸氏による「あとがき」によれば、成田龍一氏は「・・・一般の歴史学者とは少し違って・・・歴史学者として歴史を記述すると同時に、まさにその歴史(学)そのものがどのような意味で成り立ちうるのか、をつねに問い続けている人である」とのことです。
この対談において、同時代の問題(具体的には「3・11」)から歴史認識の転換をはかるべきこと、また未来(「未来の他者」)を契機に過去がまったく違って見えてくるということが提起されており、意を強くしました。
両氏による「3・11」の歴史と歴史観に対する措定が当惑するほどに哲学的といいますか思弁的で、肩すかしを喰らった感じがすることにかえって力づけられました。
かようなことで、たんさいぼう影の会長様に勝手に約しました「同時代的感覚と将来に対する問題意識による明治維新に関する仮説」を追って遅からずとりまとめ報告すべく、浅草十二階からの飛び降りを踏み切ることにいたします。
<追記>
山本博文ほか『こんなに変わった歴史教科書』(新潮文庫、2011年)という面白い本があります。「比叡山焼き討ち」のことが何かあるかと立ち読みし、それは期待はずれでしたが、二つのことが強く記憶に残りました。うろ覚えをご容赦ください。
<「鎖国」という言い方が消えた>
平成の中学歴史教科書になってから、江戸時代に外交・貿易についての「鎖国」という言葉が消えたそうです。これは、歴史研究者の目が欧米一辺倒から東アジアを重視するように向きを変え始めたことを反映するものであるとのことです。関良基先生が膝を打たれる話ではないかと思いますが・・・。
<「倒幕の偽勅」に目が向けられるようになった>
平成の中学歴史教科書になってから、薩長に交付された徳川慶喜追討の密勅が薩長と結託した公家のねつ造であったこと、そしてそれが重要な役割を果たしたことに、80年代以降の日本史研究の進展によって目を向けられるようになったことの反映であるとのことです。
中学教科書の文を見ますと、やわらかな表現ではあれ、倒幕の偽勅が薩長の謀略によるものであったことが示されています。
!むかしナマかじりした「法的思考(リーガル・マインド)」的に考えますに、偽勅、これはきわめて重大な問題だろうと思います。それ自体が天皇の公的な権威を決定的に蹂躙するものであり、さらに、この偽勅を正当性の根拠として正統性のある政権を暴力で打倒したわけですから、明治維新はまがいもなく法的には「犯罪」以外の何ものでもないことになります。このような「犯罪」を唯一法的に正当化する「暴政に対する人民の抵抗権(革命権)」というのは薩長の軍事クーデターには到底該当しません。
と、いうことで、明治維新は薩長による強引な武力クーデターであったこと(その背後の存在についてはともかく)、そこまでもう一歩です、中学歴史教科書において!驚くべきことでは。
教科書の執筆者を含めた歴史研究者の方々の真摯な姿勢と誠実なご努力に敬意を表します。














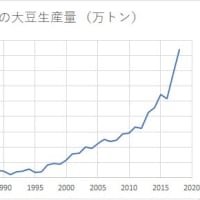

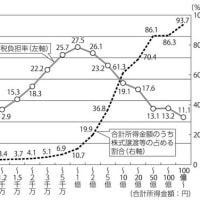



関良基先生:
繰り返し考えを漉いてみましたが、基礎的な知力学力の不足が露呈して、結果として所感吐露の域を出てはいないものを、ご親切に論文と呼んでいただいて記事に取り上げていただき、申しわけない思いで一杯です。
やはりあきらめずに院に行き、思考と書くことの訓練をすればよかったのかと、手おくれのことがふとアタマを横切りました。
ゴーリキーの『私の大学』をたよりにしてとはいえ、視界に覆いかぶさるさまざまの権威に膝を屈してしまわないようにかろうじて逃げ回るだけの人生に見合ったものしか書けないのだと、振り返らずして臍を噛んでおります。
ただしじつは、関先生のこのウェブログのおかげで「いまになって救われた」と内心大変感謝しております。
昨年度の愛すべき関ゼミ生Tさんのお人がらが偲ばれる文章のスタイルと関先生とのやりとりが不思議に新鮮に思えまして、この投稿が以下少しずつTさんに引きずられてポップ・カジュアル体となってゆきますこと、どうかご容赦ください。
12434様が「ブラック企業の特性」として示唆しておられますが、企業というものはおそらく大企業になればなるほど社員を常時全人格的に、つまり心そのものを支配します。「ブラック」流ではなく、いろいろなかたちで。
これが一方的な有無を言わさぬ支配であることが日本の企業の特徴だと言えるかもしれません。個人の独立性を超越して無条件に。ほぼカルト並みかも。
以前は、これは江戸時代の「藩」が企業として生きのこったということかと思っていましたが、どうも薩長に特有のものであるらしいことを本ウェブログの関良基先生の一連の論議から知ることができました。 たとえば、薩摩の反「公議政体」派による赤松小三郎暗殺の「論理(利害「倫理」)」がひとつです。利権勘定が武士としての人倫(仁義礼智信)に優先すること、名前はお武家風の竹中平蔵流ですね。
とりわけなぜか最近、おそらくその殆どが大企業正社員ではないと言えるであろう日本の民全体に対して大企業の支配が露骨に及ぶようになっているように思えます。
経済界の代理人である政府と翼賛議会による政策と外交、電通&マス・メディアによる人心支配のみならず、本ウェブログの記事に取り上げられたように、各レベルの教育研究機関の内部に及ぶ官僚支配によって、すべてが「金目」と化しました。
電通系のネット・ウオッチャーかと思える wellcometolivegim 氏がどう言おうが「自由」貿易とはグローバル強者である大企業のためのものであって圧倒的に多くの各地場産業事業者と生活者住民のためのものではないことは現実のグローバル経済に手の先を染めてみれば自明のことです(おそらくそちらサイドの人びとには「自分が自由であることが皆が自由であること」と思えるだろうというのは一定のインサイダー経験から実感できますが)。
と、いうようなことを想いながら「歴史問題」に不意に着地しますと、上記に書いたようなことを含めて、人間とその組織・集団の営み、その自然環境とのインタフェイス(対峙征服破壊であろうが融合調和であろうが)のすべてが歴史になり、しかも、現在から将来まで続いて行くわけで(どうか歴史が終わりませんように)、あろうことか歴史「学」をどうこう・・・とかわかったようなことを言うのはとんでもないことだと、じつは正直立ちすくんでいます。
徳川が上田攻めで喰らった想定外の蹉跌が戦力配置上の齟齬のみならず、徳川勢力自体の内的構造力学に看過できないひずみを発生させてしまったこと、「長州系体質」とは無縁で自方を等身大に見ることができる政治家であった家康はそれをよく認識して判断し動いたであろうこと、これは関良基先生のみごとな整理に拠ってはじめて推察できることですが・・・たとえばそういうことは文献史料に書かれたことのみで世界を知る歴史専門家の目には映らないだろうと思います。
Tさん風に言うと(失礼ご容赦を)「ほんもののナマの歴史は歴史専門家さんたちにはムリかなー」と。えぇ、無論まして当方のような問題外の小輩にはとんでもないことであると。そう思えます。
じつは10年以上前だったと、たしか海外で国際金融にかかわっておられる方だと思いますが「薩摩と長州の手を握らせて起こした戊辰戦争って、今でもCIAがアフリカや中南米でよくやっている軍事クーデターとおなじやね」というような言い方をされて思わず目をむいたことを思い出します。ロンドンから日本を見ているとそうなのか、と。
たとえばこういう、専門家にとっては非専門家の「無責任な」でしょうが、天馬空を行く同時代的問題意識というのは日本のなかで学究をしている日本史専門家にはちょっとありえないのではないでしょうか。
関良基先生の「歴史専門家的『歴史観』」についての的確な問題提起をかえってぐしゃぐしゃにしてしまいました。どうかご容赦ください。
いえ、専門家であればあるほど、与えられた枠に嵌まり、手にした枠を補強し、根もとを掘り返すこと、ひっくり返すことを忌避するものでしょう。
そしてじつは無難なこと(「世に沿う」こと)を言う以外は口を閉ざす、と。そして、その「専門家」の掟に反するものには歯を剥き唾をかける。そういう社会的本能をお持ちだろうと思います。
あ!自然の生きものを相手になさっている珪藻の専門家は絶対に上記にはあたりません。原発から歴史はもとより政治、経済を含めて「人為的な」ものの専門家(関良基先生以外の大方)についてのみ言っています。
と、いうことで「維新」論仮説については、ふたたび手を拱きはじめました。何とかまた立ち上がります。お待ちください。