こないだ、こどもの日に、
 「端午の節句」には、その昔 くす玉を飾った。
「端午の節句」には、その昔 くす玉を飾った。
というお話をしました。
くす玉のくすは、薬のこと。
とつぜんですが、
冷奴が美味しい季節となりました。
これに欠かせないのが、「薬味」
これにも、薬がつきますよね。
ショウがやネギなどを、なぜ薬味というんだろ???
『薬味』は本来【薬の種類や薬の原料になるもの】をいうことば。つまり薬そのもののこと。古代に薬といえば、植物など自然のものを体に取り入れることが多く、それが、現代の香味野菜や香辛料につながったのですね。中国最古の薬の書物「神農本草経」には『梅実』の記述があり、味や効能なども書かれてありました。2000年前にはすでに「梅」は体に良いとされていたのです!さて、インスタントラーメンなどに入っている『かやく』も、漢字で『加薬』と書き、薬に関係します。もともとは【漢方で主薬に少量の補助薬を加えること】をいったのが、食品に加える薬味や細かく切った野菜や肉なども『加薬』と呼んだのです。混ぜごはんを「かやく御飯」ということがありますが、「かやく○○」というのは関西での言い方で、関東では「五目○○」というのが一般的なのですよ。さて、もうひとつ。式典や祝い事などに用いられる『くす玉』も『薬玉』と書きます。古くは錦の袋に麝香、沈香、丁子などの香料を入れ、円形にし花でまわりを覆い、菖蒲やヨモギをあしらって五色の糸を長くたらしたもの。香りは邪気を払い、病気が起こらないと考えられたため、薬の玉で『くす玉』なのですね。『くす玉』は平安時代より五月五日の端午の節句に飾られました。端午の節句はもともと中国から伝わった厄払いの行事。厄を払い、長寿を願ってくす玉を飾ったのです。意外なものが薬と深い関係があったのですね。
以上、説明文は、 トクする日本語より。(いつもお世話になっています、ありがとうございます。)
トクする日本語より。(いつもお世話になっています、ありがとうございます。)
ふむふむ。
「薬味」「加薬」そして再度「くす玉」
な~るほどですね。
あ、我が家は、混ぜごはんのこと
かやく御飯ともいわないし、五目御飯ともいわなくて
「炊き込み御飯」といいますよ。
最後に
カミングアウト。
冷奴の季節~なんていいましたが
唯一、嫌いな食べ物はなんですか?と
問われたら
私、速攻「豆腐です!」と、答えるので、ありまする。
 ・・・
・・・








 「端午の節句」には、その昔 くす玉を飾った。
「端午の節句」には、その昔 くす玉を飾った。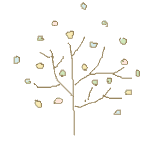
 トクする日本語より。(いつもお世話になっています、ありがとうございます。)
トクする日本語より。(いつもお世話になっています、ありがとうございます。)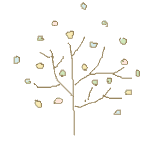
 ・・・
・・・

 はなこころ
はなこころ です。
です。