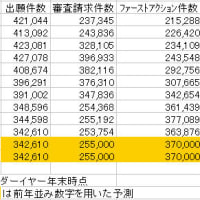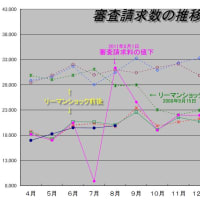◆H17. 1.31 東京高裁 平成15(行ケ)220 特許権 行政訴訟事件
条文:特許法第36条4項
原告は,発明の名称を「抗HCV抗体の免疫アッセイに使用するC型肝炎ウイルス(HCV)抗原の組合せ」とする特許の特許権者である。
被告は,平成13年10月22日,本件特許をすべての請求項に関して無効とすることについて審判を請求した。特許庁は,審理の結果,「特許第2733138号の請求項1ないし12に係る発明についての特許を無効とする。」との審決した。
(判事事項1)構成の特定の不足
「原告は,この点について,本件発明において,厳密なエピトープの特定は必要でなく,おおよその抗原性領域の特定ができれば足りるとも主張する。確かに,正確なエピトープの位置が分からなくても,ドメイン上の領域で,エピトープを含むことが明らかなものを特定することができるのであれば,原告の主張を採用する余地もあるといえる。しかし,そのようなことが,本件明細書に記載されているとも,本件優先日当時の周知技術であったとも認めることはできない。」
(判事事項2)過度の実験が必要
『原告が指摘するとおり,その予測値が約50%であるにせよ,なお,エピトープの特定には数十万を優に超える回数の実験が必要』
『前掲甲第31号証には,「どの位置にエピトープがあるかどうかを予測することによって,エピトープの同定に必要な工程数も格段に減少します。通常,このような予測を組み合わせることによって,必要となる工程数は,2桁以上少ない工程数になると見積もられます。」(6頁~7頁)との記載がある。しかし,具体的にどのような方法によるのか明らかではないし,仮に二桁以上少なくなるとしても,HCV1だけでも,7000通りを優に超える実験を行うことになるのであり,これは過度の実験に該当するといえる。』
(感想)化学は専門ではなく、よくわからないところもある。しかし、記載が甘く過度の実験が必要であれば36条4項違背となることを明確に述べたところは参考になる。
条文:特許法第36条4項
原告は,発明の名称を「抗HCV抗体の免疫アッセイに使用するC型肝炎ウイルス(HCV)抗原の組合せ」とする特許の特許権者である。
被告は,平成13年10月22日,本件特許をすべての請求項に関して無効とすることについて審判を請求した。特許庁は,審理の結果,「特許第2733138号の請求項1ないし12に係る発明についての特許を無効とする。」との審決した。
(判事事項1)構成の特定の不足
「原告は,この点について,本件発明において,厳密なエピトープの特定は必要でなく,おおよその抗原性領域の特定ができれば足りるとも主張する。確かに,正確なエピトープの位置が分からなくても,ドメイン上の領域で,エピトープを含むことが明らかなものを特定することができるのであれば,原告の主張を採用する余地もあるといえる。しかし,そのようなことが,本件明細書に記載されているとも,本件優先日当時の周知技術であったとも認めることはできない。」
(判事事項2)過度の実験が必要
『原告が指摘するとおり,その予測値が約50%であるにせよ,なお,エピトープの特定には数十万を優に超える回数の実験が必要』
『前掲甲第31号証には,「どの位置にエピトープがあるかどうかを予測することによって,エピトープの同定に必要な工程数も格段に減少します。通常,このような予測を組み合わせることによって,必要となる工程数は,2桁以上少ない工程数になると見積もられます。」(6頁~7頁)との記載がある。しかし,具体的にどのような方法によるのか明らかではないし,仮に二桁以上少なくなるとしても,HCV1だけでも,7000通りを優に超える実験を行うことになるのであり,これは過度の実験に該当するといえる。』
(感想)化学は専門ではなく、よくわからないところもある。しかし、記載が甘く過度の実験が必要であれば36条4項違背となることを明確に述べたところは参考になる。