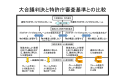事件番号 平成25(ネ)10030
事件名 損害賠償請求控訴事件
裁判年月 平成25年08月22日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 民事訴訟
裁判長裁判官 土肥章大、裁判官 田中芳樹、荒井章光
特許発明の特許請求の範囲の解釈
ア 控訴人は,本件手続補正書の「3-1)」及び「3-2)」は,・・・,原本性を証明してもらうためのデータを,原本性を証明する処理のために受け取ることを否定する陳述ではないから,ダイジェスト照合によって実現しているサービスに,原本性を証明してもらうためのデータを受け取り保管することを加えることをもって,構成要件6及び7の充足性を否定する根拠とはならない旨主張する。
しかしながら,・・・,控訴人は,本件特許の拒絶査定不服審判において,本件発明は,「伝達情報」等を発信者装置A及び受信者装置Bから内容証明サイト装置Cに送信せず,「伝達情報」を内容証明サイト装置Cが保管しないことによって,引用文献等記載の発明と異なり,通信量(情報量)が多くならず,多くの情報量を保管する構成でもなく,公証人等による伝達情報への不正関与の可能性を高くしないという効果を奏すると陳述し,本件発明は,控訴人のかかる陳述を踏まえた上で,特許査定がされたものであるから,本件発明の構成要件6及び7の意義は,契約当事者双方が契約書の「原本」を管理し,内容証明サイト装置は原本が改ざんされていないことを伝達情報のダイジェスト又は伝達情報を暗号化した暗号情報のダイジェストのみに基づいて検証することで証明するサービスであると解するのが相当である。
したがって,原本性を証明するためのデータではなく,原本性を証明してもらうためのデータであれば,「伝達情報」を受け取り保管することもできるとする控訴人の主張は採用することができない。
事件名 損害賠償請求控訴事件
裁判年月 平成25年08月22日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 民事訴訟
裁判長裁判官 土肥章大、裁判官 田中芳樹、荒井章光
特許発明の特許請求の範囲の解釈
ア 控訴人は,本件手続補正書の「3-1)」及び「3-2)」は,・・・,原本性を証明してもらうためのデータを,原本性を証明する処理のために受け取ることを否定する陳述ではないから,ダイジェスト照合によって実現しているサービスに,原本性を証明してもらうためのデータを受け取り保管することを加えることをもって,構成要件6及び7の充足性を否定する根拠とはならない旨主張する。
しかしながら,・・・,控訴人は,本件特許の拒絶査定不服審判において,本件発明は,「伝達情報」等を発信者装置A及び受信者装置Bから内容証明サイト装置Cに送信せず,「伝達情報」を内容証明サイト装置Cが保管しないことによって,引用文献等記載の発明と異なり,通信量(情報量)が多くならず,多くの情報量を保管する構成でもなく,公証人等による伝達情報への不正関与の可能性を高くしないという効果を奏すると陳述し,本件発明は,控訴人のかかる陳述を踏まえた上で,特許査定がされたものであるから,本件発明の構成要件6及び7の意義は,契約当事者双方が契約書の「原本」を管理し,内容証明サイト装置は原本が改ざんされていないことを伝達情報のダイジェスト又は伝達情報を暗号化した暗号情報のダイジェストのみに基づいて検証することで証明するサービスであると解するのが相当である。
したがって,原本性を証明するためのデータではなく,原本性を証明してもらうためのデータであれば,「伝達情報」を受け取り保管することもできるとする控訴人の主張は採用することができない。