玉名市の高瀬裏川で初夏恒例の「花しょうぶまつり」が20日から始まります。2020・21年は新型コロナ感染拡大防止のため中止されましたので3年ぶりの開催となります。
5月20日(金)から6月4日(土)まで。メインイベントは5月28日(土)です。
高瀬裏川というのは、現在の玉名市中心部が肥後高瀬藩だった頃、菊池川流域でとれた米を積んだ平田舟が行き交った運河で、河岸には町屋や蔵が軒を連ねていました。今も往時の風情を感じる町屋が残っています。
かつて、肥後米の積出し港として栄えた高瀬町は、菊池川とその支流の繁根木川の中州にできた商業の町。古代から菊池川河口右岸に開けた港町でした。古くから関西、関門、博多方面と交流があったと伝えられます。また高瀬町の人々は菊池川のことを「高瀬川」と呼んでいたそうです。江戸時代には高瀬藩の御蔵が置かれ、肥後米最大の積出し港となっていました。そのためこの港から積み出した米は「高瀬米」とも呼ばれました。明治初期まで高瀬には菊池川を渡る橋がなく対岸の向津留から「向津留渡し」と呼ばれた渡し舟を利用していました。高瀬側に舟が着くと裏川筋にかかる数本の橋で町屋に通じていました。今も残る「高瀬眼鏡橋」を始めとする石橋がその名残りをとどめています。そんな歴史に想いを馳せながら散策するのも一興です。
今ではその役割を終えた運河には花しょうぶが栽培され、毎年5・6月には「高瀬裏川花しょうぶまつり」が行われています。
僕個人にとってここは、1971年に菊池川の少し上流の河崎地区に建設中だったブリヂストン熊本工場の、工場建設要員の宿舎として、この裏川沿いの町屋の一軒を借りていましたのでとても懐かしい地区です。
2019年に放送された大河ドラマ「いだてん ~東京オリムピック噺~」では主人公の金栗四三(中村勘九郎さん)の故郷でもある玉名の風景として、この河岸から米俵を積み出す場面が放送されました。

花しょうぶが咲き乱れる高瀬裏川(過年度の風景)

かつて高瀬川と町家をつないだ裏川に架かる高瀬眼鏡橋

かつて廻船問屋や船宿などの町屋が立ち並んだ裏川沿いの河岸の雰囲気が残る
高瀬米の積み出し風景を唄った「肥後の俵積出し唄」
5月20日(金)から6月4日(土)まで。メインイベントは5月28日(土)です。
高瀬裏川というのは、現在の玉名市中心部が肥後高瀬藩だった頃、菊池川流域でとれた米を積んだ平田舟が行き交った運河で、河岸には町屋や蔵が軒を連ねていました。今も往時の風情を感じる町屋が残っています。
かつて、肥後米の積出し港として栄えた高瀬町は、菊池川とその支流の繁根木川の中州にできた商業の町。古代から菊池川河口右岸に開けた港町でした。古くから関西、関門、博多方面と交流があったと伝えられます。また高瀬町の人々は菊池川のことを「高瀬川」と呼んでいたそうです。江戸時代には高瀬藩の御蔵が置かれ、肥後米最大の積出し港となっていました。そのためこの港から積み出した米は「高瀬米」とも呼ばれました。明治初期まで高瀬には菊池川を渡る橋がなく対岸の向津留から「向津留渡し」と呼ばれた渡し舟を利用していました。高瀬側に舟が着くと裏川筋にかかる数本の橋で町屋に通じていました。今も残る「高瀬眼鏡橋」を始めとする石橋がその名残りをとどめています。そんな歴史に想いを馳せながら散策するのも一興です。
今ではその役割を終えた運河には花しょうぶが栽培され、毎年5・6月には「高瀬裏川花しょうぶまつり」が行われています。
僕個人にとってここは、1971年に菊池川の少し上流の河崎地区に建設中だったブリヂストン熊本工場の、工場建設要員の宿舎として、この裏川沿いの町屋の一軒を借りていましたのでとても懐かしい地区です。
2019年に放送された大河ドラマ「いだてん ~東京オリムピック噺~」では主人公の金栗四三(中村勘九郎さん)の故郷でもある玉名の風景として、この河岸から米俵を積み出す場面が放送されました。

花しょうぶが咲き乱れる高瀬裏川(過年度の風景)

かつて高瀬川と町家をつないだ裏川に架かる高瀬眼鏡橋

かつて廻船問屋や船宿などの町屋が立ち並んだ裏川沿いの河岸の雰囲気が残る
高瀬米の積み出し風景を唄った「肥後の俵積出し唄」



















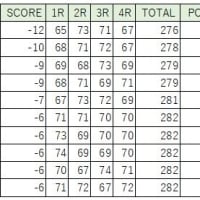
そうですか、この運河を利用して米が運ばれたのですね。往時のにぎわいがつたわってくるようです。栃木市に巴波川(うずまがわ)があります。そこは主に材木の集散地でした。そちらのように規模は大きくありませんでしたでしょうが、いくつも河岸があり、船で、渡良瀬川と利根川を通りぬけ、江戸の八丁堀へと運ばれたようです。
小江戸と呼ばれて舟運で江戸と繋がっていた栃木や巴波川のことは、何度かテレビで拝見したことがあります。たしか喜多川歌麿とのゆかりがあったんでしたっけ。
昔は運搬のメインは船だったんですね。
それにしてもどこの町にも運河が発達していたようで、その土木工事にも感心しています。
それが鉄道になり、いまや鉄道貨物はいったい何を運んでいるのだろうか(笑)と思うことです。
渡し船だと、積み下しの手間も要りますね。
あ~、次に「高瀬眼鏡橋」を渡るんですか!
写真の橋は絵になりますね。
この土木技術も凄いと思います。
私は事務屋ですが(汗)
お終いの写真の石垣もいいですね。
人力での組積工事技能も発達していたってことでしょう?
「肥後の俵積出し唄」は労働歌がこのようなお洒落な歌と踊りにかわったのか、初めからお座敷用に作られたのか?
興味深い歌と踊りです。
有難うございました。
運河造りの技術も凄いなと思います。
積み降ろしは人力ですが、昔の人は労作をいとわないですね。われわれとは労働に対する考え方が根本的に違うような気がします。
河岸の石垣を見ますといろんな時代の工法が混在しているようですので、おそらく何度も洪水に見舞われて修復や補強をしてきたんでしょうね。
「肥後の俵積出し唄」は明治初期から中期にかけて流行ったお座敷唄「サイコドン節」が元唄だと思われます。高瀬の芸者などが熊本バージョンを作ったのだろうと思われます。