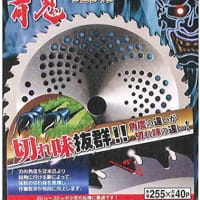60代後半の知り合いがいますが、娘さんのところに来年度の裁判員の打診が来たそうです。
大きな責任があります。どんな事件になるのかわからないし、自分に人を裁くことができるのか?と悩んだ娘さんは、この以来を受けるべきか?辞退すべきか?実家に相談に来ました。
こういうときに頼りになるのが父親の言葉です。
「一生のうちに一度歩かないかの大きな仕事だから受けなさい。何でもかまわないからとりあえず死刑にしておけば、犯人が娑婆に出てきて報復される心配はない。かまわねぇ、みんな死刑にしちまえ!」
迷いがないどころか、ぜんぜん考えていません。
選ぶ側も多少は人物を見ているのだろうか?この父親と娘ではずいぶん異なる判断になりそうです。
「12人の怒れる男」と言う名作映画がありました。USAの陪審員を描いた密室でのドラマです。日本人には陪審員制度はなじまないだろうなと思いながら見た覚えがありますが、陪審員制度とは多少違うものの責任を嫌う裁判員制度ができてしまいました。
陪審員制度と裁判員制度の違いのひとつは、陪審員制度が「有罪」「無罪」の判断に対して、裁判員制度は有罪のときの量刑にまで言及することです。
陪審員制度では「有罪」までですから、死刑なのか?主神経なのか?懲役○年なのかは裁判官が判断しますが、日本の裁判員は「死刑」まで決められるので、後々その責任に苦しめられることが懸念されています。
今年、裁判員制度で初めての「死刑」の判定が出ましたが、これに対して、裁判官が被告人に対して「控訴を進めます」と言ったのも、裁判官の判断を不服にしたからではなく、死刑判決をした民間人の裁判員が後々苦しめられることがないように、プロである自分たち裁判官が最後の判断をになうと言う心意気だったのでしょう。
最新の画像[もっと見る]