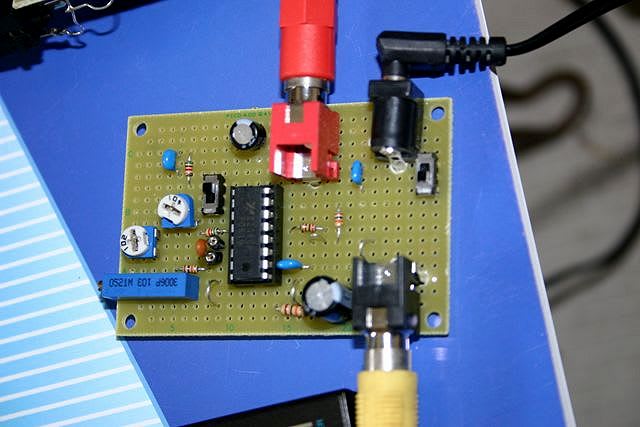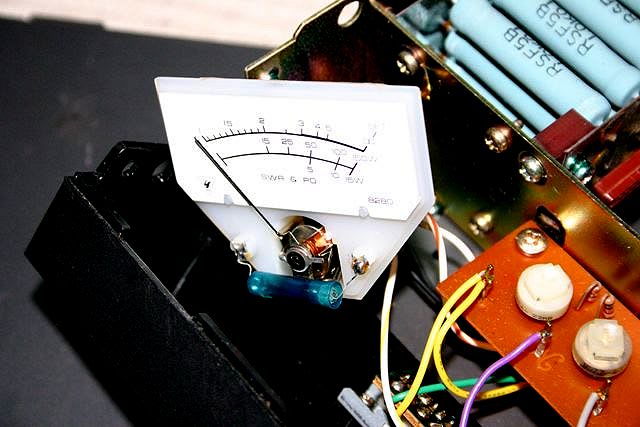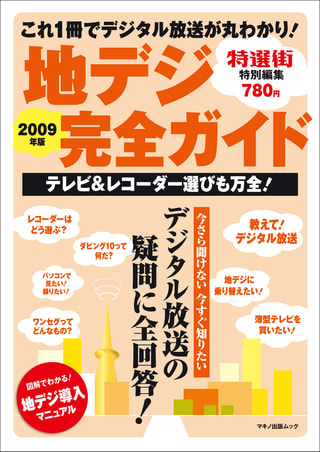HDDレコーダー代わりとして、SONY-PSXを2台ダブル録音として、使っていたが、相次いで、起動出来なくなってしまった。
HDDレコーダー代わりとして、SONY-PSXを2台ダブル録音として、使っていたが、相次いで、起動出来なくなってしまった。
録画出来なくなると生活まで不便になる?ので、急遽、ネット販売で安くて、性能が良くて、勿論これからは地デジチューナー付き、即納出来るのを探して12/18発注、12/19到着した。
東芝製の500GB-HDD&DVDレコーダーで、最新モデルより1つ古いが、性能は殆ど変わらず、最新より約16,000円安く購入出来た。
テレビはアナログ入力しか無いので、画質は従来通りだが。
早速、アンテナに接続してみた。BS/CS/地上波アナログは受信出来たが、地デジが受信出来ない。レベルもゼロである。地デジに使うUHFアンテナは、20年前から、取り敢えず設置してあった。U/V混合の増幅器を使っている。
実は、この地は電波の谷間に近いので、東京の電波が弱い。だから、周囲のUHFアンテナの向きを見ていると、結構強い栃木県宇都宮局に向けているのが半分近くある。だから、たとえ電波が受信出来たとしても、レベルが低くて画面が映らないということも十分考えられる。
先輩おもちゃドクター仲間から地デジ放送エリアの検索サイトを教えてもらい、調べたが、この辺は、やはり東京タワーしか放送エリアに入っていない。
夜も遅いので、翌日調査することにした。
12/20 午前中は、親子パソコン教室でクリスマスカードを作ると言うので、アシスタントで顔を出した。地元の工業高校生8名がボランティアで講師とアシスタントを務め、2時間で、皆さん素晴らしいクリスマスカードが出来上がり、喜んで帰った。
家へ帰り、UHFのアナログ放送を受信して見たが、殆ど映らない。設置した当時から確認してなかったのだが。アンテナか、増幅器の不良が考えられるので、切り分けすることにした。
増幅器は高い所に有り、手が届かないので、アンテナと、増幅器間のケーブルを切断して、アンテナからの同軸線にケーブルを延長してレコーダーに接続したら地デジが映った。
どうやら、増幅器がちゃんと動作していない様だ。
先程述べた通り、手が届かないので、U/Vの混合は、混合器(ケーブル接続の安い物)を購入して屋内のレコーダー側に付けることにした。
線がごちゃごちゃになってしまったが、これで、2011年対応に間に合った。
その後、各CHの受信状態を確認すると、TBSがギリギリのレベルにあり、ブロックノイズが時々発生して、正常に映らない。分配器無しだと正常に受信出来るので2dB以上増幅すれば、正常に受信出来そうだ。自作・広帯域アンプをつけて見たが、アナログVHF地上波にノイズが入ったりと使い物にならないので、20年ぶりの更新も兼ねてU/Vブースターを購入依頼した。
今日(12/23)も更に、詳しいデータリンクをおもちゃドクターから教えてもらいました。
ちなみに、東京タワーは12/23開業50周年を迎える。
これを見ると、同じ東京タワーでもアンテナの位置や形状が異なる様で、それでレベル差が出ているのかも知れません。
東京タワーのアンテナ群
茨城の鉄塔
日本各地の放送局データ
CS/BSの有料放送も、何日間かは無料視聴出来る様だ。
でも、電気的な知識の無い方が、レコーダーだけ購入して、設置・調整するのは大変だなと感じました。
●2次的には、地上波デジタル化によって、アマチュア無線のTVIが皆無か、軽減されることになる(これが、本来の目的かも)。