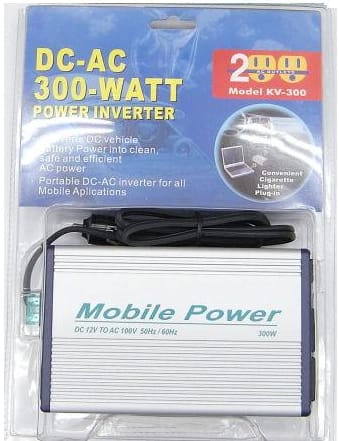最近、地デジのNHK総合、教育が受信出来ない(他のCHも一部受信出来なかったりする)というので、アンテナの方向がずれたかと思い調整するも良くならないので、接続を確かめてみた。
壁のコンセントとブースター電源部間を接続している同軸ケーブルを動かすと受信出来る様になる。
このケーブルはデッキなどに添付させる両端Fプラグはめ込み式の安いもので、チップ側の接触が良く無い様だ。
ここは大枚をはたいて、金メッキ製1mケーブル(片方はめ込み、もう片方はねじ式)を購入し交換してみたら問題無くなった。
地デジはUHF帯で周波数が高いので接触ロスが大きくなるのが原因だろう(当地は東京タワーからの電波だとギリギリのレベルなので)。
これでも、今まで受信出来ていた放送大学(東京タワーより5kW)と、ちばテレビ(船橋より500W)が受信出来なくなった。(NHK等は全て10kW)
東京タワーと、ちばテレビと、当地を地図上に表示すると約16度ずれていた。
受信電波の様な低レベルの信号(微小電流)を扱うには、金メッキが必要かも知れない。
特にFケーブルの場合には同軸の芯線をそのまま使用する場合があるので、これが接触不良の原因となりやすい。
プロの機器を製造していた頃は、全て金メッキのコネクタ/カードエッジを使用していた。