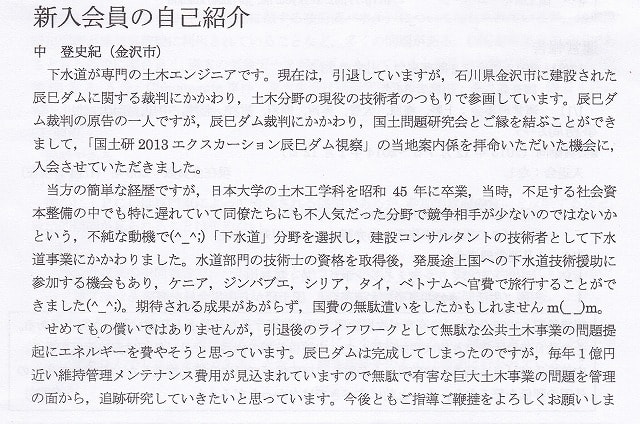国土問題研究会とは、研究者や技術者を中心に構成され、河川・道路・地域開発などにかかわる技術コンサルタントの能力を有した民間団体で住民などから依頼を受けて調査研究して解決策を提案する。国や自治体をから財源の提供を受けていないので、開発を推進する側の意向にとらわれず、政治的な圧力などによる技術的に不合理な判断を排除することができる。
特に、ダム問題の調査や提案に実績がある。1994年以降では、全国で24箇所のダム調査を行っている。
辰巳ダム裁判では、国土問題研究会の理事長(地すべり専門家)と副理事長(治水専門家)にお世話になった。御両名に、数回現場視察をしていただき、裁判所での学習会での説明、証拠調べでの証人として協力していただいた。おかげで2013年12月19日の結審まで無事、裁判を維持することができた。
という御縁があって、当方も入会させていただくことにした。
2014.1国土研ニュース440号に紹介記事が載りました。
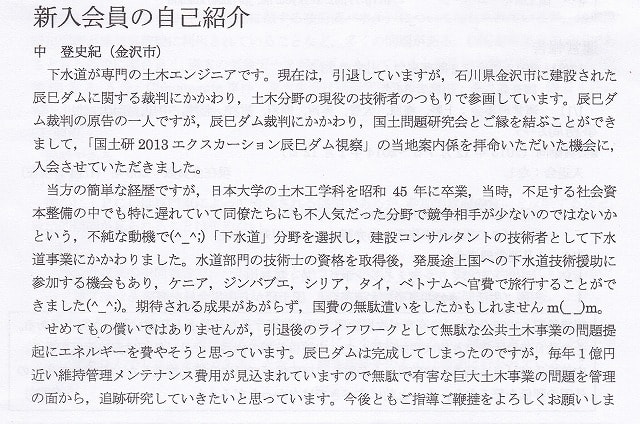
国土問題研究会の案内には、「、、科学技術が、公共という名目で開発を進める側にだけ奉仕して、開発の犠牲になる住民のために活用されていなかった反省にたって1962年に設立された。、、、、住民のための安全で住み良い地域づくり・国土づくりやそのための科学技術がどうあるべきかを調査研究して、、、「住民主義」「現地主義」「総合主義」の調査『三原則』をもとに、「専門分担型」の調査研究から、「総合討論型」の民主的調査研究の方向を指向し、、、、」などとある。
民間の建設コンサルタントで仕事をした経験からすると、住民の声は公務の担当者が受けとめた後、間接的に伝わるので住民の声がとどきにくい、バイアスがかる、民間の技術者は仕事のノルマに追われることが多いので現地に足が遠のく、同様の理由で総合討論して手間暇かけるよりも役所の担当者に意見をいわせてその指示どおりに仕事を進めがちである。調査三原則を自分にあらためて問い直してみると反省させられる。
ただ、地方の建設コンサルタントの経験が長いが、下水道の面整備(各家屋の前の道路に下水道管を2,3m程度の深さに設置する事業)などの定型的な設計業務で飯を食っていると、非三原則でも(住民は役所まかせで住民の声は聞かない、測量図上で設計、マニュアルどおりで余計なことは考えない)でも通用するので怠けていたなあm(_ _)m