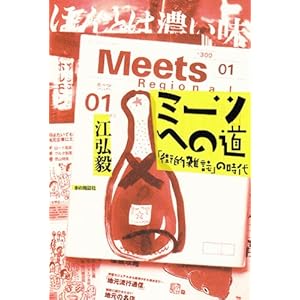本は「地域再生の罠 なぜ市民と地方は豊かになれないのか?」(ちくま新書)

好著です。
久繁 哲之介さんという現役の地域再生プランナーが書いた、誰もがうすうす気がついていながら言えなかった地域再生が失敗する根本的理由と新たな提言をまとめた一冊。
具体的な事例が多く紹介されていますが、本の前半は宇都宮市や岐阜市を例に挙げ、巨費を投じた「地域再生計画」がなぜ失敗してしまうのかを解説しています。
ひとことで言えば、「行政もコンサルも市民目線の欠けた、自分達に都合の良いプラン」を策定し実施しようとするから。
宇都宮市や岐阜市は地域再生の定番「大型商業施設」の建設と「流行のテナントの誘致」を行い、いずれも失敗してしまいます。
予算規模が100億円を超えるプロジェクトです。
その一方で岐阜市は路面電車を赤字を理由に廃止してしまいます。
街の中心部を活性化させるために商業施設を建設しておいて、その足となるべき交通手段は廃止してしまう。
なぜこんな相反する政策が同時に起こってしまうのか?
市民の声を聞かず、安易にコンサルの提案する他地域での「成功事例」を模倣するから、と著者は言います。
で、模倣したはずの「成功事例」もよくよく調べてみると「最初は良かったのに今は・・・」という「成功事例」のマガイモノだったりします。
読んでいると失敗の根っこは深そうです。
暗い気持ちになったところで、著者はいくつかの提言を行います。
そこで「成功事例」として取り上げられるのはいずれもささやかなもの。
しかも手間と時間、そして何より情熱や知恵がもとめられる「成功事例」です。
でも、たぶんそこにしか活路はないのでしょう。
数百億円もかけて「地域活性化の起爆剤」のハコモノを作っても発想の根っこが安易な模倣であればうまく行くはずもありません。
自分達の地域の資源をもう一度見直して自分達の力でささやかでも盛り上げていく。
「地域再生に王道は無い」といったところでしょうか。
たしょう論の甘いところや事例で「?」と感じさせるものがあって時々引っかかりましたが、新しい視点を提示できていると思います。
地域再生だけでなく、自分の仕事などいろいろなことに共通する「気づき」がある一冊でした。

好著です。
久繁 哲之介さんという現役の地域再生プランナーが書いた、誰もがうすうす気がついていながら言えなかった地域再生が失敗する根本的理由と新たな提言をまとめた一冊。
具体的な事例が多く紹介されていますが、本の前半は宇都宮市や岐阜市を例に挙げ、巨費を投じた「地域再生計画」がなぜ失敗してしまうのかを解説しています。
ひとことで言えば、「行政もコンサルも市民目線の欠けた、自分達に都合の良いプラン」を策定し実施しようとするから。
宇都宮市や岐阜市は地域再生の定番「大型商業施設」の建設と「流行のテナントの誘致」を行い、いずれも失敗してしまいます。
予算規模が100億円を超えるプロジェクトです。
その一方で岐阜市は路面電車を赤字を理由に廃止してしまいます。
街の中心部を活性化させるために商業施設を建設しておいて、その足となるべき交通手段は廃止してしまう。
なぜこんな相反する政策が同時に起こってしまうのか?
市民の声を聞かず、安易にコンサルの提案する他地域での「成功事例」を模倣するから、と著者は言います。
で、模倣したはずの「成功事例」もよくよく調べてみると「最初は良かったのに今は・・・」という「成功事例」のマガイモノだったりします。
読んでいると失敗の根っこは深そうです。
暗い気持ちになったところで、著者はいくつかの提言を行います。
そこで「成功事例」として取り上げられるのはいずれもささやかなもの。
しかも手間と時間、そして何より情熱や知恵がもとめられる「成功事例」です。
でも、たぶんそこにしか活路はないのでしょう。
数百億円もかけて「地域活性化の起爆剤」のハコモノを作っても発想の根っこが安易な模倣であればうまく行くはずもありません。
自分達の地域の資源をもう一度見直して自分達の力でささやかでも盛り上げていく。
「地域再生に王道は無い」といったところでしょうか。
たしょう論の甘いところや事例で「?」と感じさせるものがあって時々引っかかりましたが、新しい視点を提示できていると思います。
地域再生だけでなく、自分の仕事などいろいろなことに共通する「気づき」がある一冊でした。