2015年7月27日に発行された日本経済新聞紙の朝刊一面に掲載されたコラム「税金考 気になる光景 ビール20年戦争 技術革新世界とズレ」を拝読しました。
1995年にサントリーが初の発泡酒「ホップス」を発売したことが、ビール20年戦争の始まりでした。麦芽比率を65パーセントに抑えたことで、「ホップス」は税法上ビールでなくなり、税金が安くなり、安くてきれのある味が受けて、消費者に受け入れられ、爆発的に売れたと報じています。
日本経済新聞紙のWeb版である日本経済新聞 電子版は、見出し「(税金考) 気になる光景(2) ビール20年戦争 技術革新世界とズレ」と伝えています。
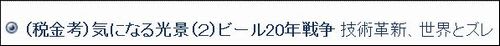
日本のビールメーカーと国税庁との“20年戦争”はまだ続いています。ビール20年戦争の原因は、ビールへの税金が高いからです。
その象徴は、サッポロビールが2017年6月22日に国税庁に対して、同社が発売する「極ゼロ」が税金の安い第三のビールでないと判定したことに異議を唱えたことです。115億円の税金の返還を求めました。
日本のビールの税率は46.6パーセントと、ドイツの約17倍だそうです。この高い税率は、日露戦争直前に戦費調達のために“贅沢品”として、課税した習慣がいまも残っているからだそうです。
この日本でのビール20年戦争の勝者はだれかを、記事は考察します。1994年に国税庁はお酒の税収入が2兆円あったのが、その後の20年で40パーセントも減ったとの分析です。国税庁は勝者ではありません・
その一方で、日本のビールメーカーの代表格であるキリンビールの株式時価発行額は、約20年前にはオランダのハイネケンの2倍近くあったもののが、現在は約30パーセントと1/3に留まっています。世界のビール最大手企業と比べると、ものすごく縮小しています。
この理由は、日本のビールなどのお酒市場が高齢化・人口減などによって、市場が縮小することが分かっていながら、新興国を軸とするグローバル市場への対応が遅れたためと分析します。日本の高いビール税率対策の技術革新に特化し、グローバル市場への対応が遅れました。
ビールという身近な商品でも、日本のグローバル市場への対応の遅れがみえるようです。
蛇足ですが、2015年7月26日発行の日本経済新聞紙の朝刊の「日曜に考える」の中に、「陰薄い財政規律派」という解説記事が載っています。自由民主党の中で、歳出削減を重視する財政規律派に元気がないと伝えます。
前回の衆議院選挙の大勝によって「官邸1強」となり、安倍晋三内閣の成長重視路線が強いからです。日本の国の借金をどのように返していくのか、国民への丁寧な説明が本当に求められています。税金を何から取るのか、国民への丁寧な説明が本当に求められています
1995年にサントリーが初の発泡酒「ホップス」を発売したことが、ビール20年戦争の始まりでした。麦芽比率を65パーセントに抑えたことで、「ホップス」は税法上ビールでなくなり、税金が安くなり、安くてきれのある味が受けて、消費者に受け入れられ、爆発的に売れたと報じています。
日本経済新聞紙のWeb版である日本経済新聞 電子版は、見出し「(税金考) 気になる光景(2) ビール20年戦争 技術革新世界とズレ」と伝えています。
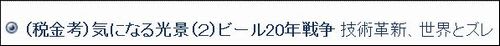
日本のビールメーカーと国税庁との“20年戦争”はまだ続いています。ビール20年戦争の原因は、ビールへの税金が高いからです。
その象徴は、サッポロビールが2017年6月22日に国税庁に対して、同社が発売する「極ゼロ」が税金の安い第三のビールでないと判定したことに異議を唱えたことです。115億円の税金の返還を求めました。
日本のビールの税率は46.6パーセントと、ドイツの約17倍だそうです。この高い税率は、日露戦争直前に戦費調達のために“贅沢品”として、課税した習慣がいまも残っているからだそうです。
この日本でのビール20年戦争の勝者はだれかを、記事は考察します。1994年に国税庁はお酒の税収入が2兆円あったのが、その後の20年で40パーセントも減ったとの分析です。国税庁は勝者ではありません・
その一方で、日本のビールメーカーの代表格であるキリンビールの株式時価発行額は、約20年前にはオランダのハイネケンの2倍近くあったもののが、現在は約30パーセントと1/3に留まっています。世界のビール最大手企業と比べると、ものすごく縮小しています。
この理由は、日本のビールなどのお酒市場が高齢化・人口減などによって、市場が縮小することが分かっていながら、新興国を軸とするグローバル市場への対応が遅れたためと分析します。日本の高いビール税率対策の技術革新に特化し、グローバル市場への対応が遅れました。
ビールという身近な商品でも、日本のグローバル市場への対応の遅れがみえるようです。
蛇足ですが、2015年7月26日発行の日本経済新聞紙の朝刊の「日曜に考える」の中に、「陰薄い財政規律派」という解説記事が載っています。自由民主党の中で、歳出削減を重視する財政規律派に元気がないと伝えます。
前回の衆議院選挙の大勝によって「官邸1強」となり、安倍晋三内閣の成長重視路線が強いからです。日本の国の借金をどのように返していくのか、国民への丁寧な説明が本当に求められています。税金を何から取るのか、国民への丁寧な説明が本当に求められています









