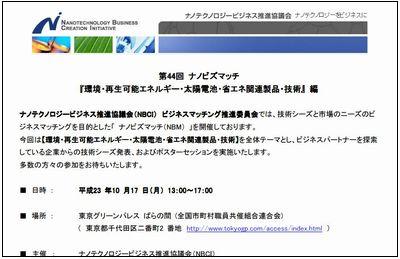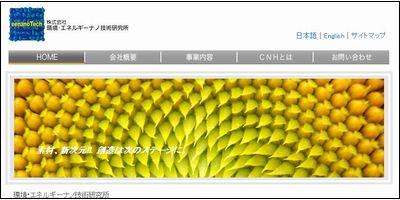ある講演会で、東京大学名誉教授の林周二さんの講演を拝聴しました。
日本を代表する経営学者、統計学者である林さんは、大学の教授や学生を前に「研究とは何か」という題名で、講演されました。2004年に単行本「研究者という職業」(発行は東京図書)を執筆され、これを読んだ学生が大学や公的研究機関の研究者(教員)になった方が多いといわれている本です。この本が講演の題名になったようです。

講演の際に、この本を紹介し、「まだ再版を重ねている」といいます。この本を含め、30数冊ほど、本を執筆されています。中央公論社が発行した中公新書「流通革命―製品・経路および消費者」は、1960年代のベストセラーだそうです。
林さんは講演の冒頭に「あと数日で84歳になる」と伝え、小学校の同級生40数人の中で寝たきりではなく、「動けるのは男性は3人しかいない」と話されました。後でWebサイトで調べてもると、林さんは1926年3月25日のお生まれでした。
70歳代は健脚で日本のアルプス級の山々を登っていたが、ある時に足に細菌が入って、片足が義足になったと説明されます。このため、かなりゆっくりと背中を丸め気味に歩かれました。
東大を定年退官後に、1987年に静岡県立大学で新設された経営情報学部の初代学部長に就任され、さらにその後は明治学院大学経済学部教授を経て、流通科学大学の特別教授をお務めになったそうです。学者として輝かしい名声を得ながら、「私は謙遜ではなく、二流の研究者」といいます。「一流の研究者はノーベル賞を取るような方」と説明し、二流との違いを“定義”されます。ただし、「二流は人まねはしない。三流は人まねをして独自性が弱い」と説明し、二流でもすごい研究者であることを匂わされます。
ご高齢ですが、話し方はとてもうまく、聞かせる講演者でした。以下、印象に残った言葉をつまみ食い的に紹介します。
「80歳代になると、友達の多くは動けない人が多くなり、知的な刺激を与えてくれない。刺激を与えてくれない友人は捨てて、年齢が若い動ける友人をつくり、刺激を受ける。友人は棚卸しして、新しい友人をつくろう」といいます。縁を大事にし、「人財を持とう」と主張されます。このため、人と会った時の「第一印象をよくするようにしている」ようです。
優れた研究者になるには、「チャンスを逃がさずつかめ」といい、「チャンスは自分でつくれ」といいます。簡単なことではありませんが、ご本人は実践した自信をお持ちのようです。

この歳でも「株を2000万円ほど、動かしていて刺激を受けている」と、結構生臭ことをさらと伝えます。大学教授時代の著作の印税で稼いだのかなと想像しました。
並の学者・研究者ではいえない内容を巧みな話術でお話しされました。ただ者ではない、イノベーターの方と思いました。
日本を代表する経営学者、統計学者である林さんは、大学の教授や学生を前に「研究とは何か」という題名で、講演されました。2004年に単行本「研究者という職業」(発行は東京図書)を執筆され、これを読んだ学生が大学や公的研究機関の研究者(教員)になった方が多いといわれている本です。この本が講演の題名になったようです。

講演の際に、この本を紹介し、「まだ再版を重ねている」といいます。この本を含め、30数冊ほど、本を執筆されています。中央公論社が発行した中公新書「流通革命―製品・経路および消費者」は、1960年代のベストセラーだそうです。
林さんは講演の冒頭に「あと数日で84歳になる」と伝え、小学校の同級生40数人の中で寝たきりではなく、「動けるのは男性は3人しかいない」と話されました。後でWebサイトで調べてもると、林さんは1926年3月25日のお生まれでした。
70歳代は健脚で日本のアルプス級の山々を登っていたが、ある時に足に細菌が入って、片足が義足になったと説明されます。このため、かなりゆっくりと背中を丸め気味に歩かれました。
東大を定年退官後に、1987年に静岡県立大学で新設された経営情報学部の初代学部長に就任され、さらにその後は明治学院大学経済学部教授を経て、流通科学大学の特別教授をお務めになったそうです。学者として輝かしい名声を得ながら、「私は謙遜ではなく、二流の研究者」といいます。「一流の研究者はノーベル賞を取るような方」と説明し、二流との違いを“定義”されます。ただし、「二流は人まねはしない。三流は人まねをして独自性が弱い」と説明し、二流でもすごい研究者であることを匂わされます。
ご高齢ですが、話し方はとてもうまく、聞かせる講演者でした。以下、印象に残った言葉をつまみ食い的に紹介します。
「80歳代になると、友達の多くは動けない人が多くなり、知的な刺激を与えてくれない。刺激を与えてくれない友人は捨てて、年齢が若い動ける友人をつくり、刺激を受ける。友人は棚卸しして、新しい友人をつくろう」といいます。縁を大事にし、「人財を持とう」と主張されます。このため、人と会った時の「第一印象をよくするようにしている」ようです。
優れた研究者になるには、「チャンスを逃がさずつかめ」といい、「チャンスは自分でつくれ」といいます。簡単なことではありませんが、ご本人は実践した自信をお持ちのようです。

この歳でも「株を2000万円ほど、動かしていて刺激を受けている」と、結構生臭ことをさらと伝えます。大学教授時代の著作の印税で稼いだのかなと想像しました。
並の学者・研究者ではいえない内容を巧みな話術でお話しされました。ただ者ではない、イノベーターの方と思いました。