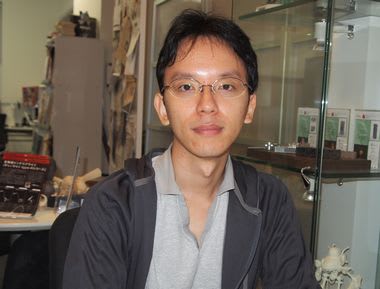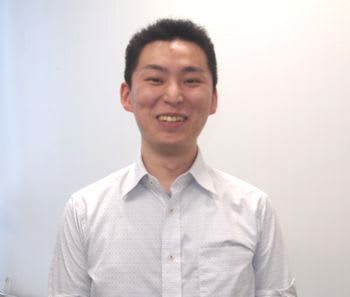産総研技術移転ベンチャー企業のライフロボティクス(茨城県つくば市)のCTO(最高技術責任者)取締役を務めている尹祐根(ゆんうぐん)さんに、あるVC(ベンチャーキャピタル)の方を通して、お目にかかりました。尹さんのお名前は英語表記だと、Woo-Keun YOONです。在日コリアン3世のご出身と、補足説明されます。
尹さんの本業は、産業技術総合研究所の知能システム研究部門サービスロボティクス研究グループの主任研究員です。

その産総研の研究開発成果を用いて、自分たちで直接、事業化を図るのが産総研技術移転ベンチャー企業の役割です。尹さんがCTO取締役を務めるライフロボティクスは、2007年12月に創業されたそうです。

現在、身体の上肢に障害のある人向けに小型軽量ロボットアーム(Robotic Arm for Persons with Upper-limb Disabilities= RAPUD)を開発し、その事業化を図っています。「RAPUD」は後に「RAPUDA」と名前を変えています。
RAPUDAは小型・軽量のロボットアームです。上肢に障害のある方が座る車イスやベットなどの側に置いて、ロボットアームを自分の思うように操作し、モノを取ったり、置いたりするなどの作業をするロボットです。


RAPUDAの特徴は、アームとハンド(把持部分)自身を合わせた可搬重量(保持、運搬できる物体の重量)が0.5 キログラムで、全体の重量約6キログラム と軽いロボットアームであることです。上肢に障害のある方自身やそのサポートの介助者の方が簡単に運べるようにするためです。「想定ユーザーは筋ジストロフィーや頸椎(けいつい)損傷を負った方々だそうです」。
尹さんは身体の上肢に障害のある人に実際に購入してもらうためには、価格を100万円以下にすることが必須と考えました。このため、「現在の産業用ロボット(垂直多関節型ロボットなど)などのような頑強な構造のままでは安くできない」と考えました。その一方で、「将来、こうした補助ロボットの安全認証を考慮して設計する必要がある」という。安全認証を取るために、「関節の動きを測るセンサーの2重化や、高信頼性通信の導入」を想定しています。
軽量でかつ廉価で、安全認証を取るという必要条件を満たすためは以下のような構造を考案しました。アームの“肘”による挟み込み事故を無くすために、屈折する“肘”部分(ジョイント箇所)を無くす構造とし、アームが伸び縮みする直動伸縮機構を採用しました。ロボットアームの自由度は7です。また、操作はゲーム機の入力機などを使えるように設計しました。上肢に障害のある人が、自分の意思で操作できるようにするためだそうです。
尹さんはRAPUDAを製品化し、身体の上肢に障害のある人に実際に使ってもらうことを考えています。一般的に、産総研の研究開発者の方は、性能最優先で設計化し製品化する方が普通でした。これに対して、尹さんはマーケッティング重視で、売れる製品を考えています(企業では当たり前のことです)。この点が、当たり前とはいえ、新鮮な驚きでした。
課題は、産総研技術移転ベンチャー企業のライフロボティクスに、事業化経験を持つCOO(最高執行責任者)の方が経営に参加することだと思いました。
尹さんの本業は、産業技術総合研究所の知能システム研究部門サービスロボティクス研究グループの主任研究員です。

その産総研の研究開発成果を用いて、自分たちで直接、事業化を図るのが産総研技術移転ベンチャー企業の役割です。尹さんがCTO取締役を務めるライフロボティクスは、2007年12月に創業されたそうです。

現在、身体の上肢に障害のある人向けに小型軽量ロボットアーム(Robotic Arm for Persons with Upper-limb Disabilities= RAPUD)を開発し、その事業化を図っています。「RAPUD」は後に「RAPUDA」と名前を変えています。
RAPUDAは小型・軽量のロボットアームです。上肢に障害のある方が座る車イスやベットなどの側に置いて、ロボットアームを自分の思うように操作し、モノを取ったり、置いたりするなどの作業をするロボットです。


RAPUDAの特徴は、アームとハンド(把持部分)自身を合わせた可搬重量(保持、運搬できる物体の重量)が0.5 キログラムで、全体の重量約6キログラム と軽いロボットアームであることです。上肢に障害のある方自身やそのサポートの介助者の方が簡単に運べるようにするためです。「想定ユーザーは筋ジストロフィーや頸椎(けいつい)損傷を負った方々だそうです」。
尹さんは身体の上肢に障害のある人に実際に購入してもらうためには、価格を100万円以下にすることが必須と考えました。このため、「現在の産業用ロボット(垂直多関節型ロボットなど)などのような頑強な構造のままでは安くできない」と考えました。その一方で、「将来、こうした補助ロボットの安全認証を考慮して設計する必要がある」という。安全認証を取るために、「関節の動きを測るセンサーの2重化や、高信頼性通信の導入」を想定しています。
軽量でかつ廉価で、安全認証を取るという必要条件を満たすためは以下のような構造を考案しました。アームの“肘”による挟み込み事故を無くすために、屈折する“肘”部分(ジョイント箇所)を無くす構造とし、アームが伸び縮みする直動伸縮機構を採用しました。ロボットアームの自由度は7です。また、操作はゲーム機の入力機などを使えるように設計しました。上肢に障害のある人が、自分の意思で操作できるようにするためだそうです。
尹さんはRAPUDAを製品化し、身体の上肢に障害のある人に実際に使ってもらうことを考えています。一般的に、産総研の研究開発者の方は、性能最優先で設計化し製品化する方が普通でした。これに対して、尹さんはマーケッティング重視で、売れる製品を考えています(企業では当たり前のことです)。この点が、当たり前とはいえ、新鮮な驚きでした。
課題は、産総研技術移転ベンチャー企業のライフロボティクスに、事業化経験を持つCOO(最高執行責任者)の方が経営に参加することだと思いました。