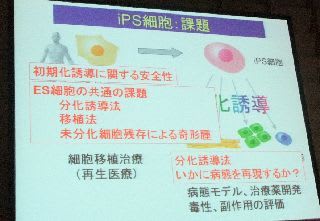日本のベンチャー企業の代表的な成功例であるザインエレクトロニクスの飯塚哲哉代表取締役社長にお話を伺いました。東京駅の八重洲側に立つ高層ビル内のオフィスをお訪ねしました。最近引っ越したばかりのきれいなオフォスでした。
同社は資本金が約11億7500万円、平成20年(1月~12月)の業績(連結)は売上高97億2000万円、経常利益7億6400万円の優れた中堅企業です。会社の規模はまだ小粒ですが、研究開発に特化した成長率が高いエクセレントカンパニーです。
飯塚さんは、「日本でベンチャー企業がなかなか成功しない理由は、面白い仕事を求めて転職するという人材流動があまり起こっていないため」と分析します。

日本人の多くは“就社”します。入社する会社そのものにこだわり、自分がどんな仕事をするかにはあまりこだわらないのが問題といいます。本当は「自分の能力を活かす“就職”を目指した方が、自分が好きな仕事ができるのに」と続けます。自分が好きな仕事に従事すれば「その仕事にのめり込み、成果を達成すれば、満足感や幸福感が味わえる」といいます。このことを、飯塚さんは「人資豊燃」という造語の四文字熟語で表現しています。
1991年5月にベンチャー企業のザイン・マイクロシステム研究所を茨城県つくば市に設立しました。飯塚さんは東芝の半導体技術研究所でLSI開発部長の要職を担う優秀な技術者でした。部長職は、部を運営するマネジメントが主な仕事でした。自分でベンチャー企業を起こして経営者としてマネジメントに励むのと、大手電気メーカーの部長職のマネジメントはどこが違うのか迷った末に、創業資金をたまたま確保できたことから起業します。最初は半導体の設計業務を委託するコンサルティングを仕事にしたそうです。
この時に、日本の大手企業の経営者や社員は「ベンチャー企業の重要性を理解していないことを痛感した」そうです。半導体の設計業務の委託の仕事を獲得するために、売り込みに行くと、小さな会社であるという理由で相手にしない方もいました。東芝の元同僚も、大手企業を飛び出してベンチャー企業を創業した飯塚さんに「何かあったのか」「何が不満だったのか」と心配してくれることに、逆に驚いたそうです。「自分で納得のいく好きな仕事をするだけの理由で、ベンチャー企業を創業しただけなのに」といいます。
研究開発型のベンチャー企業だけに、優秀な技術者が必要です。創業直後は知名度がないため、人材確保に苦労したとのことでした。半導体を企画し、設計し、製造をマネジメントでき、販売計画も立てられるという優秀な技術者が必要だったからです。半導体製品のプロデュースできる人材はそう簡単には見つかりません。大手企業は工程ごとに分担し分業しているから、工程全体を見通せる人材はあまりいないのです。
92年にザインエレクトロニクスを創業します。今度はオフィスを、東京都中央区八重洲という地の利のいい場所にしました。当初は韓国の三星電子(現在のサムソン電子)との合弁会社として設立しました。その後、合弁を解消し、独自のビジネスモデルを築いて成功します。90年代後半は日本の大手電気メーカーは液晶ディスプレー(LCD)の事業化を精力的に進めました。その画像データを高速伝送するIC(半導体の集積回路)を企画し、「各企業が別々に設計し、それぞれ製造するよりも、高性能で低価格な製品を供給する」と各社に提案し、受注します。個別に研究開発するよりは、ザインがまとめて設計した方が安上がりです。ザインは台湾や韓国の“ファウンドリー”と呼ばれる製造請負企業にその製品の製造を委託します。まとめてつくった方が安く済みます。問題は、品質保証です。優れた品質保証マネジメントを行い、クライアントの信頼を勝ち取ります。この製品はザインブランドの独自製品であり、世界の80%のシェアを勝ち取った製品も誕生しました。

このビジネスモデルのカギは、各社が共通してほしがる半導体製品を提案し、優れた性能を持ちながら各社が自分でつくるよりは低コストで供給する製品企画力です。こうした製品の企画から販売までの一連の工程をマネジメントできる優秀な技術者はそんなに多くはいません。日本は分業制が発達しており、事業全体を見通す能力を持つ方は少数派です。
日本の大手電気メーカーは最近は事業不振、事業収益の低下で悩んでいます。ザインのようなベンチャー企業と巧みにアライアンスを組み、韓国や台湾の“ファウンドリー”と呼ばれる製造請負企業(広義にはEMS=Electronics Manufacturing Serviceとも呼ばれ、電子機器の受託生産を行う)とも水平分業する仕組みを考えることも重要になっています。重要といわれて部分的には水平分業を始めていますが、まだあまり成功していないようです。
会社規模は小さくても自分の好きな仕事をするために、ベンチャー企業に就職することも重要な選択肢になっています。あるいは、自分でベンチャー企業を創業することも大切な選択肢です。自分の人生を自分で設計することが大切です。
同社は資本金が約11億7500万円、平成20年(1月~12月)の業績(連結)は売上高97億2000万円、経常利益7億6400万円の優れた中堅企業です。会社の規模はまだ小粒ですが、研究開発に特化した成長率が高いエクセレントカンパニーです。
飯塚さんは、「日本でベンチャー企業がなかなか成功しない理由は、面白い仕事を求めて転職するという人材流動があまり起こっていないため」と分析します。

日本人の多くは“就社”します。入社する会社そのものにこだわり、自分がどんな仕事をするかにはあまりこだわらないのが問題といいます。本当は「自分の能力を活かす“就職”を目指した方が、自分が好きな仕事ができるのに」と続けます。自分が好きな仕事に従事すれば「その仕事にのめり込み、成果を達成すれば、満足感や幸福感が味わえる」といいます。このことを、飯塚さんは「人資豊燃」という造語の四文字熟語で表現しています。
1991年5月にベンチャー企業のザイン・マイクロシステム研究所を茨城県つくば市に設立しました。飯塚さんは東芝の半導体技術研究所でLSI開発部長の要職を担う優秀な技術者でした。部長職は、部を運営するマネジメントが主な仕事でした。自分でベンチャー企業を起こして経営者としてマネジメントに励むのと、大手電気メーカーの部長職のマネジメントはどこが違うのか迷った末に、創業資金をたまたま確保できたことから起業します。最初は半導体の設計業務を委託するコンサルティングを仕事にしたそうです。
この時に、日本の大手企業の経営者や社員は「ベンチャー企業の重要性を理解していないことを痛感した」そうです。半導体の設計業務の委託の仕事を獲得するために、売り込みに行くと、小さな会社であるという理由で相手にしない方もいました。東芝の元同僚も、大手企業を飛び出してベンチャー企業を創業した飯塚さんに「何かあったのか」「何が不満だったのか」と心配してくれることに、逆に驚いたそうです。「自分で納得のいく好きな仕事をするだけの理由で、ベンチャー企業を創業しただけなのに」といいます。
研究開発型のベンチャー企業だけに、優秀な技術者が必要です。創業直後は知名度がないため、人材確保に苦労したとのことでした。半導体を企画し、設計し、製造をマネジメントでき、販売計画も立てられるという優秀な技術者が必要だったからです。半導体製品のプロデュースできる人材はそう簡単には見つかりません。大手企業は工程ごとに分担し分業しているから、工程全体を見通せる人材はあまりいないのです。
92年にザインエレクトロニクスを創業します。今度はオフィスを、東京都中央区八重洲という地の利のいい場所にしました。当初は韓国の三星電子(現在のサムソン電子)との合弁会社として設立しました。その後、合弁を解消し、独自のビジネスモデルを築いて成功します。90年代後半は日本の大手電気メーカーは液晶ディスプレー(LCD)の事業化を精力的に進めました。その画像データを高速伝送するIC(半導体の集積回路)を企画し、「各企業が別々に設計し、それぞれ製造するよりも、高性能で低価格な製品を供給する」と各社に提案し、受注します。個別に研究開発するよりは、ザインがまとめて設計した方が安上がりです。ザインは台湾や韓国の“ファウンドリー”と呼ばれる製造請負企業にその製品の製造を委託します。まとめてつくった方が安く済みます。問題は、品質保証です。優れた品質保証マネジメントを行い、クライアントの信頼を勝ち取ります。この製品はザインブランドの独自製品であり、世界の80%のシェアを勝ち取った製品も誕生しました。

このビジネスモデルのカギは、各社が共通してほしがる半導体製品を提案し、優れた性能を持ちながら各社が自分でつくるよりは低コストで供給する製品企画力です。こうした製品の企画から販売までの一連の工程をマネジメントできる優秀な技術者はそんなに多くはいません。日本は分業制が発達しており、事業全体を見通す能力を持つ方は少数派です。
日本の大手電気メーカーは最近は事業不振、事業収益の低下で悩んでいます。ザインのようなベンチャー企業と巧みにアライアンスを組み、韓国や台湾の“ファウンドリー”と呼ばれる製造請負企業(広義にはEMS=Electronics Manufacturing Serviceとも呼ばれ、電子機器の受託生産を行う)とも水平分業する仕組みを考えることも重要になっています。重要といわれて部分的には水平分業を始めていますが、まだあまり成功していないようです。
会社規模は小さくても自分の好きな仕事をするために、ベンチャー企業に就職することも重要な選択肢になっています。あるいは、自分でベンチャー企業を創業することも大切な選択肢です。自分の人生を自分で設計することが大切です。