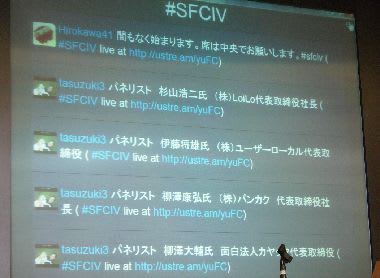東京大学発ベンチャー企業のアドバンスト・ソフトマテリアル(ASM、千葉県柏市)は、非常に柔らかくて、かつ永久歪み量が極めて小さいという夢のような性質を持つ新型エラストマー「セルム・エラストマー」シリーズを販売し始めました。
“エラストマー”というと、あまり馴染みがない小難しい材料名ですが、その代表例は合成ゴムです。ウレタン系(一部)やシリコーン系、フッ素系などの優れた弾性を持つプラスチックの総称です。例えば、パッキングなど、高い弾性が必要な用途に適用されています。
アドバンスト・ソフトマテリアルの代表取締役社長を務められている原豊さんは「今回、発売した新型エラストマーは、何回伸び縮みなどの変形を与えても、まったくへたらないのが特徴です。つまり、常に新品同様に戻るということです」といいます。「エラストマーの専門家ほど、常識を覆すような、そのへたらない性質に驚くだろう」と説明します。

主な用途は振動保護や制震、防音、衝撃吸収向け材料などです。透明性も高いので、ソフトな光学用途も期待されています。

新型エラストマーが驚異的な独特の性質を発揮する仕組みは、「スライドリングマテリアル」(Slide-Ring Material)という特異な高分子の構造を持っているからです。スライドリングマテリアルとは、“機軸”となる細長い高分子の中に、リング形状の環状分子をネックレスのように通した独自の分子構造を持つものです。

こんな不思議な構造の高分子は、研究室のビーカーの中には存在しましたが、実際に実用化されるのは、おそらく初めてです。
原さんは「リング部分が滑車のように滑ることで、さまざまな性質を発揮する」といいます。また、「リング形状の環状分子が互いに反発しあう“空気バネ”のような効果も効いている」と説明します。
多少、専門的な説明を加えると、セルム・エラストマーシリーズは、無溶媒・1液型エラストマーの熱硬化性樹脂です。そして“生地”(基材)として販売され始めました。振動保護や制震、防音、衝撃吸収向けの材料に適用するには、各ユーザーが生地を各自の用途仕様に合わせるように調整するのです。「溶媒希釈を前提とした2液混合型の生地も、求めがあれば提供できる」とも説明します。
アドバンスト・ソフトマテリアルは、2010年10月に大手化学メーカーの宇部興産と、スライドリングマテリアルの事業化に関する包括的提携を締結済みです。「事業化を促進するマーケティングや製品企画・開発などの面で包括提携しました」と、包括提携内容を説明されます。ベンチャー企業の先進的で挑戦的な新規事業と、大手の総合化学メーカーの連携こそが、これからの日本の大手企業が採用すべき新規事業起こしの常道です。アドバンスト・ソフトマテリアルと宇部興産との提携は、是非、日本でのいいお手本になってほしいと思います。今回発売した「セルム・エラストマー」シリーズは、宇部興産との包括的な提携が効果を上げていると推定されます。
スライドリングマテリアルは、アドバンスト・ソフトマテリアルの取締役を務められている、東大大学院新領域創成科学研究科教授(当時は助教授)の伊藤耕三さんの研究成果です。2000年当時の研究成果がコア技術になっているようです。このスライドリングマテリアルの研究成果を事業化する目的で、2005年3月にベンチャー企業としてアドバンスト・ソフトマテリアルが設立されましたた。スライドリングマテリアルの基本特許は、日本、米国、欧州、中国などで既にそれぞれ成立済みだそうです。
アドバンスト・ソフトマテリアルは、東京大学系のベンチャーキャピタル(VC)である東京大学エッジキャピタル(UTEC、東京都文京区)から投資を受け、順調に成長しています。実際の事業化は、NTTドコモの携帯電話機の傷つきにくい塗装材料でしたが、量的にはあまり伸びていなかったようです。この点で、今回のエラストマーの事業は、アドバンスト・ソフトマテリアルが本格的に成長する原動力になるとの期待が高まっています。新材料系のベンチャー企業の成功事例は世界的にもあまりなかっただけに、成功が期待されています。
“エラストマー”というと、あまり馴染みがない小難しい材料名ですが、その代表例は合成ゴムです。ウレタン系(一部)やシリコーン系、フッ素系などの優れた弾性を持つプラスチックの総称です。例えば、パッキングなど、高い弾性が必要な用途に適用されています。
アドバンスト・ソフトマテリアルの代表取締役社長を務められている原豊さんは「今回、発売した新型エラストマーは、何回伸び縮みなどの変形を与えても、まったくへたらないのが特徴です。つまり、常に新品同様に戻るということです」といいます。「エラストマーの専門家ほど、常識を覆すような、そのへたらない性質に驚くだろう」と説明します。

主な用途は振動保護や制震、防音、衝撃吸収向け材料などです。透明性も高いので、ソフトな光学用途も期待されています。

新型エラストマーが驚異的な独特の性質を発揮する仕組みは、「スライドリングマテリアル」(Slide-Ring Material)という特異な高分子の構造を持っているからです。スライドリングマテリアルとは、“機軸”となる細長い高分子の中に、リング形状の環状分子をネックレスのように通した独自の分子構造を持つものです。

こんな不思議な構造の高分子は、研究室のビーカーの中には存在しましたが、実際に実用化されるのは、おそらく初めてです。
原さんは「リング部分が滑車のように滑ることで、さまざまな性質を発揮する」といいます。また、「リング形状の環状分子が互いに反発しあう“空気バネ”のような効果も効いている」と説明します。
多少、専門的な説明を加えると、セルム・エラストマーシリーズは、無溶媒・1液型エラストマーの熱硬化性樹脂です。そして“生地”(基材)として販売され始めました。振動保護や制震、防音、衝撃吸収向けの材料に適用するには、各ユーザーが生地を各自の用途仕様に合わせるように調整するのです。「溶媒希釈を前提とした2液混合型の生地も、求めがあれば提供できる」とも説明します。
アドバンスト・ソフトマテリアルは、2010年10月に大手化学メーカーの宇部興産と、スライドリングマテリアルの事業化に関する包括的提携を締結済みです。「事業化を促進するマーケティングや製品企画・開発などの面で包括提携しました」と、包括提携内容を説明されます。ベンチャー企業の先進的で挑戦的な新規事業と、大手の総合化学メーカーの連携こそが、これからの日本の大手企業が採用すべき新規事業起こしの常道です。アドバンスト・ソフトマテリアルと宇部興産との提携は、是非、日本でのいいお手本になってほしいと思います。今回発売した「セルム・エラストマー」シリーズは、宇部興産との包括的な提携が効果を上げていると推定されます。
スライドリングマテリアルは、アドバンスト・ソフトマテリアルの取締役を務められている、東大大学院新領域創成科学研究科教授(当時は助教授)の伊藤耕三さんの研究成果です。2000年当時の研究成果がコア技術になっているようです。このスライドリングマテリアルの研究成果を事業化する目的で、2005年3月にベンチャー企業としてアドバンスト・ソフトマテリアルが設立されましたた。スライドリングマテリアルの基本特許は、日本、米国、欧州、中国などで既にそれぞれ成立済みだそうです。
アドバンスト・ソフトマテリアルは、東京大学系のベンチャーキャピタル(VC)である東京大学エッジキャピタル(UTEC、東京都文京区)から投資を受け、順調に成長しています。実際の事業化は、NTTドコモの携帯電話機の傷つきにくい塗装材料でしたが、量的にはあまり伸びていなかったようです。この点で、今回のエラストマーの事業は、アドバンスト・ソフトマテリアルが本格的に成長する原動力になるとの期待が高まっています。新材料系のベンチャー企業の成功事例は世界的にもあまりなかっただけに、成功が期待されています。