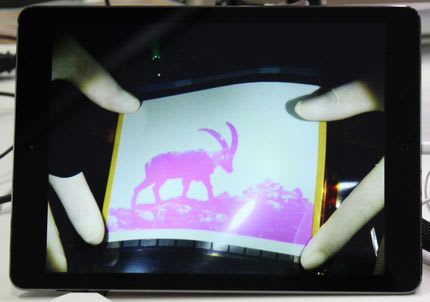今週、東京都内で開催された「元素戦略/希少金属代替材料開発 第8回合同シンポジウム」という材料系のシンポジウムを拝聴した話の続きです。
文部科学省・科学技術振興機構(JST)が推進している元素戦略プロジェクトは、希少金属元素(レアメタル元素)を使わずに、同等の性質・機能を発揮する新物質を探索する研究開発プロジェクトです。実現性がやや難しい研究開発テーマに挑戦していますが、もし実現すれば“破壊的イノベーション”を起こす可能性を秘めています。
今回の元素戦略プロジェクトの研究開発成果の中では、九州大学などの4者が共同で研究開発しているNa(ナトリウム)イオン2次電池の話に興味を持ちました。
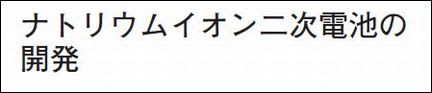
上記は、住友化学の技報に掲載された表紙の一部です。住友化学はLi(リチウム)イオン2次電池の負極になる炭素材料を研究開発してきました。その研究開発成果をNaイオン2次電池の基盤研究に生かしています。
Naイオン2次電池は現在利用されているLiイオン2次電池に似た仕組みの電池です。“2次電池”とは充電可能で、繰り返し使える電池のことです。
Liイオン2次電池は携帯用パソコンやスマートフォン・携帯電話機などの電池に幅広く使われています。今後、電気自動車などの普及が本格化し、Liイオン2次電池の需要が急激に増えると、現在、南米のボリビアなどで採取しているLi資源の採掘能力が需要に追いつかなくなるリスクが高まると予測されています。このため、Liイオン2次電池の一部をNaイオン2次電池で補足しようという研究開発を進めているそうです。
今回の九州大学などの4者の研究開発体制は、九州大学先導物質化学研究所がNaイオン2次電池の正極材料を、住友化学筑波開発研究所が負極材料を、山口大学と日本大学が電解質の開発をそれぞれ担当し、4者共同でプロトタイプ電池としての充放電挙動を確認するというものです。
2次電池反応の主役を担うNaイオンは、Liイオンに比べてイオン半径がかなり大きいために、Naイオンが出入りする正極と負極の物質探しが行われました。正極材料の探索を担当した九州大学はCo(コバルト)などのレアメタルを含まない正極材料を探索し、有力候補材料としてNa3V2(PO4)2F3(ナトリウム・バナジウム・リン、酸素、フッ素の複雑な化合物、数字は下添え字です)などの数種類の正極材料候補を見いだし、Naイオン動作を調べたそうです。
負極材料を担当した住友化学は“多孔性難黒鉛化炭素材料”として、1600℃で熱処理した「C1600」というハードカーボン系が使えることを見いだし、充放電動作でのNaイオンの可逆性を確認したそうです。問題になる金属Naの析出がないことを確認しています。
山口大学と日本大学は非水溶媒イオン液体混合電解液の研究開発を担当しました。とても複雑な物質の混合物なので中身は省略します。Liイオン2次電池での電解液の知識が基盤になっているようです。
九州大学などの4者は研究開発成果である正極材料、負極材料、電解液を用いてプロトタイプ電池を構成し、ある電流での室温・可逆反応を確認したそうです。過充電耐性試験を行い「破裂・発火現象が起こらないことを確認した」そうです。
今回の研究開発成果をさらに進めて将来、水溶液系電解液を用いたNaイオン2次電池が実用化できれば、「Liイオン2次電池に比べて、かなり低コストなNaイオン2次電池が登場する」と、九州大学先導物質化学研究所の研究者は説明します。
たぶん、まだいろいろな困難が待っていると思いますが、こうした研究開発過程からまた興味深い新物質・材料が誕生しそうです。
文部科学省・科学技術振興機構(JST)が推進している元素戦略プロジェクトは、希少金属元素(レアメタル元素)を使わずに、同等の性質・機能を発揮する新物質を探索する研究開発プロジェクトです。実現性がやや難しい研究開発テーマに挑戦していますが、もし実現すれば“破壊的イノベーション”を起こす可能性を秘めています。
今回の元素戦略プロジェクトの研究開発成果の中では、九州大学などの4者が共同で研究開発しているNa(ナトリウム)イオン2次電池の話に興味を持ちました。
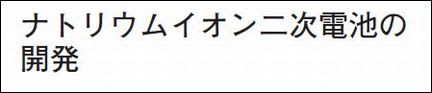
上記は、住友化学の技報に掲載された表紙の一部です。住友化学はLi(リチウム)イオン2次電池の負極になる炭素材料を研究開発してきました。その研究開発成果をNaイオン2次電池の基盤研究に生かしています。
Naイオン2次電池は現在利用されているLiイオン2次電池に似た仕組みの電池です。“2次電池”とは充電可能で、繰り返し使える電池のことです。
Liイオン2次電池は携帯用パソコンやスマートフォン・携帯電話機などの電池に幅広く使われています。今後、電気自動車などの普及が本格化し、Liイオン2次電池の需要が急激に増えると、現在、南米のボリビアなどで採取しているLi資源の採掘能力が需要に追いつかなくなるリスクが高まると予測されています。このため、Liイオン2次電池の一部をNaイオン2次電池で補足しようという研究開発を進めているそうです。
今回の九州大学などの4者の研究開発体制は、九州大学先導物質化学研究所がNaイオン2次電池の正極材料を、住友化学筑波開発研究所が負極材料を、山口大学と日本大学が電解質の開発をそれぞれ担当し、4者共同でプロトタイプ電池としての充放電挙動を確認するというものです。
2次電池反応の主役を担うNaイオンは、Liイオンに比べてイオン半径がかなり大きいために、Naイオンが出入りする正極と負極の物質探しが行われました。正極材料の探索を担当した九州大学はCo(コバルト)などのレアメタルを含まない正極材料を探索し、有力候補材料としてNa3V2(PO4)2F3(ナトリウム・バナジウム・リン、酸素、フッ素の複雑な化合物、数字は下添え字です)などの数種類の正極材料候補を見いだし、Naイオン動作を調べたそうです。
負極材料を担当した住友化学は“多孔性難黒鉛化炭素材料”として、1600℃で熱処理した「C1600」というハードカーボン系が使えることを見いだし、充放電動作でのNaイオンの可逆性を確認したそうです。問題になる金属Naの析出がないことを確認しています。
山口大学と日本大学は非水溶媒イオン液体混合電解液の研究開発を担当しました。とても複雑な物質の混合物なので中身は省略します。Liイオン2次電池での電解液の知識が基盤になっているようです。
九州大学などの4者は研究開発成果である正極材料、負極材料、電解液を用いてプロトタイプ電池を構成し、ある電流での室温・可逆反応を確認したそうです。過充電耐性試験を行い「破裂・発火現象が起こらないことを確認した」そうです。
今回の研究開発成果をさらに進めて将来、水溶液系電解液を用いたNaイオン2次電池が実用化できれば、「Liイオン2次電池に比べて、かなり低コストなNaイオン2次電池が登場する」と、九州大学先導物質化学研究所の研究者は説明します。
たぶん、まだいろいろな困難が待っていると思いますが、こうした研究開発過程からまた興味深い新物質・材料が誕生しそうです。