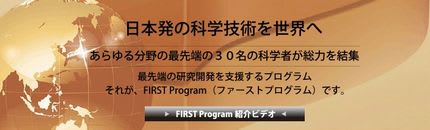京都大学は2014年1月22日に、パラジウム(Pd)とルテニウム(Ru)が原子レベルで混ざり合った新しい合金“人工ロジウム(Rh)”の開発に成功したと、発表しました。京都大大学院理学研究科の北川宏教授の研究グループの研究成果です。
この革新的な研究成果のお話を最近、北川宏教授が解説する講演として拝聴しました。
今回開発したパラジウムとルテニウムが原子レベルで混じり合った合金は、この二つの金属元素の周期表の間にあるロジウム(Rh)元素にかなり近い電子状態を持つために「化学的性質がロジウムに近いので“人工ロジウム”になる」という、現代の“錬金術”のような研究成果です。パラジウムとルテニウムは温度を2000度(摂氏)まで上げて、液相にしても相分離してしまうために、従来の溶かして合金にする製造法では合金にはならない貴金属元素同士です。

パラジウムとルテニウムの合金は、高価な“貴金属”類のロジウムよりも安く「現在の市況で約3分の1程度になるために、安価なRh代替品として利用できる可能性がある」と説明します。
パラジウムとルテニウムの合金のつくり方は具体的には、還元剤としてトリエチレングリコールを、保護材としてポリビニルピロリドン(PVP)を混合した溶液(温度200℃)に、パラジウム源として塩化パラジウム・カリウム水溶液〔K2(PdCl4)〕と塩化ルテニウム水溶液〔RuCl3〕〔塩化ルテニウム〕をゆっくりと混合すると、PdxRu1-x(xは変数)という組成の粒径が10ナノメートル以下の微粒子が作成できるそうです。
このパラジウムとルテニウムの合金の微粒子も模式図(下図の右側)を見ると、原子同士で混じり合っています。

この合金微粒子の模式図は、走査型・透過電子顕微鏡(STEM)高角散乱環状暗視野などでの元素マッピングからパラジウム(結晶構造が六方最密構造)とルテニウム(結晶構造が面心立方構造)が原子レベルで混じり合った固溶体になっていることが明らかになったそうです。錬金術師が直感的に考えることと、結果は偶然、一致したことになりまうs。
現在、ロジウムは自動車の排ガス(ガソリンエンジン)に含まれている炭化水素や一酸化炭素(CO)、窒素酸化物(NOx)を除去する触媒(三元触媒)として利用されています。
今回開発したパラジウムとルテニウムの合金も、一酸化炭素を二酸化炭素にして酸化除去する触媒としての性能が高いことが示されました。さらに、最近は窒素酸化物(NOx)を窒素ガス(N2)とO2(酸素ガス)に還元する触媒機能を持っていることも発見したそうです。
互いに溶け合わないパラジウムとルテニウムでは、パラジウムが水素(H)と反応してパラジウム水素化物になると「まったく別の白金族元素のように振る舞うために、ルテニウムと固溶するようになると、固溶する仕組みを推定している」と、北川教授は説明しています。そして「その後、パラジウム水素化物が水素を放出すると、そのまま、パラジウムとルテニウムが固溶し合った状態の準安定相として残る」とのことです。「この準安定相は約500℃まで安定しているので、実用品として利用可能な温度範囲にあるといえる」と説明します。
不思議な人工ロジウム合金の話でした。
この革新的な研究成果のお話を最近、北川宏教授が解説する講演として拝聴しました。
今回開発したパラジウムとルテニウムが原子レベルで混じり合った合金は、この二つの金属元素の周期表の間にあるロジウム(Rh)元素にかなり近い電子状態を持つために「化学的性質がロジウムに近いので“人工ロジウム”になる」という、現代の“錬金術”のような研究成果です。パラジウムとルテニウムは温度を2000度(摂氏)まで上げて、液相にしても相分離してしまうために、従来の溶かして合金にする製造法では合金にはならない貴金属元素同士です。

パラジウムとルテニウムの合金は、高価な“貴金属”類のロジウムよりも安く「現在の市況で約3分の1程度になるために、安価なRh代替品として利用できる可能性がある」と説明します。
パラジウムとルテニウムの合金のつくり方は具体的には、還元剤としてトリエチレングリコールを、保護材としてポリビニルピロリドン(PVP)を混合した溶液(温度200℃)に、パラジウム源として塩化パラジウム・カリウム水溶液〔K2(PdCl4)〕と塩化ルテニウム水溶液〔RuCl3〕〔塩化ルテニウム〕をゆっくりと混合すると、PdxRu1-x(xは変数)という組成の粒径が10ナノメートル以下の微粒子が作成できるそうです。
このパラジウムとルテニウムの合金の微粒子も模式図(下図の右側)を見ると、原子同士で混じり合っています。

この合金微粒子の模式図は、走査型・透過電子顕微鏡(STEM)高角散乱環状暗視野などでの元素マッピングからパラジウム(結晶構造が六方最密構造)とルテニウム(結晶構造が面心立方構造)が原子レベルで混じり合った固溶体になっていることが明らかになったそうです。錬金術師が直感的に考えることと、結果は偶然、一致したことになりまうs。
現在、ロジウムは自動車の排ガス(ガソリンエンジン)に含まれている炭化水素や一酸化炭素(CO)、窒素酸化物(NOx)を除去する触媒(三元触媒)として利用されています。
今回開発したパラジウムとルテニウムの合金も、一酸化炭素を二酸化炭素にして酸化除去する触媒としての性能が高いことが示されました。さらに、最近は窒素酸化物(NOx)を窒素ガス(N2)とO2(酸素ガス)に還元する触媒機能を持っていることも発見したそうです。
互いに溶け合わないパラジウムとルテニウムでは、パラジウムが水素(H)と反応してパラジウム水素化物になると「まったく別の白金族元素のように振る舞うために、ルテニウムと固溶するようになると、固溶する仕組みを推定している」と、北川教授は説明しています。そして「その後、パラジウム水素化物が水素を放出すると、そのまま、パラジウムとルテニウムが固溶し合った状態の準安定相として残る」とのことです。「この準安定相は約500℃まで安定しているので、実用品として利用可能な温度範囲にあるといえる」と説明します。
不思議な人工ロジウム合金の話でした。