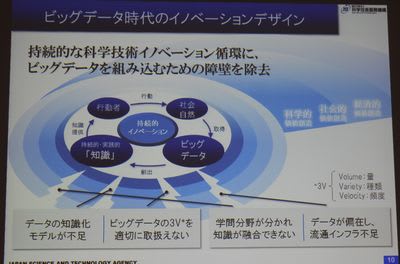岩手県盛岡市で開催されたシンポジウム「震災復興に産学官連携か果たす役割」を拝聴しました。
そのシンポジウムにパネリストとして登場した東北大学大学院教授の堀切川一男さんのプレゼンテーションを拝聴しました。通称、“堀切川仙台モデル”と呼ばれる産学官連携事例を軽妙に話されました。

仙台市では、牛タンに続く地元の名物として、新鮮な魚貝類を載せる“ズケ丼”の考案者が掘切川さんであるという“まくら話”からプレゼンが始まりました。
東北大学大学院の工学研究科の教授である堀切川さんは、潤滑技術・潤滑材料の機械技術の専門家です。堀切川さんは、以前に勤務していた山形大学で、この潤滑材を基にした産学連携による事業化で成功した経緯が有名になりました。このために、山形大学から東北大学に移籍する際に、その移籍に反対する山形市民が登場したという伝説の持ち主です。
堀切川さんは、実現性が高い産学連携事例は、企業が多数持っている製品化・事業化の失敗事例をヒアリングすることが出発点になると主張します。特に、地元の中小企業の新製品開発・新規事業開発を支援するさには、「その企業の製品化・事業化の失敗事例を聞き出し、その失敗させた原因を追究することが出発点になる」と主張します。
つまり、従来の産学連携でいわれた、大学の独創的な研究成果というシーズを基に、企業がユーザーニーズを探って新製品開発・新規事業開発するのは、優秀な研究開発部門を持つ大手企業でないと難しいとの分析のようです。
当該企業が以前に失敗したり製品化・事業化の失敗事例を聞き出し「これを出発点に問題解決とその製品性能評価などを大学の教員が受け持ち、問題点を解決することで、製品化・事業化に成功する」と主張します。その新製品の販路確保では行政の力も借りることも有効と解説します。
こうした新製品開発では、つかんだものが滑り落ちない箸(はし)、滑りにくいスリッパや作業靴の底のゴムなどがあると、実例を示します。起き上がりこぶしの原理を盛り込んだ日本酒や焼酎などを飲むぐい飲み風の食器などの実例を紹介します。
「製品化・事業化では最初の開発目標を低めに設定し、新製品として開発したものをユーザーニーズに応じて改良していく方が製品化・事業化に成功しやすい」と、体験談を軽妙に語ります。
まとめとして「地域に根ざし、世界を目指す研究・夢の実現を目指した研究」を語りました。

それぞれの製品化事例の事例ケースの話があちこちに飛びながら、その一つひとつの事例が興味深いものでした。
現在、開発した新製品の販路を確保するために、各地にある“道の駅”に販売コーナーを設けて、道の駅から口コミで評判が広がることを企画しているそうです。
堀切川さんの講演内容はプレゼンテーションとして第一級のものでした。
そのシンポジウムにパネリストとして登場した東北大学大学院教授の堀切川一男さんのプレゼンテーションを拝聴しました。通称、“堀切川仙台モデル”と呼ばれる産学官連携事例を軽妙に話されました。

仙台市では、牛タンに続く地元の名物として、新鮮な魚貝類を載せる“ズケ丼”の考案者が掘切川さんであるという“まくら話”からプレゼンが始まりました。
東北大学大学院の工学研究科の教授である堀切川さんは、潤滑技術・潤滑材料の機械技術の専門家です。堀切川さんは、以前に勤務していた山形大学で、この潤滑材を基にした産学連携による事業化で成功した経緯が有名になりました。このために、山形大学から東北大学に移籍する際に、その移籍に反対する山形市民が登場したという伝説の持ち主です。
堀切川さんは、実現性が高い産学連携事例は、企業が多数持っている製品化・事業化の失敗事例をヒアリングすることが出発点になると主張します。特に、地元の中小企業の新製品開発・新規事業開発を支援するさには、「その企業の製品化・事業化の失敗事例を聞き出し、その失敗させた原因を追究することが出発点になる」と主張します。
つまり、従来の産学連携でいわれた、大学の独創的な研究成果というシーズを基に、企業がユーザーニーズを探って新製品開発・新規事業開発するのは、優秀な研究開発部門を持つ大手企業でないと難しいとの分析のようです。
当該企業が以前に失敗したり製品化・事業化の失敗事例を聞き出し「これを出発点に問題解決とその製品性能評価などを大学の教員が受け持ち、問題点を解決することで、製品化・事業化に成功する」と主張します。その新製品の販路確保では行政の力も借りることも有効と解説します。
こうした新製品開発では、つかんだものが滑り落ちない箸(はし)、滑りにくいスリッパや作業靴の底のゴムなどがあると、実例を示します。起き上がりこぶしの原理を盛り込んだ日本酒や焼酎などを飲むぐい飲み風の食器などの実例を紹介します。
「製品化・事業化では最初の開発目標を低めに設定し、新製品として開発したものをユーザーニーズに応じて改良していく方が製品化・事業化に成功しやすい」と、体験談を軽妙に語ります。
まとめとして「地域に根ざし、世界を目指す研究・夢の実現を目指した研究」を語りました。

それぞれの製品化事例の事例ケースの話があちこちに飛びながら、その一つひとつの事例が興味深いものでした。
現在、開発した新製品の販路を確保するために、各地にある“道の駅”に販売コーナーを設けて、道の駅から口コミで評判が広がることを企画しているそうです。
堀切川さんの講演内容はプレゼンテーションとして第一級のものでした。