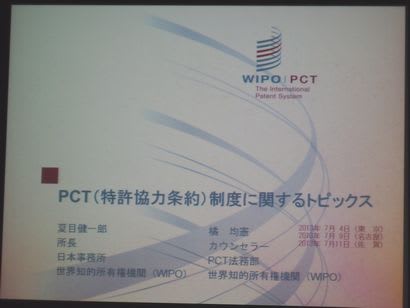宇宙航空研究開発機構(JAXA)が2013年8月27日13時45分に打ち上げを予定していた固体燃料ロケットの「イプシロンロケット」が発射を中止されました。
発射予定時刻まで秒読みは進みましたが、ロケット本体が自律的に予定時刻の19秒前に中止の判断をしたもようです。

原因は現時点では不明だそうです。
こうしたことは、まさに本番と練習の違いです。多くのロケットファンの方々が鹿児島県肝属郡(きもつきぐん)肝付町(きもつきちょう)の内之浦宇宙空間観測所の近くに集まり、今回の打ち上げ成功を見届けようとしました。今回はこの方々を残念がらせる結果になりました。
ここがロケット打ち上げ事業の厳しさでした。本番と練習の違いが、実際にはどの程度の差になっているのかという今後解析される事実が、日本の本格的なロケット打ち上げビジネスを大きく左右します。今回は、ロケットの打ち上げ失敗でない点がまだ救いですが、発射中止の実態は解明中です。
8月27日夕方に宇宙航空研究開発機構が開催した記者会見では、イプシロンロケットプロジェクトチームのプロジェクトマネージャーを務める森田泰弘さんは「地上の計算機がロケットの姿勢(ロール角:長手軸周り)異常と判断して発射のシーケンスを停止させたと考えている」と説明しました。そして「ロケットの機体は全く動いておらず、機体そのものには異常はなかった」と説明しています。
この記者会見に同席した宇宙航空研究開発機構の理事長の奥村直樹さんは「支援してもらった国民や関係機関、企業の期待に沿えず申し訳ない」と陳謝たそうです。そして「早急に原因究明に全力をあげたい」と述べました。事前に、今回のロケット打ち上げが日本の本格的なロケット打ち上げビジネスの道を切り開くとのプレゼンテーションを繰り広げたことへの言い訳です。
今回の「イプシロンロケット」ではまだ実現できていませんが、2017年度に打ち上げを目指している改良型では、打ち上げ費用を30億円以下に低減する目標を掲げており、日本が本格的にロケット打ち上げビジネスに参加する計画です。
取りあえず、数日後の「イプシロンロケット」の打ち上げ成功を祈念しています。
発射予定時刻まで秒読みは進みましたが、ロケット本体が自律的に予定時刻の19秒前に中止の判断をしたもようです。

原因は現時点では不明だそうです。
こうしたことは、まさに本番と練習の違いです。多くのロケットファンの方々が鹿児島県肝属郡(きもつきぐん)肝付町(きもつきちょう)の内之浦宇宙空間観測所の近くに集まり、今回の打ち上げ成功を見届けようとしました。今回はこの方々を残念がらせる結果になりました。
ここがロケット打ち上げ事業の厳しさでした。本番と練習の違いが、実際にはどの程度の差になっているのかという今後解析される事実が、日本の本格的なロケット打ち上げビジネスを大きく左右します。今回は、ロケットの打ち上げ失敗でない点がまだ救いですが、発射中止の実態は解明中です。
8月27日夕方に宇宙航空研究開発機構が開催した記者会見では、イプシロンロケットプロジェクトチームのプロジェクトマネージャーを務める森田泰弘さんは「地上の計算機がロケットの姿勢(ロール角:長手軸周り)異常と判断して発射のシーケンスを停止させたと考えている」と説明しました。そして「ロケットの機体は全く動いておらず、機体そのものには異常はなかった」と説明しています。
この記者会見に同席した宇宙航空研究開発機構の理事長の奥村直樹さんは「支援してもらった国民や関係機関、企業の期待に沿えず申し訳ない」と陳謝たそうです。そして「早急に原因究明に全力をあげたい」と述べました。事前に、今回のロケット打ち上げが日本の本格的なロケット打ち上げビジネスの道を切り開くとのプレゼンテーションを繰り広げたことへの言い訳です。
今回の「イプシロンロケット」ではまだ実現できていませんが、2017年度に打ち上げを目指している改良型では、打ち上げ費用を30億円以下に低減する目標を掲げており、日本が本格的にロケット打ち上げビジネスに参加する計画です。
取りあえず、数日後の「イプシロンロケット」の打ち上げ成功を祈念しています。